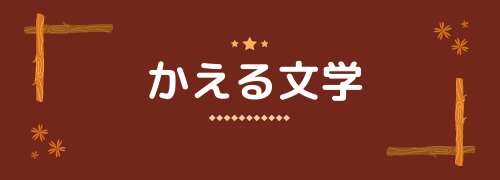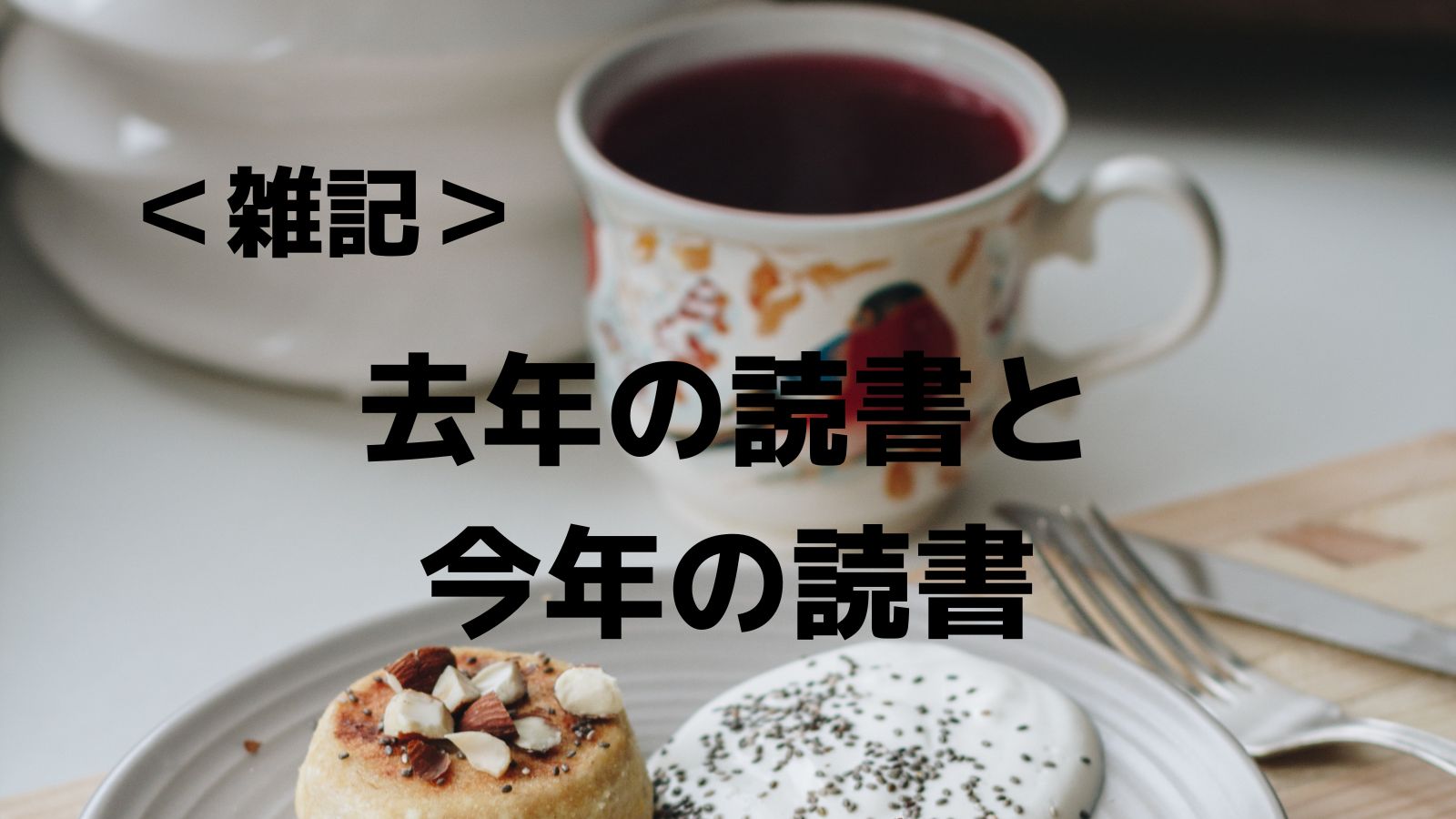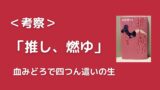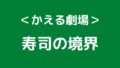新年が明けても、読書を生活の中心に据えてコーヒーをお供にして寝起きするライフサイクルは変わりません。
変化があるとすれば、朝ごはんがパンからお餅になったことぐらいですが、それもあと1週間くらいで元に戻り、通常の日常が帰ってきます。
そんなわけで、今年もおそらく沢山本を読むでしょうし、読みたい本は沢山あるわけですが、一回ここらで去年の読書を振り返ってみたいと思います。
昨年は年が明けてしばらくは、エンタメ小説や日本の文学を中心に読み進めていました。
印象に残ったのは、宇左見りんさんの「推し、燃ゆ」と凪良ゆうさんの「流浪の月」です。
この二作は<考察>でがっつり取り上げていますが、「推し、燃ゆ」は現代版の斜陽ともいえる内心の叫び文学のアップグレード版であり、最高でした。
↓「推し、燃ゆ」の考察
そして「流浪の月」は映画化もされましたが(まだ見ていない)、優しく生きづらい人の現在の地点と生き方を優しく照らす唯一無二の作品でした。
↓「流浪の月」の考察
そしてこのブログで特に取り上げていなかったんですが、佐藤究さんの「テスカトリポカ」もとても楽しく読めました。
メキシコの麻薬組織の抗争を舞台に繰り広げられる重厚かつ壮大なエンターテインメントなのですが、その核となるアステカの神々や宗教のパートが、とても神秘的かつ恐ろしく、爽快でありつつも深い闇の香りが漂う名作でした。
その後夏が近づいてくると、私の中で毎年恒例のSFブームとそしてゲームブームが訪れます。
印象に残ったのは、劉慈欣さんの「三体」と、アイザック・アシモフさんの「銀河帝国の興亡シリーズ三部作」と「永遠の終り」です。
「三体」に関して言えば、これぞ壮大な本格的思想系SF!といった感じで、ラストまで読んだときの自分という存在が、宇宙という壮大な砂時計における一粒の砂粒になったような感覚と言いましょうか・・・とにかく素晴らしかったです。
私の中でSFの二大傑作は、小松左京さんの「果しなき流れの果に」と光瀬龍さんの「百億の昼と千億の夜」なのですが、それに並ぶとも劣らないSFの傑作小説だと思いました。
そしてアシモフですが、銀河帝国シリーズは最初は
「古典的名作だからとりあえず読んでみるか」
的なノリで読んでいたのですが、これがどっこい圧倒的に面白かったのです。
特にミュールという不思議な力を持つミュータントが出てきてからは物語が加速し、予想を裏切ってくる展開が続くわけで、本作がずっと読まれてきたのが納得出来ました。
「永遠の終り」の方は、いわゆるタイムトラベルものなんですが、本作においても王道的な展開でありながら、謎を散りばめ、そしてそれを裏切りつつ、しっかり奇麗に終わらせており、本作を読んで
「ああ、アシモフは何を読んでも面白いんだろうな」
というような、ずっしりした信頼感を植え付けられました。
そしてゲームですが「ペルソナ5」と「十三機兵防衛圏」が最高でした。
ペルソナ5については本ブログで取り上げていますので、ここではは言及しませんが
↓ペルソナの記事
ここで言いたいのは「十三機兵防衛圏」です。
本作は2019年にヴァニラウェアが開発し、アトラスより発売されたゲームソフトで、あらすじとしては1945年・1985年・2025年・2065年・2105年の5つの時代を舞台に13人の主人公を操作して、人類を襲ってくるようになった機兵の謎に迫っていくというSFアドベンチャーゲームです。
そして本作がすごいのはシナリオとシステムです。
まずシナリオは謎が謎を呼び、そして辿り着いた認識が次の展開で覆されるという転回転回の連続で息をつく隙を与えません。
そしてその物語の展開も、古今東西のSFの良いところてんこ盛りみたいな内容で、なんていうか勢いがパワフルなのです。
そして本作で特徴的なのが「クラウドシンク」というシステムです。
これは主人公たちが会話で手に入れた「重要な情報」や「言葉」が誰かと会話するときに、頭の上空にセリフにように選択肢として浮かび上がってきて、それをどのタイミングで選び相手に問いかけるかをプレイヤーが判断するシステムなのですが、これが最高でした。
ただシナリオの文字を読むだけに終始しがちなアドベンチャーゲームにおいて、このシステムは本当にリアルな会話の感覚をプレイヤーに想起させ、直観的にゲームに入り込めるような仕様になっているわけです。
そんなわけで夏は最高のゲーム体験をしたわけですが、夏以降に関してはロシア文学・ドイツ文学ブームの嵐が私を襲いました。
手始めは「トーマス・マンショック」です。
私は、何年か前に「魔の山」を読んで面白いとは思いながらも、特に夢中になるほどの熱気は持っていなかったのですが、短編の「トニオ・クレーガー」を読んで衝撃を受けました。
そして、「すげかえられた首」「ヴェニスに死す」「詐欺師フェーリクス・クルルの告白」と読んでいったわけですが、正直どれも珠玉の名作でした。
文体もさることながら、芸術家と市井の人の対比や、繊細な日常における感情の揺れる瞬間や隙間をこうも美しく描けるのはとんでもないことだと衝撃を受けたのです。
ロシア文学の方は、やはりドストエフスキーです。
ドストエフスキーに関しては、何年か前に「カラマーゾフの兄弟」を読んで衝撃を受けて
「この作家は、全作品読まなくてはならない!」
という決意を固めたのですが、その決意は実行されないまま何年かが過ぎ←私はこういう人間です
そしてようやく去年に「罪と罰」「地下室の手記」「死の家の記録」「白夜/おかしな人間の夢」「永遠の夫」と、何作か読むことが出来ました。
そして実感したのは、やはり面白いということと、ドストエフスキーと自分と感覚が似ているということです←おこがましいにもほどがある
ドストエフスキーの小説は、自意識がこんがらかった人や、気持ちや気分の倒錯に負けて流されていく人という、いわゆるダメ人間がかなり出てきますが、そのダメ人間こそ私なのです←何だか偉そう笑
本当にドストエフスキーの本を読むたびに、自分のことを言われているような感覚に陥り、不思議な共感覚に陥るのです。
↓ドストエフスキーとトーマス・マンの記事
そんなわけでそれ以降の秋から年末までは、ドイツ文学やロシア文学を読もうと目標を立てたのですが、今の私は早くもその目標を忘れ、バルザックやジッド、スタンダールといったフランス文学を読んでいます。
つまりここに来てようやく悟ったのが、私は狭い範囲の目標を立てても何ら実効性を持たないし、長続きしないということです。
そんなわけなので、今年の目標は「ヨーロッパの古典文学」を集中して読むということにしたいと思います。
とはいえ面白そうであれば国内文学だろうと、漫画だろうとアニメであろうと見たり読んだりするわけであり、まあとにかく「心が動く面白い物」に触れて行こうということです←さっそく上記の目標がうやむやになりそうな予感笑
とにもかくにも、今年も色んな事を読んだり書いたりしていくので、どうぞよろしくお願いいたします。