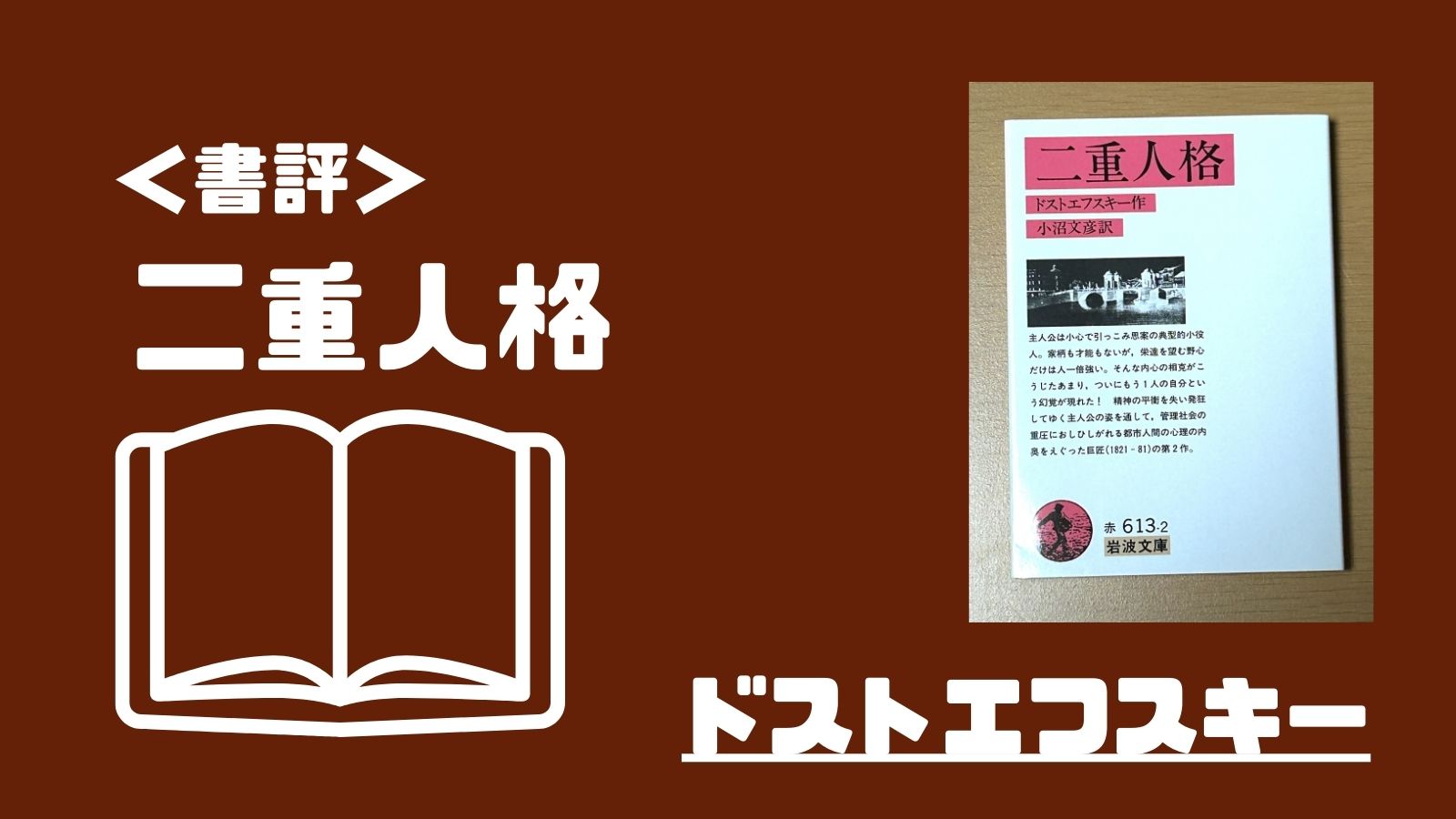「二重人格」は、19世紀ロシアの世界的文豪、フョードル・ドストエフスキーの二作目の中編作品です。
「貧しき人びと」で華々しく文壇にデビューし、本人も自信満々に発表した本作ですが、その幻想的作風もあり、当時は芳しい評価が得られなかった本作。それでもドストエフスキーは終生この作品を大事にしていたようです。
本作を読了してみて、私は大事に思っていた理由が分かり、そして納得しました。
本サイトにおいて、ドストエフスキーの「地下室の手記」という作品の考察をアップしています。
↓「地下室の手記」考察
私は初めてドストエフスキーの作品を読むなら「地下室の手記」を、物語がリニアで、それでいてドストエフスキーの濃い成分や魅力が凝縮されているので、おすすめしています。
本作は、そんな「地下室の手記」という作品と、同じ精神を宿し、かつ対にもなるような内容なので、ドストエフスキーファンにとっては必読であり重要な作品のように思います。
本作のストーリーラインは至って単純で、うだつのあがらない都市の小役人のゴリャートキン氏が、ある日、自分と同じ姿をした人間(劇中で新ゴリャートキン氏と表現される)に出会い、彼に翻弄されながら、都市を這いまわるという内容。
「地下室の手記」も主役は元小役人でしたし、いかにドストエフスキーが、都市に生きるみみっちいスケールの、自分の利益に汲々とする小物を描くことにこだわり、それを通じ、何かを見出そうとしていたことが分かります。(人間は全員みみっちくどうしようもない側面を抱えている)
本作において面白いのが、第二の人格たる新ゴリャートキン氏が、主人公の理想を顕現してるだろうにも関わらず、かなり嫌なヤツな事です笑
自分が理想としている人物像を、自分自身が好きになれないというねじれ、かつ自分が上手くいかないのは誰かが邪魔をしているせいだという被害妄想が絡み合う辺りが、実にドストエフスキー作品っぽいです。
その意味で言うと、「地下室の手記」において主人公が嫌悪している「やり手タイプ」が具現化した様な存在が、本作の新ゴリャートキン氏とも言えます。
それらも含め、作品の比較論で考えてみると、思索と物語に重きを置いているのが「地下室の手記」なら、分裂や症状、そして行動に重きを置いているのが本作なのかなとも思うのです。
本作には、後の長編である「悪霊」や「白痴」に繋がるような、狂ったカーニバル的な要素や、意志に反し突発的に行動してしまう病理など、後のドストエフスキー作品に繋がる要素も沢山あります。
幻想的でかつ、冗長でクセのある繰り返しの表現も多く、その意味で読みやすい作品ではないかもですが、その分、魅力もあり、テーマ的にも非常に重要な作品だと思うので、ドストエフスキーファンには是非、読んで欲しい一作です。