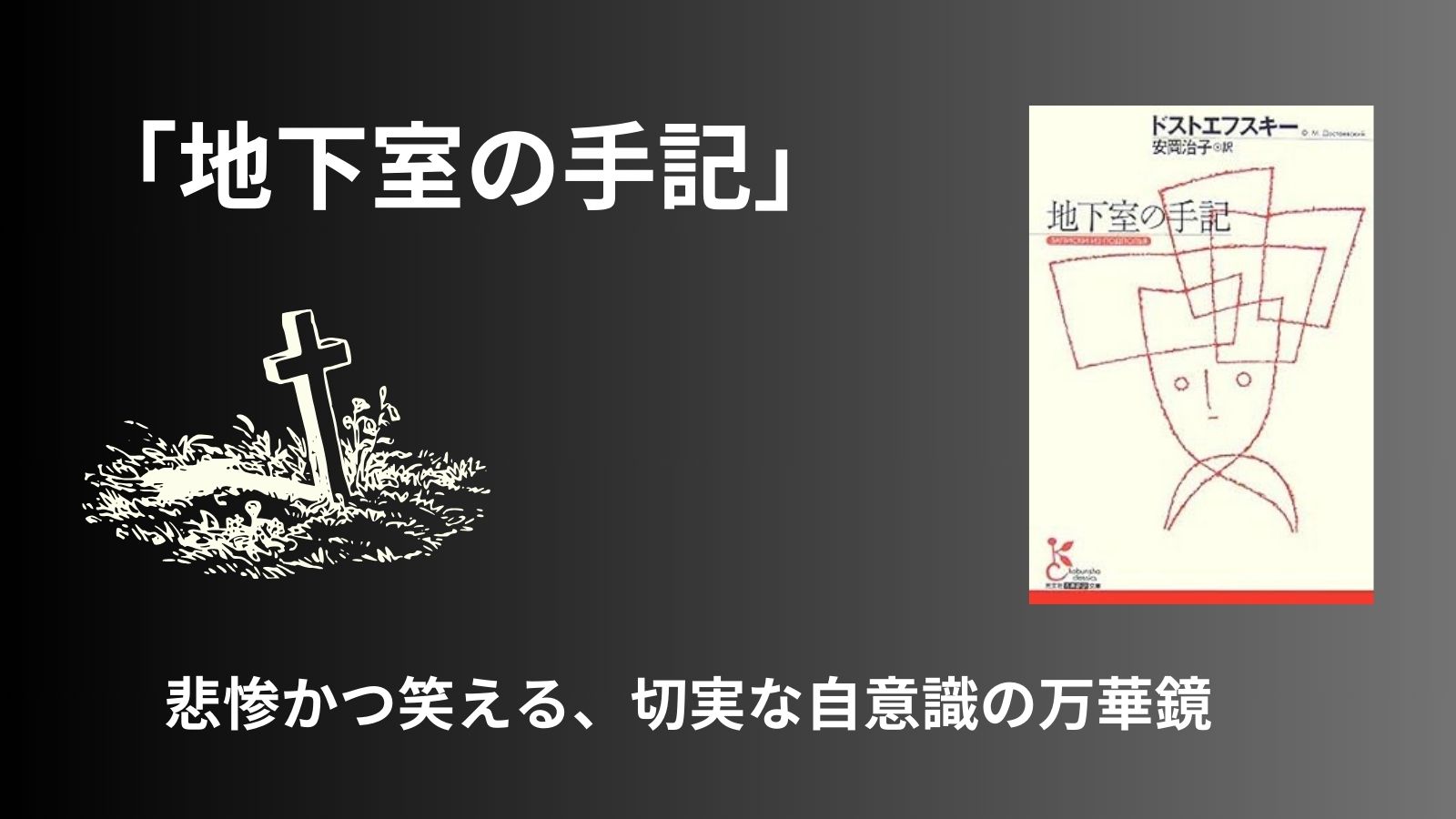「地下室の手記」は19世紀のロシアを代表する世界的文豪、フョードル・ドストエフスキーの中編小説です。
ドストエフスキーの作品の中では比較的短い作品でかつ、読みやすい本作。
しかしその内容は、「罪と罰」や「カラマーゾフの兄弟」といった晩年の名作へと連なるような、ドストエフスキーの濃密な魅力の汁のようなものが凝縮されている作品です。
量的にも読みやすいので個人的にドストエフスキーはこの作品から入るのがいいのかなあと考えています。
それでは以下、本作を自分なりに考察していきます。物語の内容のネタバレを含みますが、ドストエフスキー作品は私ごときの言葉でネタバレしたところで充分に楽しめる強度があると思いますので、気にせず読んでいいいかなとも思います。
とはいえネタバレが嫌だと言う人はここまででストップしてください。
本書の構成について
本作は、役所の八等官として働いていた主人公が、昨年親戚の遺産を手に入れ退職し、ペテルブルグの町はずれの家に引きこもり、そこで自説や哲学的省察をくどくどと並べて立てる第一部の「地下室」。
そして「ぼた雪に寄せて」というタイトルがついている、主人公と売春宿にいるリーザとの間に起こった出来事を主に語られる第二部とで構成されています。
第一部の自説の部分は、こちらの反応を先回りしたり、自分の自意識への省察が行ったり来たりするので、中々面倒くさいですが(しかしクセになる言い回し)、ただし書かれている内容については核心を突いていたり、意外性があったりと豊かな知見や宝石が詰まっています。
第二部は、主人公の過去の出来事を振り返るわけですが、これは第一部で述べた思想が現実に放り込まれたらどうなるか、という実践的な側面があり、主人公の自意識が現実の人間と対峙して、どんどん悲惨な方向に転がっていくのを眺めることになります。
やり手タイプと自意識タイプ
本作の主人公の思考は、ひねくれてねじ曲がっています。
その主人公が、糾弾するのが「やり手タイプ」です。
本作の舞台は19世紀のペテルブルグであり、特に世紀の後半は科学的合理主義が人々の思想の中心を占めていました。
そんな人々を主人公は糾弾しているのですが、これは科学を信じ、努力を積み重ね、お金を獲得し、出世し幸せを獲得していく、今でいう猛烈サラリーマンタイプに近い人物のことだと私は自分なりに解釈しています。
努力して、建設的に幸せを獲得出来るのだからいいのではとも思いますが、主人公は彼らを実は自分の頭でろくすっぽ考えていない馬鹿だと見下しているのが文章から伝わってきます。
「何者かになりうるのは愚か者だけ」「俺は誰より賢いから悪い」この発言には、科学法則を無条件に信じて邁進してしまえる人への嘲笑、さらに言えば鈍感に目標だけに邁進出来る人の神経の太さへの嘲笑という二種類が含まれていると思います。
そしてこの主人公が一筋縄でいかないのは、やり手タイプを糾弾していながら、その逆である自意識過剰な人(自分自身)も糾弾しているからです。
自意識過剰な人を、化学実験装置の蒸留器から生まれたと揶揄する描写は、自意識もまた書物から与えられた、頭でっかちな机上の空論だ、という嘆きを感じます。
自分を含めたそう言う人を「ネズミ」と言い、それらの人は疑問や疑惑を自意識の上に積み上げ、身動きが取れなくなり、結局、地下室に潜り込むしかなくなるとも言います。
その対比で結局は、考えないで目標に邁進出来る愚鈍な人の方を「自然と真理の人」と言っているわけですが、こう書いていながらも「やり手タイプ」を心の底では認めていないのが透けて見えます。
主人公が言っている主張は、なかなかじめじめしているし、言い訳だと思う人もいるでしょうが、個人的には面白くかつ、とても共感出来ました。
あの時代のペテルブルクと今の日本を同じように比較するのは無理があると思いますが、日本社会では、今なお、社会の部品として盲目的に努力を積み重ねるタイプが尊ばれ、出世していくのが現実です(30人も同じ教室で同じ競争をさせてる学校なんてその典型)
建前として個性個性と言いますが、物事をしっかり自分なりに考えようと思って1年間休んだりしてしまったら、その時点で落伍者認定されてしまいます(とはいえ現在はまだよくなった)
私は、個人的に物を考えたり、何かぶらぶらと興味があるものを探す時間こそが人生において大事だと思うし、キャリアアップ、キャリアプランとかいう言葉が好きではないので、主人公の主張には共感する部分が沢山ありました。
無慈悲な自然法則
本作の主人公が本質的に敵視しているのが、「科学的自然法則」です。
これは二×二=四の様な計算式で、全てが対覧表の様に説明出来る科学法則のことであり、前項の項目と併せて、この科学法則を前提に合理的で資本主義的に生きている人間を軽蔑しています。
主人公いわく、もしこのような法則が全てなら、自分の意志や責任なんて存在せずに、腹を立てる相手すら見当たらなくなってしまうと言います。
復讐や憎しみすら「それは法則」「それは反射」の様に分解され、結局、壁をぶん殴るしかなくなると言い、主人公の中で自然法則というものが、人間にとっての大きな壁であるという認識であることが分かります。
本作に出てくる重要ワードに「水晶宮」という言葉があり、これはすなわち人間にとっての理想の世界を指していますが、主人公のそれと、世間の「水晶宮」はまるで違うものです(詳しくは後の項目で)
世間の夢見る合理的で一覧表のような水晶宮。そんなものがあるなら欲求はなくなり、全てを受け入れるしか無くなると言い、そんなものはピアノキーに過ぎない、つまり全体の機械的な部品に過ぎないと言っているわけです。
しかも人間は、理性を信奉し、戦争や虐殺をダメだと分かっていながら結局これを繰り返します。
主人公はもし、そっちのやり方(科学法則の水晶宮)でよくなるならそれでもいいと言っていますが、世界から争いはなくなっていません。
本作は、19世紀のペテルブルグが舞台の小説であり、あの時代のペテルブルグは科学的合理主義が形成した先進的で実験的な町であり、おそらく合理的で何の疑いもなく働き続けるやり手タイプで溢れていたのでしょう。
だからこそ、主人公の批判は、科学ややり手タイプに向くわけですが、その主人公が反対に重視するのが「欲求」と「倒錯」であり、さらに奥には彼なりの「信仰」というものが隠れています。
欲求・気まぐれ・呪い
本作の主人公が、自然法則の壁を打ち破る切り札的に考えているものがあります。
それが気まぐれな欲求です。
美徳をわきまえ生きてきた人が急な行動で全てをぶち壊したりする「突飛」な欲求。
理性は理性的側面に過ぎないが、欲求こぞが全生活とし、その気まぐれこそが自由意志と個性を守ってくれると主人公は言います。
前項で述べた全体の部品に過ぎないピアノキーでないことを確認するには、デタラメ、奇想天外の要素や願望こそが大事であり、さらに言えば破壊や混乱、苦しみや呪いの効用を語る主人公。
特に呪う事が出来るのは人間だけだといい、呪うことにより、ピアノキーで無いことを確認出来るといいます。
ただしもし呪いすら、理性による対覧表で止められてしまうなら、その時はわざと狂人になるとすら言っています。
以上の様に、これは非常にデーモニッシュな思想ですが、その根底には意志・思考の自由への強烈な信奉心があります。
絶対に、自分は社会の部品の様な機械的な存在にはならない、その覚悟なのだと私は本作を読んでいて感じました。
僕は現在、生きるというのは、なめらかで流れていくような丁度良い幸せなバランスを見つけることだと考えており、それが軸としてあります。
しかし、それは別に今現在そう思っているだけであり、いくらでも変化していく可能性があるわけです。
その意味で、主人公の考え方は人生を考える思考材料の一つになりえるし、理解出来る部分も多いです。
急に来る欲望や願望、その力強さははかりしれないものがあります。また私自身、子供の頃から変わっていると言われて育ったためか、変なもの変わったもの、突飛な展開の物語を見たり読んだりするとアドレナリンが出る体になっています。
個人的に気まぐれな欲望と欲求が行きつく先に何かがあるなら、それはそれでとても興味があるし、そちらの未来がカオスだとしても、そこにそれなりの幸せがあるなら見てみたい気もします。
気まぐれの欲求が倒錯的な快楽を生む
人間の生きる目的は快楽を感じることにあります。
そしてその快楽を求める心が欲求であり、この二つは密接に結びついています。
本作の主人公は、「歯痛」のような、「闘うべき相手が見当たらない、悪意のこもったうめき声のような痛み」にも快楽はあると言っています。
それどころか、血みどろの屈辱や誰かから分からない嘲笑こそが、時に快楽の絶頂をきわめることがあるとも言っており、これはかなり倒錯的です。
しかし現代の日本でも、痛みや苦痛が待っていると分かっているのに、背徳感から不倫に燃え上がったり、寝取られなんていうジャンルもまた倒錯的であり、痛みと屈辱を快楽に変えるタイプのものです。
個人的にも人間には安息だけでなく、苦しみや痛みを求める欲求みたいなものが組み込まれているように感じます。
特に難しく考えない、もしくは単純に健全に考えたい人は、苦しみを努力に置き換え、その後来る快楽を成功に置き換え、なんてことなく生きていくことが可能でしょう。
しかし、物事を疑いながら考えていく性格の人は、その理性的な置き換えに満足することなく、常識的な快楽に疑いをもちます。
そして自分の知らない領域や、自分の意図しない欲望を集め・広げていくことになるわけで、これは好奇心と表裏一体のものだと思います。
本作の主人公は、そこに理性的な対覧表への嫌悪感もプラスされるので、無意識にそこから飛び出そうと、突飛で倒錯的な苦痛の中へ飛び込んでいくことになるのです(これが第二部)
さらに主人公は人間が破壊と混乱を愛すのは、本能的に目的の達成を恐れているからで、人の目的は達成せざるプロセスの中にあるのではとも言っていますが、慧眼だと思います。
人間文明がこうも発展してきたのは、完成に安堵するのではなく、常に成長する意志を持ち続け、スクラップ&ビルドを繰り返してきたからだと考えると、破壊的な性衝動や突飛な全てをぶち壊す欲望も理解が可能です。
村上春樹やペルソナシリーズでは、こういう欲望を制御しバランスを取ることが大事だということを言っており、自分もそうだと思いますが、本作の主人公の突飛な欲求や痛みこそが自分の意識や個性を担保するという思想も一つの哲学としては、理解出来ます。
苦しみは意識の唯一の根拠
本作の主人公は、前の項でも述べた、二×二=四に代表される、対覧表的な科学法則に対するアンチテーゼを根本に抱えています。
何も考えないですむような平穏無事だけが幸福ではない、また苦しみやきまぐれこそ幸福なこともある。
そう語る背景には、全てがあらかじめ決まっていて自分の意志が存在しないような安息に対して、強烈な反発心があります。
生きていれば本物の苦しみや破壊や混乱は拒めない、なぜなら苦しみこそ意識の唯一の根拠だという主人公の意見は、一見すると極論にも思えます。
しかし、意識を持っていることこそ人間にとっての最大の不平であるという言葉により、上記の言葉の説得力が増します。
意識があるから苦しみがあり、意識が無ければ苦しみなど無いからです。
しかし人間はそれでも絶対に意識を捨てたりはしない。ここに主人公が苦しみと意識を結び付ける思想の肝があるように思います。
二×二=四の様な科学法則は、最後、瞑想みたいなのしか必要としなくなるのに対し、苦しみを伴う意識は己をむちうつことは出来るといい、徹底して原理的な部分まで考え抜く主人公。
一方個人的な意見としては、人間には苦しみを求める倒錯的な欲望もあると思いますが、それ以上に慈愛・優しさという要素も意識の要素として確実にあると思います。
しかし本作が面白いのは、実は主人公もまたそのことは分かっているということなのです。
具体的に第一部では書かれませんが、第二部の発言と第一部で検閲により落とされた部分を想像することで、その思想は見えてきます。
その主人公の真の水晶宮については最後に考察することにして、次の項目では第二部の主人公の悲しきドタバタ喜劇を考察していきます。
第二部という哀れかつ笑える狂騒
第二部では、主人公の過去の出来事。主に売春宿にいたリーザとの会話が描かれます。
その本筋の話の前に、将校や友人とのエピソードが描かれるわけですが、これがまあ悲惨です笑
道を通るために自分を物のように動かした将校を何年も根にもち、しかし勇気がわかず、最後ぶつかって溜飲を下ろしたり。
相手が明らかに自分に好意を持っていない友人たち(もはや友人とは呼ばない)の集まりに無理に参加し、あげく下ネタトークで盛り上がっている時に「俺は色事師は嫌いだ」と言い、さらに嫌われ、あげく友人たちが移動したソファーの前を気にかけてほしくて何時間も歩いたり(まさに悪夢)
最後にはリーダー格の友人に侮辱したことを許してくれたまえと泣きつく始末で、これだけでも最悪なのに、そいつから「君なんぞに僕が侮辱されるなんてことはありえない」とバッサリ切り捨てられてしまいます。
リーザのいる売春宿に行くことになったのも、友人連中をひざまづかせるか、そのリーダー格に平手打ちするかという目的であり、自意識がこんがらがり、どんどん哀れな方に転がっていく様もここまでくると笑えてきます。
そもそもその後、リーザと出会い、本心をさらけ出す交流が描かれますが、入りとしては風俗に来てるくせに、風俗嬢に説教をするオヤジそのものです。
第一部では、理性による対覧表や、意識や苦しみなど、かなり哲学的な事も語ってるくせに、何でこんなことになるんじゃい笑 と最初読んだ時は思いましたが、自分のプライドや自意識が高すぎて、侮辱が許せず、かつ突飛な行動や欲求により、どんどん自分が侮辱の海に落ち込んでいく様は、まさに第一部の苦痛こそ意識の根拠だという説の実践なのではとも思えます。
リーザとの交流も、本心をさらけ出し、自分の惨めさを吐露し心が通じたはずなのに、リーザが精神的な優位の位置に立った事、支配欲や所有欲が絡みついた情熱、等々が絡み合い、その熱に任せ復讐のようにリーザと性的行為に及びます。
これもまさに突飛な欲求や憎しみに身をゆだねた結果ですが、さらに最悪なのは書物で読んだシーンの再現かのごとく、リーザに金を握らせたことです。
そしてリーザはその金をしわくちゃにし出ていき、第二部の過去の事件は終了になります。
そんなわけで読後は「はあ、何やってんだよ」と寂莫とした何とも言えない感情になるわけです笑
ただしエピソードは、本物の愛の前でもそれを信じ切れずに、自意識と憎しみの自縄自縛で踊るという本作の主人公、というより本作のテーマ性が高度にまとまっているシーンでもあります。
そんなわけで第二部は、第一部で行ったり来たりしている自意識を現実に放り込んだらこうなるよ、という劇場であり、それはとても笑える喜劇でありながら、非常に哀れな悲劇でもあるのです。
ぼた雪、センナヤ広場の地下室の棺、じめじめしたぬかるみ
ここでは第二部のタイトルの一部でもある「ぼた雪」とリーザとの話の中で出てくるセンナヤ広場の地下室の墓地、ぬかるみの中に埋葬される棺の話の象徴性について述べていきます。
主人公は、地下の棺は後のリーザのなれのはてだと表現しますが、これらのことは主人公自身の精神も象徴しています。
雪がとけかかっているぼた雪。
この中途半端にとけかかっている状態は、自意識と理性とプライドが溶けあっている主人公の精神状態の象徴のようですし、その水が地下の墓地や土に染みこんでいる状態も、地下室で引きこもり、自意識をドロドロにかき回し続ける主人公にリンクします。
プライドや自意識により、疑いや欲望の渦の中で思考を続け、どんどん自意識や思考の部屋から出れなくなっていく主人公の様子が、高度に象徴されているのがこれらの描写だと思うのです。
主人公が求める真の水晶宮
本作は、第一部の水晶宮の部分に検閲が入り、作者が述べた重要部分が削除されています。
文脈からみても、主人公が求める水晶宮は、理性の対覧表のような水晶宮と別にあることは明らかであり、この真の水晶宮を暴くことが、本作の主人公の精神の深層に抱えるものを知ることになります。
そしてこれは第一部の前後の文脈や、リーザとの会話に割としっかり描かれていると思います。
売春宿にいるリーザに説教をする最中、自分の気持ちのたがが外れ本音を吐露していくシーン。
「恋愛によって結ばれたからには愛が過ぎ去ってしまうことはない」
「時間が経っても、新婚当初よりもっと素晴らしい愛が生まれる」
「子供はそんな感情や思考を保ち続けていく」
そうなのです。本作の主人公の精神の深層にはこのような愛の概念が生きているのです。
この愛の概念を踏まえ、さらに第一部の文脈を見ていきます。
主人公が敵視する、理性の対覧表のような、自分の意志が存在せずに、苦しみや不健全な快楽を排除してしまうような水晶宮。
主人公はそれをアカンベエ出来ない水晶宮と表現します。
そしてその後、おそらく自分が求める真の水晶宮について、「我々世代特有のある種の旧き不合理な習慣から創り出したもの」と語り、それは自分が願望を持つ限り存在すると言っています。
これは文脈から判断するに「信仰」だと思います。そうなのです。主人公は理性であつらえた水晶宮は否定していますが、信仰は否定していないのです。
さて上記の「愛」と「信仰」の二つについてをまとめてみようと思います。
主人公の水晶宮とは、理性と科学に裏打ちされた西洋的な価値観ではありません。
苦しみや、突飛な欲望の発露や倒錯を全て包み込むような寛容さがあり、精神の重要さを説くだけでなく、大地に根差した生活全てを祝福するような水晶宮。
それは生活や肉体の全てを肯定するので、肉体の重さや苦しみを含むことになります。しかしそれらの全てをお互いに対する愛が包み込み、そしてそれを受けついていく子供により愛が広がり保持されていく、そういう大地に根付いた水晶宮こそが主人公の理想だと思うのです。
本作の主人公が最後に言う。「君たちは真の生き生きを知らない」「何を愛し何を憎むかも分からず本を取り上げたらお手上げで、固有の肉体さえ重荷に感じる始末」という言葉は理性による水晶宮を何も考えずに信じ切っている同時代人への強烈な言葉のパンチであり、その裏には自分が持つ真の水晶宮への信仰があるのだと思います。
本作の主人公、及び本作の精神
前項では本作の主人公が求める真の水晶宮ついて語りました。
しかしそうなると、何で第二部でリーザに対しあんな仕打ちするんじゃいとツッコミ入れたくなります。
そもそも本作の主人公は、悲劇的かつ喜劇的で個人的には好きですが、どこか狂言回しのピエロのような趣があり、現実感がありません。
私は、その理由が本作の主人公は、ドストエフスキー自身の作家的葛藤精神が具現化した存在だからだと考えています。
私がドストエフスキーの作品をある程度読んで感じたのは、この人は常に血を流すレベルで考え続け、そしてその迷いそのものも作品として昇華してしまうような、魂の発露の作家なのだろうということです。
人間には様々な人がいますが、どんな人にも愛を信じ慈しみ深い側面と同時に、暴力的な欲望を抱えている、私はそう考えています。
その慈愛の方に重きを置く作家は多く、そしてそれは素晴らしいことだと思いますが、慈愛だけでなく、欲望や混乱といった要素にもしっかりと視線を定め、徹底的に平等に考え抜き、人間存在を描こうとしたのがドストエフスキーだと思うのです。
その作家の精神の具現化が本作の主人公だとすると、屈辱と苦しみと愛の中で、血しぶきをあげて踊るピエロのような姿から、後の五大長編の輪郭が透けて見える様な気すらしてきます。
本作の主人公が最後に「俺は人生においてとことんやってみたかっただけだ」「君たちは半分もやる勇気がなかった」「臆病さを思慮と勘違いしてなぐさめてるだけ」と言い放ちます。
これは科学を無条件に信奉しているだけで何も考えず、常識やタブーについて鼻から考える事を否定している同時代人への強烈な皮肉です(現代人にも当てはまる)
何度も言いますが、ドストエフスキーは血を流しながらタブーなどの壁をとっぱらい、自意識の混乱や倒錯など、不完全である人間を考え続けた作家だと思っています。
そして本作の主人公、及び本作そのものがその精神を映した鏡の様な小説であり、だからこそ自意識は行ったり来たりし、徹底的に無様な姿を主人公はさらけ出すのです。
まとめるなら本作のテーマは行ったり来たりする不完全な人間精神そのものを描くことにあると言っていいかもしれません。
自意識の奥底で愛への信仰を隠していながらも、それを信じ切れず、憎しみや突発的な欲望に身をゆだねてしまう。
その姿を克明に徹底的に描くことで、読者の心には何かが刻まれ、それはおかしくもあり悲しくもあるような形容しがたい唯一無二のもの。
本作の主人公の主張が全て合致する人は少ないでしょうし、否定すべきだと思う人もいるかもしれません。
しかし自意識の揺らぎに裏打ちされ、行ったり来たりしながらそれでも深い部分に潜っていく言葉の中には、何かしらの宝物が必ずあるはずです。個人的に私にとっては宝物だらけでした。
めくるめく万華鏡のように人間精神の振れ幅や様々な可能性を見せてくれた本作に感謝して本考察を終えます。