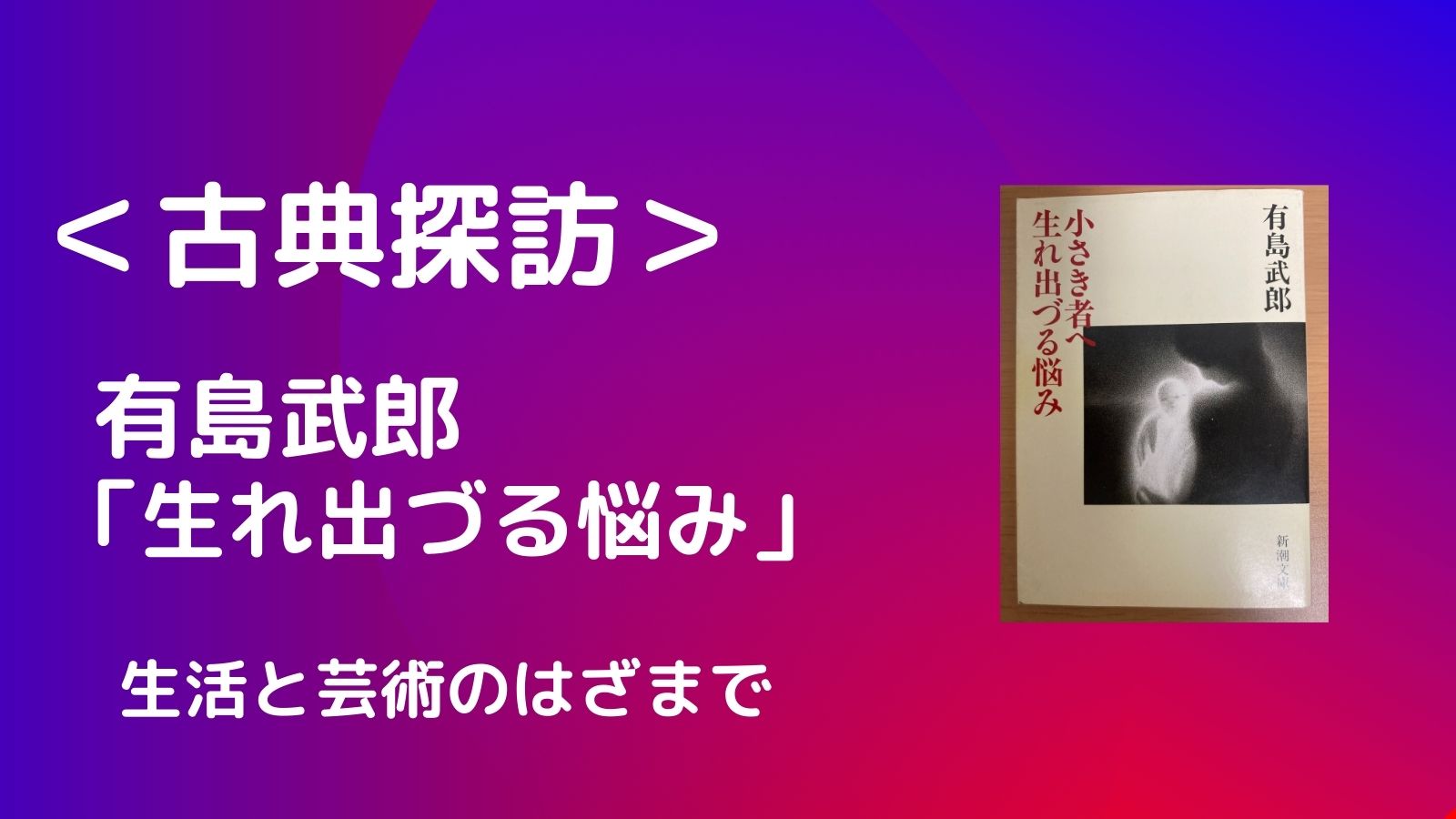「生れ出づる悩み」は、白樺派の作家、有島武郎さんの短編小説です。
力強い心理に迫った描写と、鼓舞するような文章で描かれる本作を自分なりに考察していきます。
以下、物語の核心部分に触れるので、ネタバレが嫌な人はここでストップしてね
ざっくりストーリー
主役である文筆家の「私」は、札幌で絵が書くことが好きな少年、木本と出会います。
しかし、数年後再会したときに彼は厳しく貧しい状況の中で、漁村の仕事に従事していました。
それでも絵をかくことを続けていた木本の絵に心を打たれた私は、彼の漁村での暮らしや彼が抱えた思いを、彼から受け取った手紙などをもとに、自分自身の想像で描写します。
そして最後は、「私」から、木本に対して、そして木本と同じように悩んでる人、さらに自分自身にも鼓舞するようなメッセージを伝え、物語の幕は閉じます。
心に迫る陶酔的な語り口
この小説の特徴は、その語り口でしょう。
特に中盤からの「私」が、木本と話したことや手紙から想像した、漁村での仕事や暮らしの様子や、船の帆が折れる事故などの描写は、想像したのではなく、まるで本当に木本に起こったことを見てきたかのような、圧巻の描写力で描かれます。
また木本の生活を想像で描写するときの呼び名が「君」に統一されているのも、木本のことを描きながらも、読者自身に語りかけてくるような印象を呼び起こさせます。
さらに、そこに作者の陶酔的な感情も加わるので、その熱量で自然と、こちらの体や心も熱くなってくるのです。
想像力の熱量を感じる一方で、読む人の中には、勝手な想像で自分の気持ちだけ盛り上がっていてついていけない、と思う人もいるのではと思います。
自分も、これは木本に起こったことを想像して書いているんだよなあ、という少しのもやもやを抱えながら読み進めていましたが、最後まで読んでそのもやもやは払拭されました(後述)
過酷な生活と芸術
「私」が描写した漁村での生活は過酷です。
木本自身から手紙ももらっていましたし、「私」も漁村の実態を人生の中で実際に見ているでしょうから、この描写は時代の現実を表してるといっていいと思います。
全身で肉体を酷使して働いても、お金はわずかしか入らず、一生懸命働くことにより、生活だけはしていけるものの、結局ほとんどの利益は海産物会社の大きい手によりかすめとられます。
そんな中で絵を書いていくことが、家族や周りに申し訳ないという気持ちも分かるし、しかしそれでも書きたいという葛藤も、とても共感出来ます。
時代は進みましたが、現代でも貧しい中で、自分だけが見える何かをつかもうと芸術や創作に従事している人が沢山いるのだと思います。
そしてその過酷な状況の中から出てくるもの、もしくはそれをもろともせず、自然の本質を切り取ることが出来る人が、芸術の光から手を差し伸べられるような気がするのです。
自分は裕福な人でも、その人なりの悩みや、そこからしか書けないものがあるとは思いますが、過酷な体験が精神に働きかけ、放出されるリアルさは、おそらく誰にも勝ちえないものなのかもとも思います。
作者自身の思い
「私」が想像で描いた木本の漁村での生活の描写は、作者自身の心の投影が、かなり入っていると思います。
そして、そこに見えるのは、過酷な生活から生み出す芸術への憧憬と、自分の恵まれた環境への罪の意識です。
ところどころに、東京で余裕をもって文章を書いている自分や、周りの状況に対する嘲笑が見られます。
そして、船の帆の事故や、漁村での暮らし、会社の抜け目なさ、デパートのいやらしい描写からは、作者自身が現在の世の中をどう思っているのかが、ありありと見えます。
根底に自分の東京の生活や社会への疑問、違和感がどっしり構えており、それが想像上の漁村の暮らしの描写に拍車をかけているように思えるのです。
木本の苦悩を描写しながら、そこに自分の苦しみも仮託している。
自分はそのように感じました。
そこに光をあてること
最後の場面で「私」は、この文章が想像であることを改めて言及したうえで、君よ!と再び木本にメッセージを送ります。
「自分がこの優れた魂の悩みに光をあてなければ、それを誰も知ることが無かったし、全ての現象は神秘に包まれていて、何をもたらすかわからない恐ろしい原因は、地球のどの隅っこにも隠されている」
とメッセージの中で語っています。
作者は、自分がこれを書くことにより、全国の至る所の片隅で、起きている苦しみや葛藤に光を当て、芸術を目指す人を鼓舞するメッセージになるという思いをこの小説に込めたのだと思います。
陶酔し、鼓舞するような言葉も、優れた魂の葛藤に光を当てたいという思いの表れなんだなと納得出来、もやもやしていた思いが消えていきました。
本当に取材をして、徹底的にリアルを書くというのではなく、会話や手紙から、想像を通じて自分のフィルターで書くところに、理性と想像力の光を信奉した白樺派や、作者の特徴があるのかなあと感じました。
最後のメッセージについて
最後のシーンで、木本が、ふっと緊張の糸が切れて、自然と崖の上に足が向かい、自殺の手前で踏みとどまる描写の、緊迫感や切実さは、こちらの心に刃の破片を埋め込みます。
我に返らせたのが、海産物会社の汽笛の音(資本の象徴の音)だったことも、現実の残酷さ哀しみに輪をかけています。
そしてそのあと、「私」の生を鼓舞する力強いメッセージになるわけですが、自分は個人的にこのメッセージは、本当にそう思っている側面もある反面、一方で理性の力で無理やり心の底から絞り出したような感じも受けました。
言うなれば、そういう風な社会を信じたい、目指していきたい、という願望を言い聞かせているように思えたのです。
しかし、つらい現実をみつめながらも、最後は「君よ!」と木本へのメッセージを通じて、読者や、芸術に生きる人に希望のメッセージでしめくくるところに、作者の優しさを感じますし、反面、ものすごく繊細で生きるのが苦しかったんだろうなあというのも伝わってきます。
さいごに
この作品は、非常に読者との距離が近く、心に語りかけてくる作品です。
この熱量を好きだという人もいれば、もしかしたら合わないと思う人もいるかもしれません。
個人的には、ものすごく作者さんの人格にシンパシーを感じ、想像力をやりすぎなくらいにエネルギーに変換した熱量に心が動かされました。
本作を読んで有島武郎さん自身にかなり興味が湧いたので、どこかで他の作品も読み、考察を書いてみたいと考えています。