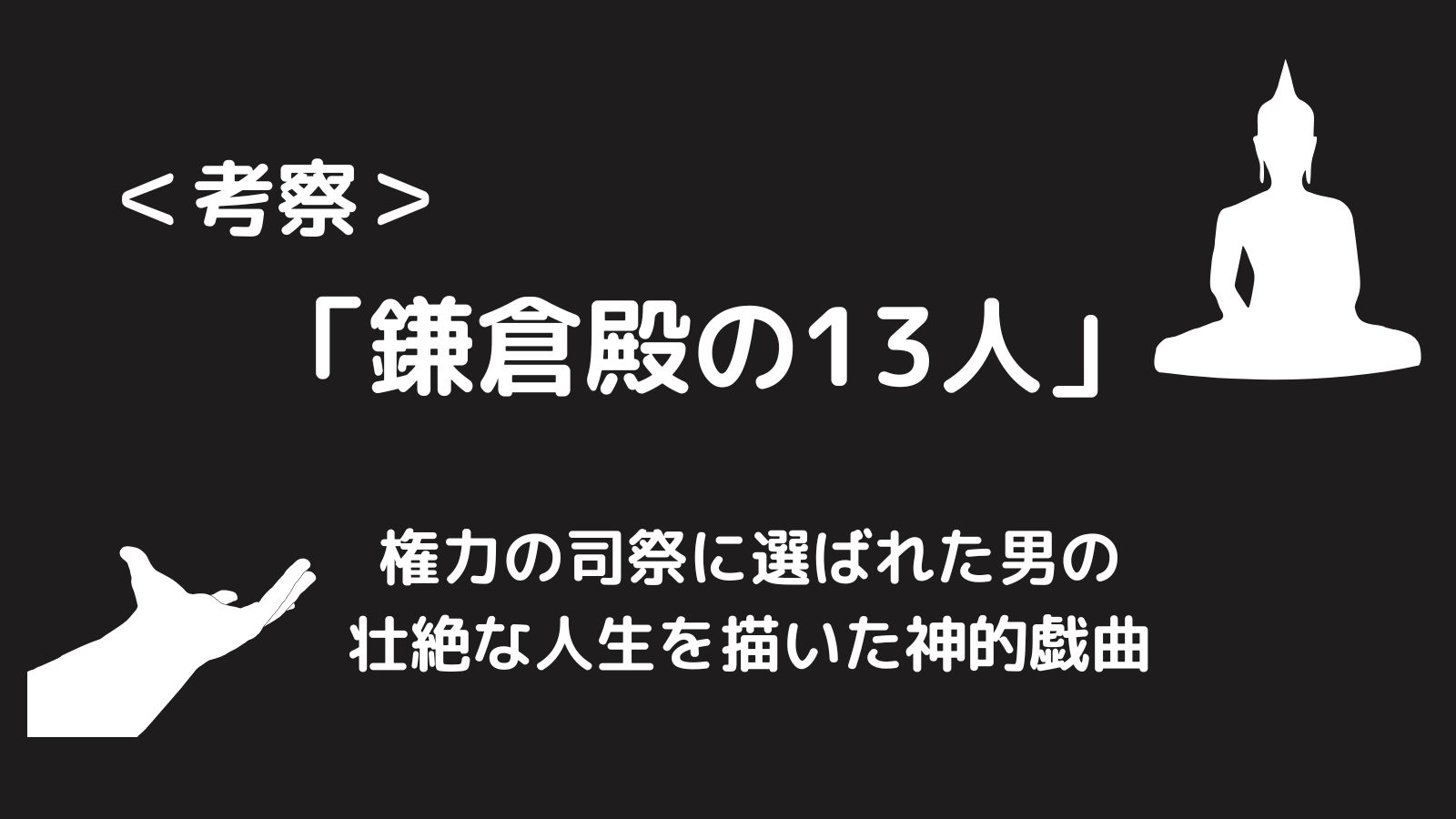鎌倉殿の13人は、2022年に放送された、三谷幸喜さんが脚本を務めた三作目の大河ドラマです。
血と陰謀が入り乱れ、面白いけれども複雑で難解な鎌倉時代初期というテーマを、分かりやすく描き切り、そして文学的価値の高みも兼ね備えた現代まれにみる傑作!
本当に1年間、ドラマのレビューをしてきて良かったと心から思います。
そんな本作を、自分なりに考察していきます。
以下の考察は、物語のネタバレを大いに含むので、それでもいいよって言う人だけ見て下さい。
神的戯曲
本作は、とても戯曲的な作品です。
戯曲とは、小説のような風景の描写や地の文やセリフなどを併せ、それ自体で読み物として完成されているものではなく、基本的に人物のセリフの掛け合いで構成され、舞台で上演されることを前提にして作られた物のことを言います。
三谷幸喜さんは演劇畑の人なので、本作が演劇テイストが強いのは当然ではあるのですが、本作は三谷さん自身がシェイクスピアを参考にしたとも言われているように、よりその要素が強いです。
実朝が暗殺された鶴岡八幡宮の階段が舞台のようで主要人物が見上げるようになっていたり等、場面の作り方も舞台的で、そして人物がなるべく同じ場所にいるように配置されています。
戯曲は人と人の会話こそが重きを成しますが、本作も非常に人と人との会話こそが重きを成しており、そこが非常に戯曲的です。
そして本作の特徴は、複雑な鎌倉時代を誰にでも分かるようにカリカチュアしていることです。
細部よりは大まかな事実の抽出に重きを置き、歴史に詳しくない人も脱落させないような作りは非常に見事だと思います。
また本作では会話に重きを置きつつも、その背景の光や画、人物の表情により言葉では表現出来ない事柄の具現化にも成功しています。
そしてシェイクスピアなどの欧米の戯曲のように、会話の掛け合いや、光や表情により、最後は神的ともいえるような普遍的で深的な場所まで辿りつくのであり、その意味で本ドラマは本当にすごい作品なのです。
権力の司祭となるまでの義時の変遷
本作の主役である北条義時。
私はドラマ後半、「果たして尺が足りるのか?」という心配をしていましたが、終わってみれば完璧な構成でした。
伊賀氏の変とか、泰時の政治シーンを見たいという欲張りな願望はありますが笑、義時の人生という点で見れば、これぞ至高の構成だと思います。
本作は1~26話位までが、頼朝の元での見習い編。
27~38までが頼朝の死後の混乱と、そして義時が父を追い出し執政者としての覚悟を決めるまで。
そして39話からラストまでが、権力の司祭として君臨し、そして一人の人間、政子の弟として死ぬまでが描かれました。
その中で非常によく書かれていたのが、義時に影響を与えた事件と心情の変化の描写です。
まず最初に義時に打撃を与えたのは上総広常の暗殺でしょう。
頼朝にとって最大の脅威であるとはいえ、義時を頼りにしてくれた広常が目の前で殺されるのを見ている事しか出来なかったわけで、その時の義時の表情は今なお頭から離れません。
そして次は、比企の陰謀による阿野全成の死でしょうね。
御家人同士の融和を志していた義時が、力の論理を使わなけば陰謀が跋扈することに気付き、鎌倉の闇を断ち切るために、自らが鎌倉を率いる覚悟を固める描写は胸が熱くなりました。
私は、本作には3つの神が居ると思っているのですが(詳しくは後述)、義時はここで権力の神に選ばれた、もしくは自ら身を投じたとも思います。
史実でも、この事件が頼家・比企と北条との仲を決定的に悪化させたように思うので、この展開はその意味でも良かったと思います。
そして、次が決定打。
畠山重忠の死と、父である時政の追放です。
長年の友である重忠の理不尽な死、そしてそれを招いたのは父の時政。
父の命乞いをしたいのに、決して自分からは言い出さない描写(畠山の死や他の御家人への公平性から)、そしてその後の、顔の半分が闇に覆われたように、悲しみの慟哭をたたえた父との会話シーンは、義時がここで覚悟を決めると同時に、捨てることになるものへの悲しみが表現されていて圧巻のシーンでした。
そしてその後の回の「穏やかな一日」というタイトルで、権力の司祭足る覚悟を決め、傲慢さを自らに飾り立てた義時と、周りの関係を描き(表面上は穏やかでも、火種は燻っているのを淡々と見せた凄いい回でした)、そしてその後は、衝撃的なラストへとひた走っていく・・・・・
大河において、ここまで一人の人生を劇的に描き切ったことは、今まで無かったのではと思う位、本作は、本作における北条義時という人を描き切ったと思います。
そして権力の司祭としての義時と、タイトルの「鎌倉殿の13人」との関係性、そしてメインビジュアルの、13色の着物の帯の中で義時が両手を上げて立っている姿についての考察は後の項目で詳しく書きます。
慈愛としての政子と、その成長の変遷
実は私は本作には主人公が二人いると思っており、それが政子です。
本作の政子は、自分の子供たちのほとんどが不幸な運命により命を落としながらも、常に慈愛の精神を忘れないキャラクターとして描かれました。
義時が頼朝の死後、「慈愛」から「権力」の方へ軸足を移していったのとは対照的です。
言うなれば義時が「権力の神の司祭」とするなら、政子は「慈愛の神の伴走者」でした。
そして本作は政子が色んな人々との出会いによって慈愛精神を高めていく軌跡の物語でもありました。
亀の前事件では、頼朝の不倫相手に憤るだけでなく、亀の前からのアドバイスを素直に受け取り(これが出来るところに政子の資質がある)
また、りくは陰謀家ではありましたが、その希望を失わない精神は、一途に思いを走らせがちな政子の心を逃がし楽にする手法を教えてくれました。
また政子の精神の根本になったのが、頼朝には言えない、御家人の不平やたわいもない話を真摯に聞いたことです。
自分の思いに寄り添い聞いてくれるからこそ、八田知家のように必ずしも北条与党でない御家人も、政子に「北条が本当はどう思われているか」という耳の痛い話題を素直に喋ってくれたのです。
そして人の話を聞くことは、聞いてくれた人の心を健やかにするだけでなく、聞いている政子も成長させます、このように政子は精神の円熟度を高めていったのです。
実の妹の実衣に関して言えば、実衣は人並みの野望を持ち、そして死への恐怖を持つ、いわゆる聖俗併せ持つ普通の人として描かれました。
お互い不用意な発言で傷つけあうこともありましたが、政子は常に妹を守るスタンスを貫き、そして最後には実衣は尼副将軍として政子を支え、お互いに自分の思いを言い合い笑い話が出来るまでになりました。
これは常に手を差し出し続けた政子に対し、実衣が手を差し出し返したということです。
その意味でいえば、トウについても同じことが言えます。
トウは暗殺者でありながら、政子の自殺を止めました。(これもまた感慨深いシーン)
そして政子は、そんなトウを身寄りの無い子供たちに武芸を教える役割を任じることにより報います。
これもトウが差し伸べた手を、政子が差し伸べ返した事例と言えると思います。
トウについて言えば、本当の狙いは善児に対する復讐だったとはいえ、暗殺者として手が汚れていることも事実で、そして何より頼家を殺した張本人でもあります。
しかし政子の手は、一度罪に手を染めたものにも、差し出し許す恩寵の手であったのだと思います。
そして政子の慈愛は、その上にいる運命を司る何かをも掴み、その政子の手が義時を修羅から解放したわけです。
まさに本作は、義時と政子という運命に選ばれた姉弟の物語だと言えると思います。
血と政治の都市・鎌倉
前項で本作は主人公が二人いたと言いましたが、実はもう一つ主人公格と言えるものがあります。
それは「鎌倉」です。
本作では鎌倉を舞台に、数々の人々が陰謀に身を投じ、粛清により命を絶たれていくわけですが、その血や思いが重なる後半になればなるほどこの「鎌倉」という場が浮かび上がってきます。
物語が進めば進むほど、人々の思いが重なれば重なるほど、この「鎌倉」という概念や場が視聴者の頭の中に出来上がっていくわけです。
これと対称となるのが「京都」です。
京都に関して言えば、見れば見るほど「腐敗・堕落・陰険」という場として浮かび上がってきます。
鎌倉は確かに凄絶なほど血が流れていますが、そこにはまだ政治のダイナミズムがあります。
いわば新しい産声を上げ暴れまわるひな鳥の精神です。
しかし京都はとうに政治を放棄し、堕落と私欲と前例踏襲しか能が無い、もはや終わった地であったわけです。
本作の最終話が承久の乱を淡々と描いたのも、もはや京都は特筆して書くことはなく、それよりも新時代へのリレーとしての義時と政子に重点を当てるべきという判断だと思います。
鎌倉と京都では死に方に際しても、梶原・畠山・和田が凄惨ながらもしっかり見せ場を残して散るのに対し、平賀朝雅も源仲章もまあひどい醜態をさらして死んでいくので差別化がしっかり図られてると思います。
本作の見どころとして、鎌倉の中での陰謀や思惑を巡るハードな政治ドラマとしての側面があります。
公暁を刺し殺し、首を差し出す三浦と、それを認める義時と広元により、実朝暗殺後早々に坂東新体制が宣言される当たりは本当に最高でした。
とはいえ、鎌倉の血の政治が決して全肯定出来るものではありません。
武田信義が息子を殺された際に「お前らは狂っている」といいますが、これは本質を突いてると思います。
鎌倉は特に、荒れくれものの坂東武者たちの政権でしたから、その傾向が極端に出ていましたが、政治や権力には人を狂わす何かが宿っています。
人類の政治史なんてどのページを開いても、狂ったエピソードのオンパレードです。
民主主義により選挙が戦に変わったので、人が死ぬことはなくなりましたが、それでも近現代や現代の政治史には狂ってる人が沢山います←具体的には名前は上げません笑
しかし、それでも人間が生きていく以上「政治」や「権力」からは逃げられません。
本作は、そんな「政治」や「権力」に向き合い、試行錯誤していく人々を通して鎌倉時代という日本史史上の転換点を描いた作品なわけです。
そして陰謀の最中でも理想を失わないことで、一時的ではあるにせよ泰時による穏やかな治世が訪れるわけです。
その意味で本作は人間を描くことで、鎌倉という時代精神を描いた作品なのだと思います。
本作における頼朝の役割と大江広元
私は頼朝を尊敬しているゆえに、本作の頼朝の描写に対しては疑義を投げかけていました。(大泉洋さんは大好きです)
しかし物語が終わって振り返った時に、本作の頼朝はこれで良かったのだなあ、と思い直しました。
私は史実の頼朝は偉大なカリスマ将軍だと思っていますが、本作における鎌倉時代というのは、その都度の事件において、それを直面した人々のもがきや思い、苦しみによって作り上げられてきたものという描写がなされているからです。
もし前半の源平合戦を重厚で怜悧な頼朝の描写で描いていたら、後半もさらに物語が残虐で重々しくなるため、かなりハードさが飛び抜けた作品になってしまったと思います。
それはそれで個人的には好きですが、色んな人が楽しめる為にも息抜き要因としての茶目っ気キャラは必要だったでしょう。
そして今回、実は頼朝より比重が実は大きいと思うのが、大江広元です。
本作における彼の存在感は、正に「鎌倉政治の設計者」のそれでした。
史実で頼朝を礼賛する人の中にも、頼朝の知恵とカリスマがすごかった派と、広元の言った事をそのままやっただけなのでは派がいます。
政治家としては、良い人材の判断を尊重出来るのもまた能力だと思うので、後者の場合でも頼朝の価値は揺るがないと思いますが、本作は後者の描き方に近かったですね。
通常の政務や、広常の暗殺など、あらゆることを広元と相談し導かれるように決めていったように本作の頼朝は見えました。
私は史実でも大江広元はとても偉大な人物だと思っていましたが、本作でも果たした役割はとても大きいです。
広元が居なければ、荒れくれ者たちに政治の作法が浸透することは無かった気がしますし、さらなる混乱と無意味な血が流れていたように思います。
しかしそんな広元ですが、彼はそれでも設計者に過ぎません、それを実行し遂行するのは、実質的な武力を背景とする御家人たちです。
現代でいうと政治家と官僚の関係でしょうね、政治家は大きな力を持ち方針を決めますが、派閥やら何やらの権力闘争や選挙で負ければ、その座を追われます。
しかし官僚はあくまで政治家の方針の実行者なので、基本的に失脚はしません。
広元はその能力ゆえ、頼朝から時政、義時・政子というトップたちに常に重宝されました。
もちろん彼らが広元の知恵を利用したかったからというのもありますが、広元の方も彼らを上手く自分の方向性へと誘導していった側面もあるでしょう。
本作の広元は、前半は頼朝、後半は義時のパートナーとして、政治都市・鎌倉を作り上げました。
広常暗殺や義盛追討に関して彼が非常に積極的だったのは、広元の鎌倉の中に旧態依然とした豪放磊落で、政治の作法が分からないものは必要がなかったからでしょう。
この手法は残酷に見えますが、その後、泰時の治世の時に文治の世が来ることからも、間違いと切り捨てることは難しいのが分かります。
その意味で広元は頭の中に、鎌倉政治の理想図を常に持っていたと思います。
そして本作の政治家たる、頼朝や義時が非常に神の存在を意識していたのに対し、広元はおそらく自分の理性を最も信奉していたと思います。
その意味で運命に翻弄される人々を描いた本作において、運命の風下に立たなかった広元はもっとも成功したとすら言えるかも知れません。(ゆえに最も悪い人にも見え、それもまた魅力)
そんなわけで、鎌倉時代の精神は、人々がもがきあがいた産物として描かれ、政治作法は広元が常にいるため、頼朝は本作においてこれくらいの描き方でちょうどいいのだと思います。
義時が神の加護を意に介さずに地獄に落ちてでも鎌倉の礎を築こうとしたのに比べて、頼朝は自分が神の加護を失うのを恐れて最後は錯乱していました。
そこに政治家としての義時と頼朝の覚悟の差も伺えます。
そして本作は、まさに北条義時が主役なわけでそれでよいのです。
頼家と実朝
頼朝死後の鎌倉殿の、頼家と実朝。
彼らは権力の神に選ばれなかった者たちです。
頼家は、政治のバランス感覚の欠如ゆえですが、実朝は複雑でした。
和田合戦の前段階では、将軍として義時と義盛の争いを調停しており、非常にバランスの取れた鎌倉殿になったかもしれません。
しかし和田合戦が決定的に彼の運命を変えてしまいました。
ここにおいて実朝は、「鎌倉に信用できるものはいないから京都を頼る」という時計の針を逆戻りさせる方針を採択することになります。
鎌倉殿としては完全に失格ですが、こうなってしまった要因は義時にあります。
自分が目の前で広常を殺されたのと同じことを実朝にしたからです。
実朝に力の論理を教えようとした意図があったのかもしませんが、繊細で優しい実朝には逆効果でした。
そもそも今の義時は力の論理を受け入れていますが、広常の死の時はとても心を痛めていたはずです。
なのに想像力を働かせず、合理的に乱を処理した結果が、実朝を一見優しく雅にみえる京都の方へ軸足を移させてしまいました。
北条は和田合戦以降、義時が政所だけでなく侍所も掌握するので、実質ここにおいて最高権力者の地位を固めるわけですが、本作ではこれ以降、義時は京都に苦しめられ続けます。
これは慈愛の神への思いを失い、他者への想像力が欠如しつつある義時に対する報いでしょう。
そもそも実朝は北条にとって大事な玉であり、とてもバランス感覚のある鎌倉殿でした。
それを失う結果を招いたことが義時自身の悲劇にも繋がっていきます。
ここで頼家の話に戻りますが個人的に私は、本作の頼家の最後がとても好きでした。
座して死を待つのではなく、戦って散る。
あまりいいイメージがなかった頼家の印象を本作は大きく向上させてくれました。
そしてその息子の公暁もまた、実朝暗殺の経緯は浅はかだと思うものの、父の檄なる血を引いている気性がとても素敵に映りました。
のえと三浦義村を巡る因果
終盤に権力の神の司祭たる義時を追い詰める、神への反逆者ともいえる二人。
双方ともに、ろくでもない人たちではありましたが、こういう行動を取らせてしまった要因は義時にもあります。
そもそものえは「妻」であり、義村は「友」であったはずです。
のえの目的は最初から堕したものでしたが、しっかり愛を込めて接していたらここまでのことにはならなかった気もしますし、前の妻と比べるという絶対してはいけない発言を義時はしています。
そして義村に対しても、守護の任期制を告げる時のやりとりはプライドをへし折るものでした。
ここにも権力への神へ近づきすぎたゆえの傲慢さが、義時の足を引っ張っています。
そしてもしこれが慈愛たる政子であったならば、こうはならなかったとも思うのです。
実衣やトウ、そしてりく、亀の前、藤原兼子など、それぞれ思惑を抱えたものたちを政子は、話を聞くことや心を開くことで関係性を築いていきました。
ここに義時と政子の差があります。
本作における三体の神々
本作品は非常に神や仏に対する言及が多い作品でした。
梶原景時は、非常に信心深い人物として描かれ、頼朝を助けたのもそこに神の何かを見たからでした。
そしてその頼朝も、神仏の加護をとても頼りにしていました。
その意味で本作はとても神的な作品です。
そして私は本作に息吹く三体の神を、作品の深淵から見出しました。
まず人に属する神として「権力の神」
そしてこちらも人に属する神で「慈愛の神」
これらは人の思いや感情に呼応する、人とリンクした神だと思います。
そしてもう一つは、運命を司る絶対者としての神です。
ここでいったん私の「神」に対する価値観を書いておきます。
私は子供の頃は
「世の中は科学で説明出来ることが絶対で、神なんていないやい」←ちょっと可愛い
と思っていました。
しかし欧米の文学や哲学、宇宙の本を読むにしたがって徐々に
「あれ、神っていないとは言い切れないかもな・・・」
と思い始め、そして今に至っては
「ていうか神は間違いなく在る(ある)」
そう思うようになりました。
そもそも科学による宇宙の始まりの説明が
「無」から「有」が生まれた
という矛盾を内包しており、「無」を「有」にした存在がいると考えた方がすっきり説明がつきます。
そう思って以来、私は暇さえあれば世界が本当はどうなっているかと考えるようになりました。
そもそも私は「無限」ということを考えることが出来ますが、それは「無限」という概念を想像出来ているわけで、その概念をどこかで植え付けた人がいるかもしれません。
それかもしかしたらこの世界は、誰かがコンピューターで作った世界かも知れません。そうなるとそれを作った人こそ我々にとって神になる・・・・・
とまあこんなことを考えてたら一日が終わります笑
欧米の文学や日本の近代文学では、日常における表情や、光の反射に神を見るという描写も多く、その意味で私が本を読んだり作品をみたりするのは、聖なる瞬間や普遍的な何か、つまり神的な何かを得るためとも言えます。
その意味で、どんな形でもいいから神の事を考えるのは楽しいわけです。
話が本作からかなり逸れましたが、これが私の神に対する考え方の一端です。
それでは以下では、そんな私があまりよくない頭の中で本作から見出した神の姿を書いていきます。
二体の神々の相克とそれを見守る絶対者
前項で述べた「権力の神」と「慈愛の神」。
これは人間の感情や思いの延長線上に宿る存在です。
そして「権力の神」は頼朝、時政など変遷はありましたが、物語冒頭からその資格を持っていた義時を最終的な司祭に選びます。
「慈愛の神」は、人々の思いを聞き、集めた政子を伴走者として選びました。
まだ義時が司祭たる立ち位置を確立していない前半は別として、後半は義時と政子は鎌倉政治の方針を巡り対立していきました。
これは「権力」と「慈愛」の代理戦争でもありました。
人間が集団社会を営む上で避けては通れない政治。
そしてそこには矛盾した二つの調和が求められます。
人々の平和を「慈愛」により求め、それを実現するには「権力」が必要になる。
人類の歴史はどのページをめくっても戦争の歴史ですが、その目的に自国民への愛が純粋ではない場合がほとんどとはいえ、全く入っていないことはありません。
つまりこの二つの神たる「慈愛」と「権力」は、人間が持つ二つの顔でもあるのだと思います。
誰かの事を愛おしいと思う心もあれば、力で支配したいという願望もある。
人間とはそういう矛盾した生き物なのです。
だからこそ鎌倉では政治のダイナミズムが脈動すると同時に大勢の血が流されます。
その意味で本作は、義時と政子という姉弟の物語であり、「権力」と「慈愛」の融和や戦いといった紆余曲折の物語でもあるわけです。
ただし本作の義時は「権力の神の司祭」でありましたが、司祭としての方向性は「私」の利益ではなく、基本的には「公」に向いていました。
義時の目的は、理想の鎌倉政治の体現、そしてそれを実現する泰時へリレーを繋ぐことであり、そのために権力の修羅へと自らを変身させたのです。
もちろん北条家の繁栄という要素もありますが、荒くれものの坂東武者の中での集団指導体制は、義時が挫折したように、かなり無理があるのも事実です。
後の世の最も安定した武家政治と言われた徳川政権も、根底には圧倒的な徳川一強がありました。
その意味で義時の方向性が、やり方がどうかは別として間違っているとも言えません。
その意味で義時が言った「鎌倉は誰にも渡さん」と言ったセリフは、歪んでいるにしろ、そうではないにしろ鎌倉政治の牽引者の地位は私こそがふさわしいと言う、公に基づいた自負なのだと思います。
さてここで運命を司る絶対者としての神について触れておきます。
私は、この存在は世界を作ったモノであり、そしてそれは空気や大地、川や海など至るところ、というか全ての場所に在るモノだと捉えています。
そしてこの神は運命を司っていながら、主体的に行動することはなく、基本的に人々や世界の流れに任せ干渉しない存在だとも思います。
しかしその存在が、何かの局面において気まぐれなのか、深い思慮なのか、人の思いに呼応してなのかは分かりませんが、世界に影響を及ぼすことがある。
それが本作のラストシーンだと思います。
義時は実朝が暗殺されるのを黙認することで修羅になる覚悟を決め、運慶に自分の姿と神仏とが一体となった像をオーダーしました。
これは、神の加護により自己の幸せを願っていた頼朝を超え、神の加護など恐れずにその高みへ登り、より盤石な政権を泰時に渡そうとする目的でしたが、これはやはり超えてはならない一線でした。
絶対者は傲慢になった権力の神とその司祭を許しませんでした。
運慶が見るに堪えない恐ろしい像を義時にもたらしたのは、運慶の芸術家としての矜持もありますが、この絶対者の意志も働いていると思います。
この像は義時の精神の驕りを現わしていて、そしてこの像が出来た時点でもう義時は手遅れでした。
泰時の治世のために、先帝を殺そうとする義時は、殺すという選択肢の他にいくらでも取る道があるのに、それをすることにより自分から地獄へ落ちようという感すら漂っていました。
ことここに至り自らの理性を基に「権力の神の司祭」をしていた義時は、権力の神に完全に取り込まれてしまいました。
そして絶対者は、「政子と慈愛の神」へと呼応することにより義時を権力の神の虜ではなく、一人の人間として死なせようとしたのだと思います。
「鎌倉殿の13人」の意味とは何なのか
本作のラストシーンにおける頼朝の死後、死んでいった御家人たちの総数が13人であることを義時が述懐するシーンは最初見た時は
「ラストシーンは最高だったけど、タイトルの回収は無理があったなあ」
と思いました。
しかしその後、本考察を含め色んなことを考えているうちに、その考えはかなり変化しました。
ここからは個人的意見ですが(今までだって充分個人的意見である笑)
タイトルの「鎌倉殿の13人」の「鎌倉殿」は、頼朝や実朝などの征夷大将軍を指すのではないと思うのです。
それでは何かというと、それは「理想の鎌倉政治」という「観念」です。
本作の義時は、頼朝存命時は自らの理想を、そして死後は頼朝が作った鎌倉政治を自らが解釈した理想を抱えていました。
そして義時だけではなく、政子には政子の理想が、三浦義村や和田義盛にもそれぞれの思いがあり、その流血を含めた試行錯誤により「鎌倉政治」は整えられていきました。
史実では鎌倉殿は、摂関家から親王へと受け継がれていきますが、実質の権力は北条氏が握っており、その意味で鎌倉殿は形式的な権力としての存在になっていきます。
本作でも、義時が死去する時には、鎌倉殿は摂関家の幼い三寅(藤原頼経)になっており、その後見的な存在として北条という御家人筆頭が、御家人たちと相談し政治を主導する体制が固まっていました。
その意味で、本作のタイトルの意味は、「鎌倉政治」を固める為に、犠牲の人柱となった13人という意味だと思います。
そして義時がこの13人に入らないのは、義時がこの「鎌倉政治」を固めるための「権力の司祭」だからです。
事実、頼朝が死んで以降は、頼家や時政など政治のトップは変わりましたが、広元と共に権力の中枢に居て、鎌倉全体の視野を持っていたのは義時だけでした。
全ての犠牲者が、義時の手によるものではないですが義時は常に権力の身近にいました。
そしてメインビジュアルの、13色の着物の帯の中で義時が両手を上げて立っている姿は、権力の司祭として13人の人柱たちの象徴である帯の上に立っている図を現わしているのだと思います。
その意味でこのメインビジュアルはとても禍々しい儀式の画としても見れるわけです。
そして本作は義時が権力の司祭へと選ばれ、その生涯を全うする物語であるゆえに、この権力の神こそまた義時と同じく主役中の主役でありました。
13人の犠牲者は、権力の神の祭壇に捧げられたわけで、ここに政治というものが持つ権力の神の禍々しさが表現されています。
その意味で、義時の運命を決定付けることになった運慶の仏像は、義時の心だけを表現したものではないと思います。
あの仏像は、権力の神に祭壇に捧げられた人、そこに血や肉を捧げた人、すなわち鎌倉政治に関わる全ての人の禍々しい権力欲を現わしたもの、すなわち権力の神そのものの姿だと思います。
そして本作のラストは、義時が絶対者と呼応している政子の手により、権力の神から解放されて終わるわけで、その意味で本作は徹底的に義時という権力と共に生きた人生と向き合ったと思います。
それは絶対者による救済の物語
本作のラストシーンは現代のドラマ作品では、ほとんど見ることは叶わない聖なる瞬間でした。
政子は、薬を床に流す前に頼家の死の真相について知るわけですが、これに対し様々な感情があったとはいえ、「素直に話してくれてありがとう」と言っています。
「許すこと」が幸せになるために必要である・・・
宗教や哲学書が言う言葉ですが、これは分かっていても容易ではありません。
しかし、政子はこのシーンで「許す」ことを実践しています。
複雑な感情がありつつも、ありがとうと言える。
政子は、そういう慈愛の境地に達しました。
しかし義時は義時で、自分の幸せや、神の加護を放り出し、地獄の修羅となり権力の神と共に「鎌倉」の為に身を焼こうとしています。
こちらもある意味では完成と言えます。
権力の神と同化することは、自らを焼き尽くすことと同義なのかもしれません。
そして政子は、義時を権力の神から解放するために薬を流すわけです。
「慈愛」や「許し」に達した政子に、おそらく迷いは無かったと思います。
そしてそんな政子に絶対者も呼応しました。
このラストシーンは政子と絶対者が一体となり義時を救いに導くシーンでした。
一般に「高貴」という言葉は、清浄や美への執着から、自分の手を汚さなかったり、現実を見なかったりというイメージもあります。
しかし、このシーンの政子は、薬を流すことが自らの手を汚し、心を傷つけることを知ったうえで、それでも義時の救済へ手を差し出しているわけです。
これこそ本当の意味での「高貴な手」ではなく「聖なる手」です。
本作は、長い「慈愛」と「権力」の戦いの果てに、「絶対者」と「慈愛」が「権力」の神を殺す話でもあり、それは聖なる手が義時を一人の人間に戻す物語と同義です。
そして義時が泰時に渡してくれと言っていた、小さな観音像。
あれは義時が、修羅に落ちようとも、どこか心のほんの隅にでもいた「慈愛」の精神の象徴です。
色んな人々の「慈愛」が込められ、義時の側にいた「慈愛の結晶」。
これは色んな人の話を聞き精神を高め、義時と二人三脚で歩いてきた政子とも重なります。
最後、政子は絶対者と一体となり義時を救いますが、この観音像もまた、人々の慈愛の思いにより絶対者の恩恵が宿っています。
その意味で政子と観音像は、その性質や意義・象徴において同義だと思います。
義時の精神と運慶の仏像がリンクしてるのを思うと、「運慶の仏像」と「小さな観音像」により、聖と邪の差異を視覚化している点も、本当にすごいと思います。
そんなわけで本作のラストシーンは、絶対者による救いのシーンでした。
そしてこのシーンが個人の救いだけでなく、鎌倉の、真の救いであるためには未来への希望が必要となります。
それが泰時です。
泰時は、昔の義時のように「慈愛」を失わないようにしながらも、義時が「権力」に取り組み試行錯誤するのを側で見続けてきました。
私は二体の神の相克の項目で
人々の平和を「慈愛」により求め、それを実現するには「権力」がいる。
という二つの矛盾した要素のバランスの取れた調和こそが、政治の難しさであり目標と語りましたが泰時はそれの体現者です。
そして泰時をそんなバランス感ある人物にしたのは、前の世代である義時と政子の軌跡、すなわち「権力」と「慈愛」の戦いの軌跡を見たからです。
すなわち本作は、バトンを希望の世代へ繋ぐ、地ならしと繋ぎの世代の物語でもあるわけです。
泰時の治世では、一時ながらも穏やかな治世が実現しました。
それは激動の時代において一時の穏やかさではありますが、それを求めよう、実現しようとする精神こそが現代にもつながる人類の希望や理想への意志であり、最も重要なことだと思うのです。
最後に
本当にすごい作品だった。
私は鎌倉時代が大好きなこともあって、本作が発表されてから2年間ずっと期待して、そわそわしながら放映を待ち望んでいました。
いつもこのサイトでは、本の考察をアップしているのですが、基本的に全て読了済みの作品を書くため、自分の評価は定まっており、そして自分が本当に良いと思った作品を選ぶことが出来ます。
しかし大河ドラマを1年を通して追う場合、そうはいきません。
私はただでさえ感情の乱高下が激しいので、1話ずつ見て雑感を上げるのは本当に大変で、かつその都度、本作へのスタンスが右往左往しました。
そしてまた常に「もし最終回まで見終わってイマイチだったらどうしよう」という不安も抱えていました。
なぜなら私は作品を読んだり見たりするときに、もちろん全体を通して好きか嫌いかを決める側面もありますが、それと同時に最後の一言や1シーンで評価が覆ることが大いにある人だからです。
しかし本作は、そんな私の杞憂を軽々乗り越えて、それどころか私が常に求めて止まない聖なるシーンを与え、とんでもない景色を見せてくれました。
もう感謝しかありませんし、本当に1年間書いてきて良かったと思います。
これからも聖なる瞬間を追い続け、また自分もそんな瞬間を作り出したい。
そんなことを改めて実感出来た本作に改めて感謝を述べて、本考察を終えます。