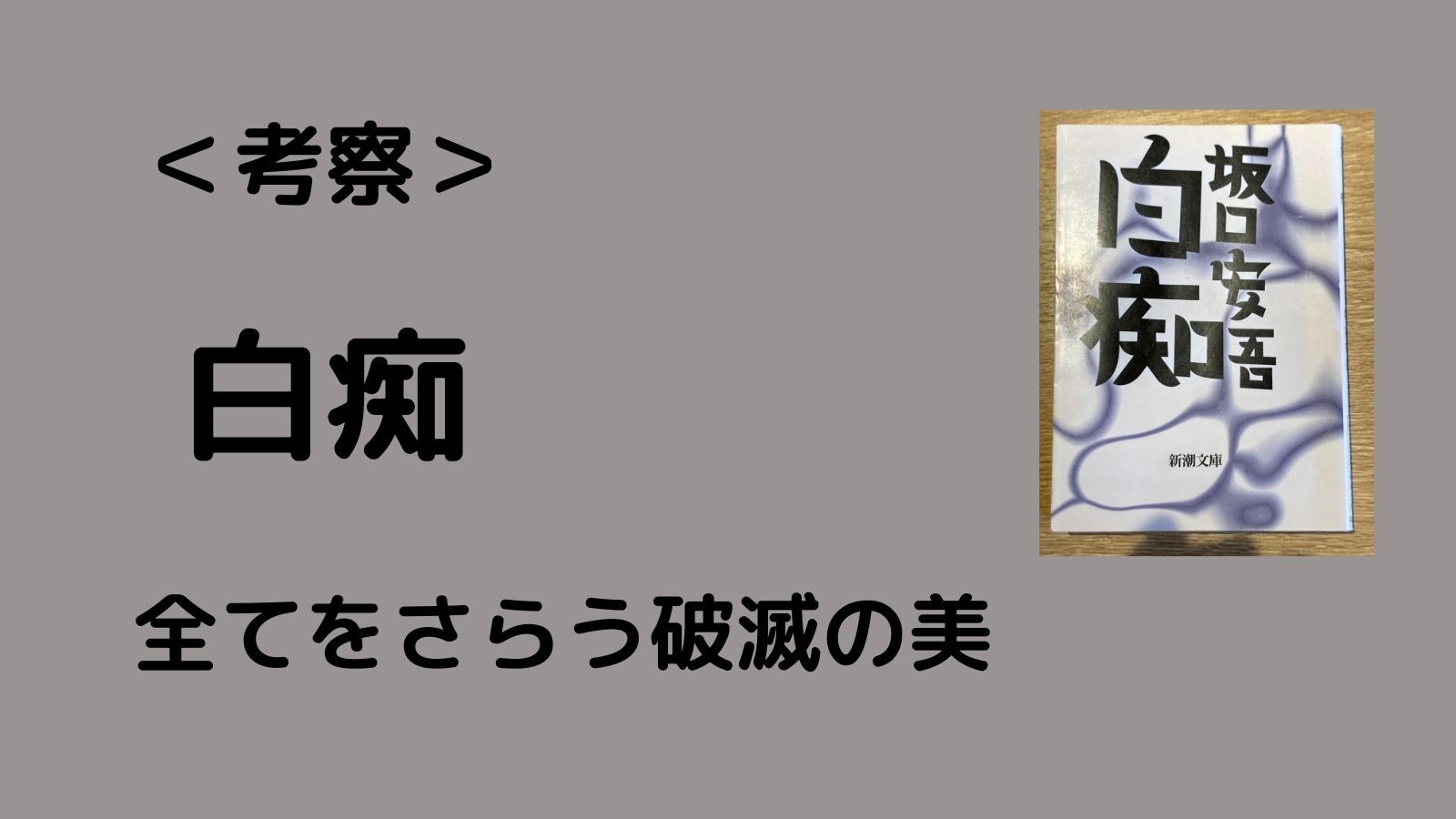「白痴」は坂口安吾さんの短編小説です。
坂口さんは、戦前から戦後にかけて活躍した日本文学を代表する小説家の一人で、純文学だけではなく歴史や推理小説など数多くの作品を残しています。
坂口さんの作品では、今回考察する「白痴」と「堕落論」が特に有名で、この2作により時代の寵児になりました。
精神の様々な側面と、退廃の美を描いた本作を自分なりに考察します。
ネタバレが嫌な人はここでストップしてね。
ざっくりストーリー
(現在において差別的であったり適さない言葉が多々ありますが、時代背景などの観点から、作品内の言葉をそのまま使っています。)
時代は第二次大戦の敗戦間近。
文化映画の見習い演出家である伊沢は、場末の工場や商店街、安アパートが林立する地域で、小屋の一室を借りて住んでいます。
これらの安アパートの何分の一かは妾や淫売が住んでいたりと、地域の人々の生活は乱脈ですさんでいます。
そんな時、ひょんなことから路地のどん底に建っている家に住む、気違いの男の、白痴の女房を自宅に囲うことになる伊沢。
そして日常生活で白痴の女と交流することになるのですが、あるとき伊沢の住んでいる地域に空襲が訪れます。
空襲の炎の中を白痴の女を抱いて出ていく伊沢。
果たして伊沢は何を思い考え、そしてその精神は何を抱えているのでしょうか?
躁鬱的な描写
この話は基本的に全て、伊沢の視点で進んでいきます。
伊沢は芸術や創作に対し熱い思いを持っているものの、あまりに俗物で流行りを追うことしか考えてない映画界や、それぞれを慰め、なれ合いの相互互助会みたいになっている演出家たちを軽蔑しています。
そんな中でふと出会った白痴の女に、慎み深さや無垢さを見出すわけですが、この気持ちが二転三転します。
あるときは常人よりも思索的だと感じたかと思えば、女が爆撃の恐怖にとらわれる顔を見た時は
「白痴ゆえに理知もなく、純粋にあさましい死の苦悶の表情に、これほど醜悪きわまるものはない」
とかなり強い嫌悪の思いを抱いたりします。
自身の心情の動きをそのまま描き、虚飾を排除しているところに、この物語の醍醐味や特色があります。
そして、この入れ替わる感情の奥には、もっと根源的な願望が隠されています。(後述)
無垢なものVS人間の生活
「無垢で純粋なもの」として伊沢が捉えている白痴の女。
それと対立しているのが、伊沢が思う映画界や、安アパートにいる妾や淫売、そしていわゆる普通に暮らす人々であり、「俗世界である人間の生活」と言い換えてもいいかもしれません。
普通の小説なら、伊沢は白痴の女の側に気持ちの重心を移して、その観点から進行しそうなものですが、この小説はそんな単純な描き方はしません。
白痴の女を肉欲の発露でしかないと考えたり、世間の生活者の目や、掟にこそ何かがあるんじゃないかと怯えたり、無垢な物の方の長短も、人間の生活のほうの長短にも敏感に神経を張り巡らせています。
私は、快楽や芸術に対して敏感な人は、あらゆることに敏感なので臆病だと個人的に思っていますが、伊沢はある種、常に何かに怯えており、非常に臆病で繊細です。
しかし、だからこそ感情が行ったり来たりして、物事を多面的にバラバラに無秩序に考えざるを得ないわけで、こういう複雑怪奇で繊細な思考回路を持つ脳の中にこそ、本当の芸術に連なる、まだ見ぬ何かが眠っているのではないか、そんなことを思います。
象徴
ストーリーをそのまま追うだけでも十分にすごい本作ですが、私はこの小説は非常に象徴的な側面があり、人物や物事が何かを象徴していると考えています。
まず白痴の女ですが、これは無垢なもの、すなわち芸術性の象徴だと考えます。
林立された安アパートや給料が表すのは、雑多な生活の象徴でしょう。
白痴の女を肉欲の発露であったり、泥人形のようにしか捉えられないようになる時の描写も、自身の芸術に対する懐疑を表してるように思います。
美の表現は、しょせん性欲に繋がるものに過ぎないんじゃないか。
自分の作品は価値のない泥人形に過ぎないんじゃないか。
物を作る人間なら誰しも一度は考えるのではないでしょうか?
そして劇中で、空襲に襲われた時に選ぶ二つの道も、芸術の道と生活の道の分かれ道だと個人的に感じました。
空襲から逃げる多くの人々が目指す道は、火の手から遠いけど、その先に空地も畑もなく、焼夷弾に道をふさがれたら死の運命が待つのみの道。
そしてもう片方は、既に両側の家が燃えているが、抜ければ、小川があり麦畑へ出られる道。
女を抱き「俺たち二人の一生の道はいつもこの道だ!」と言いながら、後者の道を行く伊沢は、芸術へ突き進む精神の体現的存在に感じました。
しかし、ここで終わらないのがこの物語のすごいところです。
滅びという昇華への憧れ
無事に炎を超えて生き延びた伊沢ですが、危機が去り日常が顔を出すと、途端に白痴の女に嫌気がさします。
その時の伊沢の、逃げている自分と女を俯瞰して見たイメージの表現は辛辣です。
「男が女と肉体の行為に耽りながら、女の尻の肉をむしりとって食べており、食べ続けた結果、女の尻の肉はだんだん少なくなるが、女は肉欲のことを考えているだけ・・・」
なんというグロテスクで、心の奥底に刻みつられるような表現でしょうか。
さらに女を捨てようとも思ったものの。
「紙屑を捨てるにも、捨てるだけの張り合いと潔癖ぐらいはあるが、この女を捨てる張り合いも潔癖も失われている。」
そんなことも言っています。
このショッキングな表現を前項で書いた文脈で変換すると、ここにきて、自分の中の芸術のあさましさや、無価値さがまた顔を出してしまったということになります。
伊沢はそこに死や危機が迫る時、言うなれば非日常にいる時には、芸術の感情が研ぎ澄まされます。
しかし日常になると、途端に退廃のぬかるみの中に沈み込んでしまうのです。(途端に自分のもつ芸術の感情がグロデスクで意味のないものに思えてくる。)
伊沢は、物質的で生活的なことがそもそも向いていなくて、本質的に空想や美、精神といったものの方に心が向いています。
そしてそんな、彼が心の奥底で求めているのが、生活や精神等で揺れ動く矮小な自分、そして自分を取り巻く世界全てを、圧倒的なスケールで破壊してくれる破滅なのです。
戦争で体験した過酷な経験や、空襲という何もかもを焼き払う光景を繊細な精神が感受したことで、破滅への陶酔的な願望が生まれたのではないか、個人的にそんな風に思いました。
この小説で坂口さんが表現したことは、道徳的な良し悪しなどではなく、作者である坂口さん自身の、虚飾を排除した精神の動きと本質だと考えています。
人間というのは自分でも分からなくても、心のどこかに破滅への願望を抱えており、それと上手くバランスを取って生きています。(少なくとも私はそう)
この作品は上辺だけの道徳や偽りを排し、純粋な願望や精神を描いたからこそ、重く深く心に刻まれるのだと思います。
自分の心をこんなにも揺さぶってくれる小説に出会えたことに感謝して、考察を終えたいと思います。