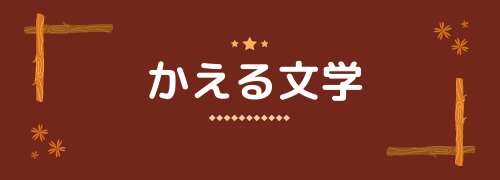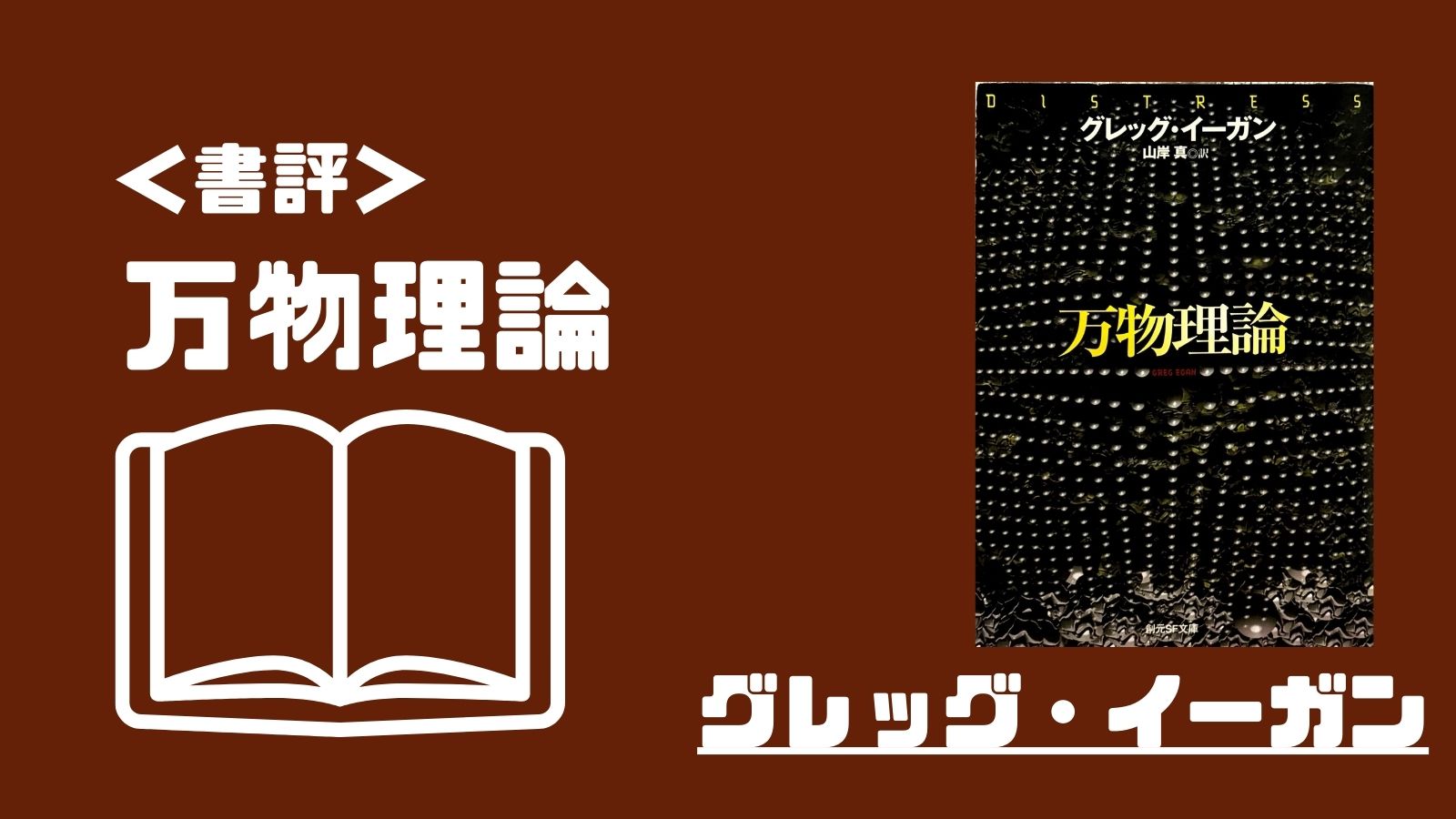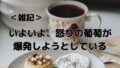「万物理論」はオーストラリアのSF作家、グレッグ・イーガンさんの長編小説です。
本書を手に取ったきっかけは、Youtubeでの東浩紀さんの雑談配信にて(今、日本で一番雑談が面白い人はマジで東さんだと思う)、おすすめのSF作家としてグレッグ・イーガンさんを上げていたのが理由です。
とりあえずグレッグ・イーガンの何かしらの長編を読みたいと思い、上下巻に分かれているのでなく、タイトルに惹かれた本作を購入。先日に読了しました。
本作のあらすじとしては
映像ジャーナリストである主人公のアンドルーが、直前に取り組んでいたトンデモ寄りの科学を扱っている番組に嫌気がさし、ステートレスという人工島で行われる、三人の物理学者がそれぞれの「全ての物理法則を包み込む単一の理論」。
すなわち万物理論をそれぞれ発表。そのうちのどれが正しいのかを議論するというイベントに、ヴァイオレット・モサラという三人の中で最も若い20代の女性を中心に取材に挑み始める、という感じでスタートする物語です。
本作は、というよりイーガンさんの作品はハードSFに分類されるものであり、本作も科学用語や専門用語がふんだんに多用されます。
私は元来SFは好きだけど、ハードSFは苦手という、なんちゃってSF勢であり、どちらかというとバリントン・J・ベイリーさんのような、アイデアだけでがんがん突っ走り、話の筋の面白さで魅せていくという作家さんの方が好きだったりします。
しかし本作は、難解な用語が多いながらも、するするとページをめくり、あっという間に読了してしまいました。
その理由は物語のストーリーテリングが面白く、細かい用後や科学・宇宙理論が分かってなくても(間違いなく私は全部は理解出来てません)、物語の重要な展開や本質的な事は、通して読めば、誰でも理解出来るようになっている事だと思います。
またメインの流れ以外のところでも、こちらの好奇心や知識欲をくすぐるような描写や仕掛けがあり、難しいんだけど、自分の脳が少し進化しつつ、かつ楽しい。というような不思議な快感に陥り、それはかなり唯一無二な体験でした。
本作は冒頭からかなりエッジが利いていて、死後復活という、殺人事件で殺された被害者の生命活動を短時間だけ復活させて、犯人の名前を聞き出そうとする、捜査を主人公が現場で取材しているシーンからスタートします。(なかなかのおぞましさ)
その後も万物理論を巡り、カルト集団や様々な思惑、そして世界で広がる謎の症状などなど、色々な謎が、科学的な描写と絡み、読書の好奇心を牽引し物語は進んでいきます。
私が本作を読み終えた時、思ったのは
「ああこれは、地球幼年期の終わり案件だ」
という感想でした。
地球幼年期の終わりは、アーサー・C・クラークさんの長編小説で、非常に思弁的であり、「我々はどこから来てどこへ行くのか」という根源的なテーマを、鮮やかにかつ大胆に描いた唯一無二の傑作SFです。
私は物語終盤まで本作をハードSFだから、かなり現実的で論文的な落としどころになるのではと考えていたのですが、とんでもなかったです。
まさかこんな地平にまで連れていかれるとは・・・
私が上記のような感想を持ったのは、上述の「地球幼年期の終わり」と、最近ではホリー・ジャクソンさんの自由研究には向かないシリーズの三作目、「卒業生には向かない真実」くらいです。←三部作だけど読んで欲しい
本作は、科学知識や好奇心を刺激し、かつ非常にスケールの大きい名作なので、気になったら是非読んで欲しいです。