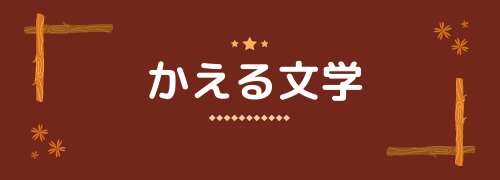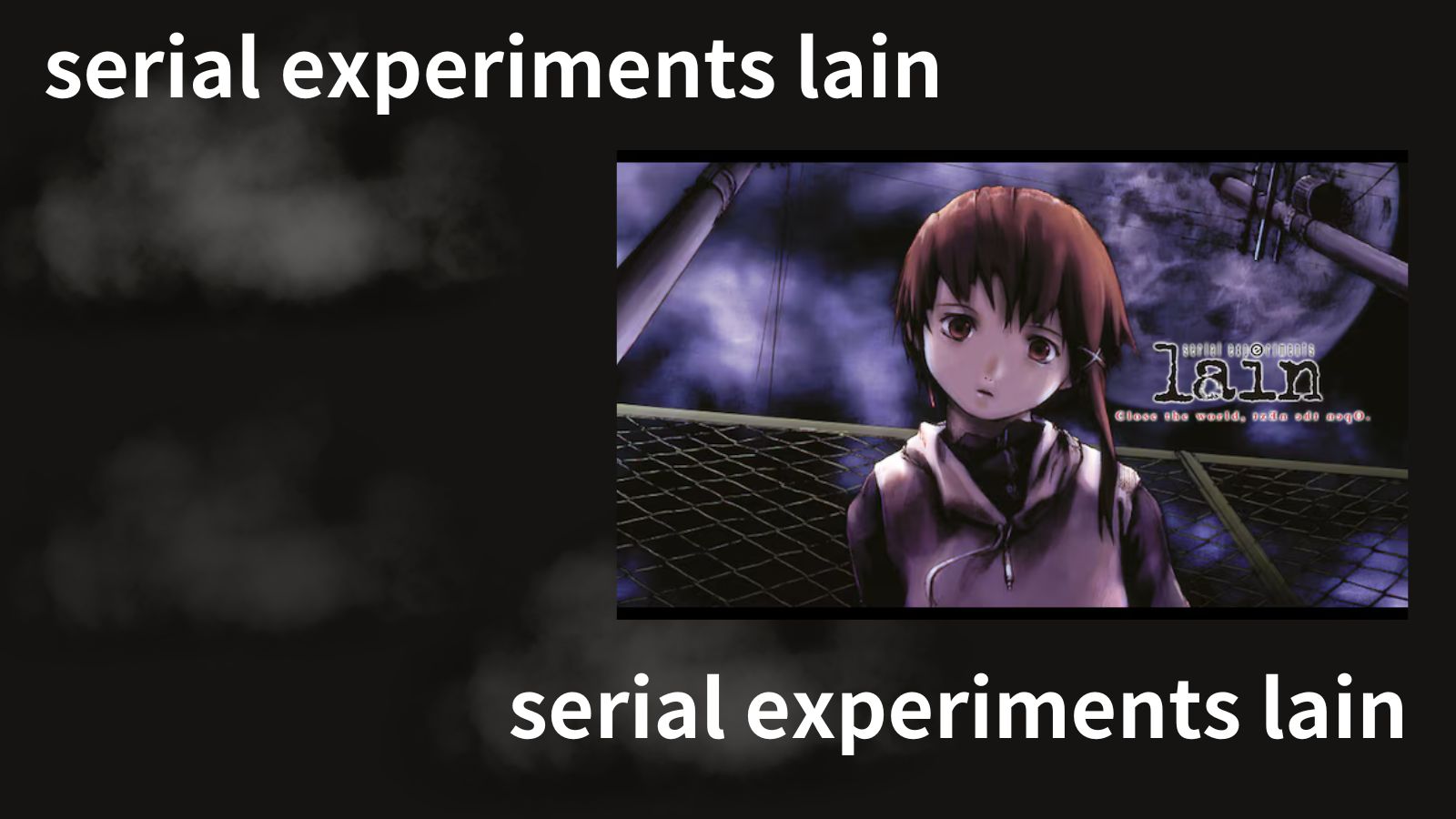「serial experiments lain」は1998年に放映されたアニメ作品であり、ゲームや雑誌の企画が相互関連して展開されたメディアミックス作品です。
90年代に作られた作品でありながら、現代のネットやSNSの問題を予見しているような内容や、不穏な雰囲気やスチームパンク、サイコホラー的な描写が非常に魅力的で、日本だけでなく海外でもカルト的な人気を誇る作品です。
評判は常々聞いていて、いつか見なくてはと考えていたものの、なかなかタイミングが無かったのですが、今年、サブスクにあるのを発見し、二日間かけてじっくりと視聴しました。
そして見終えた時、そのネット社会だけにとどまらない人間存在を問う根源的視点や発想に感動し、何でもっと早く本作を見なかったのかと、自分の怠惰さを呪いました。それ位、圧倒的なパワーを持つとんでもない作品です。
本作は非常に様々な視点や示唆に富み、底が深い作品であり人によって様々な解釈が成り立ちます。
ゆえにここに書いてあるのは、あくまで私はこう考えるという一つの可能性であり、正解だなんて言うつもりはありません。特に物語終盤の解釈は大分、独自的かもしれません。
ゆえに「へえ、こいつはこう思っているんだな」くらいの感じで気楽に読んで欲しいです。
また私は主に、本作の心理的・精神的な面に着目し考察しているので、科学的考察は弱いし、そういう知見は薄いことを最初に記載しておきます。
そして本考察においては基本的にアニメ版のみであり、ゲーム版を私はプレイしていません。(高すぎてプロレタリアートには手が出ないのら)
また本作の主人公である「岩倉玲音」ですが、分裂的存在や象徴性に着目し表現を分けると、なかなかに文章として分かりづらいと判断し、以下からは基本的にカタカナのレインで統一します。
それでは作品の考察に入っていきます!!
例に洩れず、かなりの長文なので、気になる項目だけ見たり、分けて読んだりするのもいいかもしれません。(もちろん全部読んでくれたら嬉しい)
以下、物語のネタバレを含むので、それが嫌な人はここでストップしてね。
物語の流れ
本作は非常に黙示録的な作品です。
その意味で、英利政美が意識をプロトコルに埋め込んだのがいつかという厳密な時系列よりも、アニメ内で起きた物語の順番こそが重要だと考えています。つまり「聖書のように一冊の書物として捉えるべきでは?」ということです。
それを踏まえると本作の始まりは、四方田千砂が自殺した事です。
流れで言うと
① 四方田千砂が自殺し、死んだはずの千砂から玲音がメールを受け取る
② NAVIを通しワイヤードというネットワーク世界にのめり込み、徐々にリアルワールドとワイヤードとの境目が曖昧になっていき、自分の意識と存在について混乱する
③ ありすの助けにより、肉体と心という重要な価値観に気づき、偽神である英利政美を倒す
これが一連の物語の流れになります。
本作は難解で様々な要素を扱うので、複雑に思われがちですが、実は構造的には非常に王道な古典や神話の様な構成なのです。
そしてその物語のスタートが、現実世界では人間と繋がることが出来ないという、孤独による少女の自殺であること。これが非常に重要です。
これは本作のテーマの一つに、現実世界の孤独と分断があるということを現わしているように思います。
本作の主軸。ネットワークと集合的無意識
本作ではネットワークを人間の脳内シナプスの網のように見立てています。
そして地球全てを網上に網羅するネットワークを使う事は、全ての人類がネットワークを通し繋がる事であり、それを突き詰めると人類は集合的無意識的なものと繋がるのではないか、という一つの思想実験を主軸においている作品です。
集合的無意識というのは心理学者のユングが提唱した概念で
「人間の意識の奥には全ての人間が繋がっている無意識の共有空間があるのではないか」
というものであり、これを元に多くの作品が生まれてきました。(村上春樹とかペルソナとか)
本作が画期的なのは、情報ネットワークと集合的無意識との関連性に真剣に取り組んでいることです。
現代において、インターネットやSNSやAIなどについては、概ね技術論や利便性についてだけ述べられており、人間の存在や意識など、心理的・根源的アプローチでネットワークを深く語ったものは、私の知る限り本作くらいな気がします。
ワイヤードとリアルワールド、プロトコル、シューマン共鳴
本作は現実世界のリアルワールドと、現代で言うインターネット上の世界の様な、ワイヤードの二つの世界を軸に展開します。
現実世界であるリアルワールドは90年代の殺伐とした東京をそのまま投影しており、劇中で出てくるクラブのサイベリアなどは、当時の渋谷カルチャーの影響が見受けられます。
一方でワイヤードの方は、モデルはインターネット上の世界ですが、脳内シナプスと情報ネットワークの関係性が強く示唆されていたり、自身の意識がネットワークに入り込んでいるような没入的な表現が多様されたりと、現実世界への影響が非常に強いものとして描かれています。
そもそも本作の物語が徐々にネットワークが現実世界を侵食していく流れなので、そういう表現になるのは当たり前なのですが、そこで特筆すべきなのは、浸食していく過程において科学面よりも、人間の心理面に重きを置いている事だと思います。
本来、プロトコルという用語は、コンピューター同士が通信を行うためのルール的な意味ですが、本作では、よりコンピューター世界を繋ぐ言語性に着目し、ネットワーク全体のコア管理システムのように表現しています。
また本作に出てくる重要な用語にシューマン共鳴という言葉があります。
これは劇中で説明されている通り、地球自らが持つ固有の電磁波のことで、研究によって人間の脳や精神に影響あるのではと言われています。
前項で述べた本作のテーマをプロット面の流れで説明するなら
「もしプロトコルとシューマン共鳴の融合をさせたら、地球の意識と人間の意識を繋げる事になり、それこそが集合的無意識なものと繋がることなのでは」
ということを描いた作品だとも言えます。
98年当時の社会情勢と不穏な雰囲気
本作では日常生活シーンでなぜか重低音が鳴っていたり、電信柱や建物の影にピンクや赤が混ざったようなモヤやモザイクが浸食していたりと、常に不穏な雰囲気が物語を包んでいます。
背景や建物が白塗だけであったりすることも多く、それらは自分がどこにいるのか分からない、目的も分からないと言ったような自我の混乱や揺らぎを見事に表現しています。
90年代の後半について私は、バブルが弾け、人々が消費文化の残滓の中で、惰性とニヒリズムの中でひたすら無気力に踊っているような印象を持っています。
敗戦後、経済だけは好調だったのにそれもまたポキンと折られ、不況に突入し、人々が覇気を失っていく。
大人たちは無気力なまま、不可能である今までの現実を続けたいという、怠惰な思考放棄状態で仕事に向かい、そんな社会の意義を見出しえない大人に対し、若者は援助交際やブルセラ、ガングロなどで退廃的な抵抗を示し、倫理観は崩壊。
そんな時にノストラダムスの予言が重なっているわけで、まさに90年代後半は、退廃的な世紀末の雰囲気でした。
本作のスタートが基本的に猥雑なネオンの中の交差点なのも、それらの雰囲気の投影であり、またサイベリアというクラブも当時の渋谷系カルチャーを元にしていると思います。
ここで重要なのは、私たちが生きる現代もまた、90年代後半とは違うものの、ある種の退廃感や混沌の渦の中にあることです。
コロナが明け、戦争や紛争による物価高により、人々の生活は苦しくパパ活が横行し、若者は闇バイトに手を染める。
とはいえ90年代後半に比べると、一部の人の問題意識や政治の流動性は高まっているので、状況はまだマシかなとも思います。
しかし現代社会も、本作の世界観や精神性に非常に近い位置にある事は事実で、その意味で本作は今だからこそ見るべき作品なのだ、私はそう思います。
全てを表現しているオープニングの秀逸さ
本作のオープニングのアニメ映像は、驚くことに劇中での重要なメッセージや精神をほとんど表現しています。正直、圧巻です。
まずテレビを見ている大人たちや、ゲームをしている子供たちの画面上に、何かを口ずさむレインが映るわけですが、その顔は険しく、怒っているように映ります。
本作はかなり多種多様な問題提起や示唆があるので、あまり怒りという感情は目立ちませんが、その根底には現代社会の孤独や分断、そして思考を放棄している人間に対する怒りが確実に流れています。
物語序盤で、レインが電車の中の人間に対し、うるさい事を指摘するシーンがあります。
これはワイドショー的などうでも良い事ばかりを口にし、本質的な事は思考出来ない現代社会に対する怒りの発露を表現していると私は思います。
そして核心的なのはオープニングの終盤で、歩道橋の宙空で止まるクマのフードを置き去りにし歩き去るレインの描写です。
これは空想性や神の意識という要素を放棄し、肉体と大地が紡ぐ現実に戻るという劇中の選択をそのまま表現しています。(詳しくは後述の項目で述べます)
レインの象徴性
本作の主人公である岩倉玲音。
この名前自体が本作において表現したい事、メッセージについての象徴だと私は考えています。
まずレインを日本語に訳すと「雨」です。
そして本作のタイトルである「serial experiments lain」を日本語で表現すると、「連続した実験としての雨」という事になります。
「雨」という言葉には、大地と空の循環、そしてあまねく降り注ぐものというイメージがあります。
雲が雨になり大地に降り注ぎ、木々や山に流れ、その川が海へと辿り着き、そして再び空へと戻り、また雨となる。
その流れの中で生命は生きているわけで、雨というのは、生命・大地の恩寵です。
また名前の漢字に含まれる「音」にも注目するなら、雨や大地の循環には音が常に寄り添います。聖書の福音書にも音という言葉が含まれており、雨と同時に音もまた恩寵を現していると言えるのではないでしょうか。
後に述べますが本作において岩倉玲音は、集合的無意識的な大いなるものとリンクしている存在として描かれます。
本作のテーマの一つに、インターネットと人間の集合的無意識が結びついたらどうなるかというのがあるわけで、普遍的に偏在する無意識と、あまねく降り注ぐ雨という共通のイメージリンクが、主人公の名前及び物語に含まれているのだと思います。
その意味で本作は、偏在する無意識とリンクしたレインがあまねく世界を包み飲み込む過程を描いているわけす。
それは非常に思考的冒険で先験的であり、まさに連続実験の雨という言葉にぴったりだと思います。(連続という言葉にはゲームやアニメのメディアミックスとしての側面もあるかもしれません)
また名字である岩倉についても重要な意味があるように思います。
私は本作の裏モチーフに「天の岩戸神話」があると思っています。
これは須佐之男命の乱暴により嫌気がさした天照大御神が岩戸の中に引きこもり、光が失われてしまったのを、アメノウズメの踊りなどにより再び引っ張り出し、世界に光を回復させた日本神話の一エピソードです。
当たり前ですが、本作の舞台モデルは日本であり、ネットワークを通し、それを利用する日本人の精神を描いた物語が展開されます。
その上で、古代の日本神話とのリンクを示すことで、ネットワーク時代の神話的性格を強調しているようにも思えます。
本作では終盤、自身の思考のおどろおどろしい檻と化した、自宅に引きこもっているレインを、ありすが助け解放する描写や、自身の存在定義に戸惑い深海のような場所でうずくまるレインを、空にいる父が、神としての責任の象徴であるフードを脱がす手助けをしてくれる描写があります。(詳しくは後述)
これは非常に構図として「天の岩戸神話」と近いです。
また「岩」というのは古代の日本信仰や祭祀において重要な意味を持っていたことが確認されており、その意味で連綿と続く日本精神を含んだ文字だと言えます。
ここでさらに「倉」の字に対して過度な意味づけをするのは少しやりすぎな気がしますが、古代から律令時代、そして現代まで、倉は年貢米であったり大事な家宝を貯蔵していく、保管、言うなれば継続性の場所です。
その意味で岩倉玲音という名称は、非常に日本的で連綿と続く継続性を秘めており、かつ普遍性を象徴した名称だと思うのです。
岩倉玲音の内向性と空想性、純粋性
本作の主人公である岩倉玲音。
彼女の特徴はその内向性と幼稚性、そして空想性です。
高校性でありながら、家ではクマの着ぐるみを着て、部屋の窓にはぬいぐるみが溢れており、学校では辛うじて友人のアリスがなんとか交友関係を繋いでくれるものの、玲音から友人に話しかける描写はほとんど見られません。
90年代の後半から、漫画やアニメの主人公に熱血系やヤンキータイプではない、内向的なキャラクターが増えていきますが、岩倉玲音もまたその時代の少年・少女が抱えるナイーブさを象徴した様なキャラクターになっています。
この傾向は2010年代、20年代を経て現在でも続いており、むしろアニメ文化がサブカルチャーからメインカルチャーに躍り出たのもあり、より顕著になっているかもしれません。
ゆえにですが、玲音からは現代のZ世代にも共通する、内向的でありながら素直で真面目というような共通するファクターも見受けられ、今見ても違和感なく乗ることが出来る主人公になっています。
ただしレインはただ内向性で良い子というだけでなく、奥には無垢で研ぎ澄まされた純粋性があり、その純粋性こそが本作の主人公たらしめている要因です。
劇中において日常ではぬいぐるみたちに白いシーツがかけられているのに、ワイヤードとリアルワールドの境界が曖昧になる時にはシーツが取り除かれ、ぬいぐるみがくっきり浮き出る描写があります。
これは
日常世界では理性が幼稚性に制限をかけている状態だけど、無意識下が前面に出てくる時には抱えている幼稚性が出てくる
という象徴的な描写だと思いますが、玲音の純粋性を担保しているのは、その幼稚性でもあり、空想性や幼稚性は、純粋性と表裏一体で繋がっているのではと、私は思います。
難解な内容なのに本作が今でも人気があるのは、アニメや小説を見たり読んだりすることは好きだけど、人と接するのはどこか苦手という、現代まで続く若者の性質に寄り添い、かつその可能性を描いた岩倉玲音のキャラクター造形にあるのでは、そんなことを思うのです。
ネットワーク時代の予言の書
本作はWindows 95や検索エンジンが登場して数年だったネット初期の頃に作られたとは思えない程、その後のスマホやSNS時代の世相を言い当てており、その先進性には正直、度肝を抜かれるほどです。
NAVIという本作の中で現実のPCに対応する機器の描写には、最新式を配達のお兄さんが羨ましがったりと、現在で言うガジェット競争的なシーンもありました。
また本作にはアクセラという脳の演算機能を倍化する様な薬物が登場するのですが、それらは現代の若者のタイパ的指向や効率化、また映画を早送りする様な現象を言い当ててるようにも思います。
劇中の物語が進むにつれ、玲音はどんどんワイヤードの世界にのめり込み、NAVIを極端なほどに改造・拡張し、現実との境目が分からなくなっていきますが、これらもネットゲーム廃人やネット中毒による引きこもりなど、現代まで続く問題を表象しています。
また本作において重要な役割を担うナイツは、現代社会におけるネトウヨ的な存在や陰謀論を信じる人々と、とても重なります。
そして本作のラスボス的立ち位置である英利政美に関しては、現代のインフルエンサーや一部の学者にありがちな、テクノロジーの進化やAIの進化を思想的な裏付けもなく、技術論のみで無条件に肯定する人間を凝縮したような存在です。
その意味で本作の出来事は、言い過ぎかもしれませんが、現代で起きている事の縮図のように思え、ネットワーク時代である現代の事を予測した黙示録だ、その様に思うのです。
また本作では、ナイツやワイヤードの人々の書き込みや発言を、服や口はあるけど顔が無い人々が畳に正座し、ひたすらそれぞれが口だけで喋っているシーンで具現化しています。
これはとても皮肉で粋な描写です。
恐らく劇中のワイヤードの書き込みや発言は、今で言う掲示板やSNSに該当すると思います。
つまりこの描写は、畳という日本的なイメージの上で行儀よく正座しつつも、顔はバレない安全圏で、あることない事を無責任に言う浅薄な精神が、掲示板やSNS利用者の本質だよ、と言っているわけです。(全員がこういう利用者ばかりではない)
もちろんネット社会は悪いことばかりでなく、現代の政治を動かしたり庶民にとっては力になってる側面も大きいです。確実に無いよりはあった方がいい技術だと思います。
ただしどんな良いものも、使う人間の資質や性質に左右されます。むしろ本作は、ネットを描きつつ、本質的にはそれを使う人間や社会の問題を描いているように思うのです。
境目が分からなくなる
前項でも述べましたが、本作の主人公である岩倉玲音はワイヤードの世界にのめり込み、どんどん現実との境目が分からなくなっていきます。
どんどん研究所の生物兵器のように、パイプで拡張されていくNAVIの描写は、肉体を動かさずに自身の欲望や怠惰さだけが、執拗に絡まり、体の中から腐っていく、というような、ネット中毒者の心や健康状態を極端にデフォルメしたもののようにも思えます。
また劇中において、友人であるありすの自慰行為をレインが隠れて見ているシーンがあります。
アダルトサイトでは自慰行為を配信するライブチャットという存在があり、昔からそれなりの支持を集めていますが、それだけでなくそもそもネット自体が、自分が部屋という安全圏にいつつ、世界中のいろんな出来事を見れるという、ある種の覗き的な性質があると思います。
元々人間の精神は複雑です。
ゆえにどんな優れた人にも、他人の負の部分を覗きたい、または禁止されていることこそやりたくなるような性質が眠っていると私は思います。
ネットというのは日常生活に比べて多大な情報やサービスが溢れており、あらゆる欲望を簡単に成就させてくれるがゆえに、欲望の加速装置という側面があります。
本作の主人公であるレインは、ある種、性欲的なものから隔離されている様な存在として規定されていて、むしろ肉体的な性質はありすが請け負っているので、その部分はあまり深掘りはされていませんが、ネット社会が性欲にも強い影響を与えているのは間違いないと思います。
本作において主人公のレインがワイヤードにのめり込んでいくのは、どちらかというと欲望というよりは、世界に対する疑問、そして彼女が持つ純粋性や使命的な要素が大きいです。(大いなる存在とリンクしている為、詳しくは後述)
一方で玲音の内向的な性格と根源的に抱えている孤独が、彼女をワイヤード世界にのめり込ませるもう一つの大きな要因でもあります。やはり本作の重要なテーマは、現代社会の孤独なのです。
その意味でネットやSNS中毒というものの現代の原因もまた、不満や孤独が大きな要因にあるように思うのです。(承認欲求も孤独の発露の一形態だと思います)
そこにさらに様々な欲望が絡みついていくと、自身の脳はそこから出れなくなり、自我や認識に混乱をきたしていくのでは、そんなことを思います。
そのイメージを具現化したのが、パイプまみれのレインの部屋なのだと思うのです。
快楽とはという思考実験
本作のタイトルの一部である「連続する実験」の名の通り、劇中では色々な思考実験のような面白い発想があります。
例で言うと、ワイヤード上のファントマというゲームは、シューターゲームと、幼稚園の鬼ごっこが繋がってしまう(鬼である幼稚園児の方が狩る側というのは核心的)という99年当時においては非常に先駆的で実験的なアイデアだったと思います。
しかし凄いのは当時先駆的だと思われていたこのアイデアも、現実世界では、戦争での戦車や戦闘機とゲームを繋げるというような話もあり、あながち空論ではなくなっているということです。
本作のファントマのエピソードでは、一面では「快楽とはどのような性質を持つのか」という問いかけという面もあると思います。
そして現実でのゲームと戦争を繋げるというアイデアもまた、快楽により罪悪感を薄めるという、快楽の性質を利用した悪魔の発想です。
本作では様々なテーマを多様に含んでいる為、快楽についてそこまで深く掘り下げてはいないですが、これを深く掘り下げたのが「華氏451度」という作品だと思います。
華氏451度の世界では、焚書により人々が反射的快楽にだけ身を費やすディストピアが描かれますが、現代社会でもスマホによる反射的快楽のパワーが人々から集中力や思考を奪っています。
快楽は悪いものではないですし、生きていく為に必要なものですが、その付き合い方やバランスは非常に難しいものなのだと改めて思います。
ナイツとは何か
本作においてワイヤード内で重要な役割を担うナイツ。
劇中では、「情報の流通や操作により、たった一つしかない真実を事実にする行為者」という風に定義されており、その実現を目指すネットワーク上の集団がナイツで、自らを守護騎士の集団になぞらえています。
正直なところ、彼らがどういうルールや思想の元で動いていたのはピンときませんが、重要なのは彼らが極端なワイヤード原理主義の集団(現代で言うネット原理主義)というところです。
メンバーは会社の社長から普通の主婦まで様々であり、それぞれが現実社会では普通に生活しながら、ワイヤード内においてナイツとしての活動をします。
ナイツは、物語終盤で、ワイヤードのシステムと自身の意識を同期し、神になろうとした英利政美が、自身を崇めさせる存在として組織させた集団である事が明かされ、最終的に用済みになったら処分されています。
私は本作のナイツの描写というのは、現代のネット右翼や陰謀論者に非常に近いものがあるように思います。
ナイツのメンバーは全員が情報強者、あるいは自分が真理を知っているという様な特権意識を持っています。
これは現代のネトウヨや陰謀論者の「自分の信じている情報だけが正しい」「それらの勝利が絶対である」という誤った使命感と、とても親和性があるように思います。
ナイツが言う「たった一つしかない真実」という言葉は、まさにそれを裏付けており、自分が信じたもの、見たものだけが真実という様な、非常に狭く一方的な価値観を有しているのもまた、共通しています。
そもそも真実なんてのは時と場所と人の数だけあり、絶対的なものなど存在しないのであり、その中でいかに相手の主張を理解し折り合えるかが大事な事なのだと、私は思います。
またナイツという英語の日本語訳の「騎士」も、正義の厳格な実行者のような、一方的な自意識を称揚する非常にマッチョな名称のイメージが一面的にはあるように思います。
また本作は基本的にワイヤードとリアルワールドという二項対立の中で、その境目が曖昧になっていくという流れで進むわけですが、そこに進歩派と守旧派という流れも絡み、複雑に展開していきます。
その守旧派の代表が橘総研であり、進歩派がナイツです。
最終的に守旧派である橘総研の人々は、悲惨な最後を遂げますが、進歩派のナイツもまた同じく悲惨な最後を遂げます。
行き過ぎた両方の勢力にノーを突きつけているのもまた本作の一つのメッセージでしょう。
ナイツにしてもネトウヨや陰謀論者にしても、その奥には現実社会への不満や孤独があり、その怒りや反動による盛り上がりという側面があることも見過ごせない点だと思います。何度も書いていますが、本作の重要テーマは現代の孤独と分断なのです。
また英利政美がナイツを簡単に切り捨てたのは、ある種、非常に神話的なように私は感じました。
一部の分析や論説では、旧約聖書などで見られる、神の人々に対する厳しい仕打ちは、神である事を確認するには、支配しているという厳しい事実や行為が無くてはならないのでは、というものもあります。
その意味でナイツは英利政美にとって、自身や自身が構築した世界が神であることを確認する道具の一つだったのかもしれません。
守旧派としての橘総研
前項で述べたナイツが、極端な進歩派で描かれるのと対称に、リアルワールドにおける既得権・守旧派として描かれるのが、橘総研です。
本作のラスボス的立ち位置である英利政美が元々いた企業であり、NAVIを開発している先端企業ではありますが、劇中での行動から、イメージ的には守旧派に近く、むしろパイプや賄賂で事業を受注しているような、いわゆる癒着企業的な印象が個人的に強いです。
英利政美が本作で実行した案は、非常に極端なので認める事が出来ないのは分かりますが、彼らの言う「あくまでワイヤードはリアルワールドを補完するサブシステムでなければならない」という意見もまた、未知の可能性へ一歩先に踏み出そうという意志をまるで感じませんし、裏には今まで通りのことを前例踏襲で続けたいという、官僚組織的な停滞感があります。
また「リアルワールドでもワイヤードでも神など必要ない」という言葉からは、信仰心が薄く、自身の快楽や経済的利益にのみ従事する日本の企業、もっといえば、大多数の日本人全体の傾向をよく現わしているとも思います。
面白いのは、本作において最初に敗北するのは守旧派的な橘総研ではなく、進歩派であるナイツだということです。
これは組織的パワーとコネクションを持つものが、如何に強いかという証左でもあるように思います。
特に村社会の延長という性質が強い日本社会で顕著ですが、出る杭は守旧派により打たれるのです。
そして本作がよりリアルなのは、守旧派が敗北する時でも上層部は守られ、下にいる者だけが簡単に切り捨てられることです。
リアルワールド維持という理念の下で戦っていた実動部隊は、英利政美と繋がっていた(いいように利用されている)上層部の意向により簡単に始末されました。
結局のところ、理念は形だけで、自身の利益が最大化出来れば、どんな立場にも転身を遂げるというのも、非常に現代社会における上層部の人間性を良く現わしているなと思います。
英利政美という偽神
本作における最大級の重要人物、そしてラスボス的な描かれ方をしている男、それが英利政美です。
ワイヤードのシステムの根本であるプロトコルに、地球自身が出す微弱な電波(シューマン共鳴)と自身の意識を埋め込み、自身と地球とワイヤードとを一体化させる。
つまり集合的無意識とワイヤードを繋げ、現実世界とワイヤードの境目を無くし、その一元化された世界のコントロールをするような神的な存在になろうとした。
それが英利政美の狙いであったと私は解釈しています。
まるで日本の古い神事を模したような赤い顔の模様や、アノニマスな存在としてワイヤードを支配したいという発言からも、英利の自身を神になぞらえたいという嗜好が分かります。
彼が言う、「肉体の進化の限界は神に決定づけられており、それを超えたい」というのは、非常にニーチェの超人的な考えですし、ある種、ガンダムにおけるニュータイプの様な考え方のようにも聞こえます。
また「最も進化した人間は、それより高い機能を人に持たせる権利がある」という趣旨の発言は、傲慢な優生思想の発露であり、歴史上の様々な権力者を想像させます。
レインや人々をソフトウェアやプラグラムに過ぎないと彼は言いますが、それは彼自身が自身を高い位置に置きたい、他人を自分が改変可能で、害を与えないプログラムと思いたいという意識が働いているのではとも思います。
本作において英利政美は、ありすの手助けにより、肉体や大地の価値観に目覚めたレインにより葬られます。(詳しくは後述)
その時の矛盾を突きつけられ我を失なった、巨大な目玉や手が絡まり、まるで腐った男根のような怪物に変貌する姿は、非常に象徴的です。
完全に敗北した後は、言葉を悪く言うならパイプの人糞の塊のように見えました。
ここまで述べた発言や人間性を見た時、私は英利政美を、現代において何の精神的・哲学的な思考も無しに、ただネットやAI技術を称賛するような、一部の学者やインフルエンサーと非常に親和性がある存在だと考えています。
その意味で敗北前のグロテスクな姿が、やたら目だけが大きいのも、新情報ばかりに目がさとく、精神性が無い事を現わしているようにも思えます。
また、ネット技術の進化が凄いのは別にその人自身が凄いわけでもないのに、まるでそれが自身の全能性の証左のように思う浅薄さやおぞましさを、腐った男らしさとして、男根のように表現しているのではと感じました。
既に述べていますが、私は本作のテーマは、集合的無意識や、神という存在の省察と同時に、現代人の孤独であると思っています。
その意味で言うと、英利政美の根本の動機というのも実は、物語最初に自殺した四方田千砂と本質的には同じであり、それは孤独なのだと思います。
現代社会で居場所がなく、人と繋がれずに自殺した千砂同様に、英利政美も会社や社会に排斥され居場所がなく、孤独や不満を抱えていたのです。
その意味で、自身を神だと考えるような歪んだ自意識を生んでしまうのは、殺伐とし人に寄り添う視点を欠いている現代社会なのかもしれません。
ありす、肉体や大地の象徴
玲音の事を本気で考えてくれる唯一の友達。それがありすです。
自身はクラス内において、陽気で目立つグループに所属しており、かつ内向的なレインをクラスに溶け込ませようと意識もしている、人が良く、非常にバランスの良いキャラクターとして描かれているありす。
個人的に自分が、ほっといてほしいタイプの陰キャなので、若干彼女の事を面倒くさいなあと感じもしましたが笑 しかし良い友人であることは間違いありません。
玲音の項目で、天の岩戸神話についての関連性を述べましたが、アリスについては西洋の物語である「不思議の国のアリス」のイメージが投影されているように思います。
ありすは、ワイヤードとリアルワールドの境目を破壊してしまい、英利政美の言葉により、「人間存在はただのプログラムに過ぎないのではないか」と疑心暗鬼の中にいる玲音に対し、肉体の鼓動である心臓の音を聞かせ、生命の感覚を喚起し、その暗闇を晴らすという役割を果たします。
日本神話において天照大御神を岩から出すのは、アメノウズメという神の役割です。
しかし本作においては、その役をありすが担います。
一方で、赤と青の色が混ざったような、おぞましい異世界のようになっているレインの自宅に入るのは、不思議の国のアリスの穴に飛び込むという象徴も重なっているのではと思います。
そしてレインに肉体の力を気付かせ、暗闇から解放するのは、まさに天の岩戸神話の投影であり、このシーンは二つの物語の象徴性を帯びているように思うのです。
大きい視点で眺めると、日本神話と西洋の物語のミックスとも言えるかもしれません。
そもそもインターネット自体が、西洋文明の中から誕生したものであり、その意味でもインターネットをモチーフとした物語である時点で、西洋と日本の文化の混合という要素は含まれているように思います。
さてここからは、ありすがレインを救うその裏にある根本的な役割や意味について深掘りしていきます。
その本質は、肉体と大地の価値観です。
玲音は背が小さく、非常に内向的かつ無垢で、どこかしら中性的に描かれるのとは別に、アリスの容姿は普遍的な高校性の女の子として描かれ、性格も素直で明るく、学園生活を謳歌しています。
彼女には大地が培ってきた肉体や愛情という感性がベースにあり、バランスよく現実世界を生きていける存在として描かれているわけであり、その背景にはしっかりと両親に愛されて育ったというのがあるように思います。
人間はそもそもとして太陽光を元に地球の大気や水、土から生まれた存在です。その肉体が連綿と遺伝として受け継がれ、進化していき現代の人間があるとするなら、今ここにある肉体というのは、歴史が大地と共に培ってきた愛情の証左だと考えてもいいかもしれません。
哺乳類にとって最も大事なのは、母の愛やスキンシップであるというのもまた、いかに肉体を媒介したコミュニケーションが大事で、かつ我々がそれと共に歩んできたのかというのを現わしているように思います。
また本作には、男性教師のことを思いありすが自慰行為をするシーンがあります。
このシーンの狙いとしては、ありすが性欲・愛欲という役割を本作において担っているという面もあるのではないかと、個人的に考えています。
私は性欲というものは、人類を繋いてきた愛の発露でもあり、本来的に大地に近いものなのだと思うのです。
またこれは主観に過ぎませんが、親に全力で愛されてきた人は、性欲が割と強く、かつ性に対して、ネガティブなイメージを持っている人は少ないように個人的に感じています。
ありすは、「自分自身を存在の垣根を崩すプログラムでありアプリケーションだ」と言うレインを優しく否定します。
体は冷えて冷たいけど玲音の体は生きていると言い、そして玲音と共に心臓の音を聞き、お互い笑い合う。
これこそが本作において最重視する哲学や思想を端的に表現したシーンであり、この大地の力に英利政美は敗北したのです。
レインも千砂も、つまるところ英利政美も、現実世界の孤独や分断から、全員が繋がれる世界を意識的にせよ無意識的にせよ、ワイヤードに求めてきました。
しかし最終的にレインを救ったのは、性格も嗜好性も違う他人だけど、友達であるありすでした。
私は、人間とはそれぞれが違うからこそ、相手を理解しようとし、コミュニケーションが生まれ進化してきたのだと思います。
その意味で肉体を消し、無意識を一として繋がってしまったら、そこに孤独は無いかもしれませんが、愛や喜びもないように思います。虚しい精神の全体主義です。
本作においてレインに、肉体と大地に根差す愛情を気付かせたアリスの役割は、非常に大きなものだと思います。
集合的無意識と神
地球そのものをニューラルネットワーク化し、地球自身の意識を覚醒すること。
本作で英利政美は自身の目的をそう語っています。
本作は、「人類がネットワークを通し繋がる事は、突き詰めると集合的無意識的なものと繋がる事ではないか」という一つの思想実験を主軸においている作品です。
それの実行役として設定されているのが英利政美で、彼はそこに神として君臨しようとしました。
本作の革新性は、情報ネットワークという科学的なツールを、人間が利用したり情報を共有するという点に着目し、ネットワークというのは精神的心理的に人間を繋げる存在なのではという問いを物語の中心に据えた事にあります。
本作が放送された時には、まだ検索エンジンも出たてで、SNSなど存在しなかったことを考えると、現代でさえ言及の少ない心理的・根源的な視点でのアプローチは脱帽です。
本作のタイトルを和訳すると「連続した実験としての雨」であることは既に述べましたが、まさにあまねく人間精神に広がる集合的無意識を雨に見立て、ネットワークと集合的無意識が繋がったらどんなことが起こるかという、思考実験を行ったのが本作なのだと思います。
そしてその物語の中で、集合的無意識で全存在を繋げ、そこに君臨することで神を目指したのが英利政美なのです。
さてそれではここから結果として、その実験がどうなったのか、そもそも何をもって神と言えるのかを考えていこうと思います。
物語終盤、レインを、偏在する集合的無意識を英利政美が肉体化した存在であると述べます。
英利政美の目的は、人間が持つ集合的無意識をネットワークと同化し、リアルワールドとワイヤードを一元化することですから、その目的の遂行役のプログラムとしてレインを肉体化したというのが、英利政美の理論です。
前項で肉体と大地の価値観により英利政美が敗北したことは既に述べましたが、覚醒した時のレインの言葉の要旨は短いながら核心をついています。
「それはあなたが考えたことなのか」「だとしてもその前はどうなのか?」
いかに英利政美が二つの世界の境目を崩そうと試みたとて、過去の歴史・蓄積は消えません。そもそもの英利政美自身、子供だった時代があり、学者でなかった時代があります。
つまりいくら集合的無意識と現実を繋げたところで、地球や人間にはそこまでに至る連綿たる物語があり、その力は強固なのです。
言うなれば、英利政美であれ、誰であれ、私たちは地球という物語の途中参加者に過ぎないのです。
さらに英利政美が自分の頭で考えたアイデアでさえ、それまでの研究者の先行研究や悪戦苦闘があるからこそ、成立っていることは言うまでもありません。
そう考えると英利政美が神とはとても思えなくなります。
レインが「ワイヤードはリアルワールドの上位互換じゃない」と言う趣旨の発言をしますが、そもそもリアルワールドがあって、その影響下でワイヤードが生まれている以上、上下ではなく、相互補完の関係で考えた方がいいのです。
英利政美も現代のネット原理主義的な学者も、ここの視点が欠けており、ネット社会を現実より高くおいているように思います。(逆にネットワークを低く評価することも論外。ネットワークも現実世界の一形態です)
レインが、ワイヤードは情報を流すフィールドに過ぎず、共有されている無意識や膨大な蓄積に繋がることは出来ても、それ自体に人は迫れない、という趣旨の事を言いますが、これこそが本作の思想の核心部分でしょう。
ここに英利政美の計画が破綻していたことが明らかになります。
つまり英利政美がやったのは、現実世界とワイヤードの境目を壊そうとしただけであり、人の肉体を消し、情報データに同化することは出来ても、地球自体の意志には全く迫れていないということです。
確かに英利政美は集合的無意識と人間が呼ぶ何かとワイヤードを繋げ、良いところまではいきました。しかし結局は本当の神の使い手であるレイン(次項目にて詳しく述べます)に全て引っ繰り返され、世界は元通りになっています。
そもそも便宜的に、本作が描く大いなる深淵を、集合的無意識と呼んでいますが、それはユングが提唱した言葉を援用しているに過ぎず、膨大な記憶や記録と無意識が眠る深淵については、人間の言葉で表現できるものでは無いのかもしれません。(私はそれらを神と呼んでいいのではと思います)
本項目における「集合的無意識と神」というタイトルに関し、こと英利政美について言うなら、その本質に全く迫れてないし、その精神の欠片も掴めていないという事です。
そもそも英利政美にあるのは技術や手法だけであり、精神性や哲学性は感じられません。
彼には神への洞察や哲学的省察がまるでないのです。そもそも本気で神という存在を信じていません。意識しているのは自分が神の様な存在になる・なれるということだけです。
そこにあるのは、孤独や疎外感により歪んだ、自身が権力を振るいたいという欲望だけであり、彼が憎んでいるであろう守旧派の古い感覚の人々と実はほとんど変わりません。
とどのつまり、彼がなれたのは限定された場の中における神のおままごとでしかなく、所詮はただの部門長に過ぎませんでした。
レインは天使である
迷い苦しみながらも、肉体と大地に裏打ちされた価値観により覚醒し、英利の計画をオールリセットしたレイン。
本作の物語の流れや、天の岩戸神話との関連性を俯瞰してみた時に、レインこそが本当に神の意志に導かれた存在、言い換えると、すなわち天使なのではないか、私はそんなことを思います。(物語内でタロウがレインの事を天使と言及する場面があります)
レインが劇中で言及するように、人は神様という存在を作り、祈り、それらの効用を信じてきました。
それらの人々に偏在する無意識の象徴的存在がレインなのだと本人が劇中で言及しますが(その真偽は本項目内で書きます)、作品全体を見通しても、祈りに代表されるような純粋性の象徴がレインなのは間違いないと思います。
言い換えるなら、祈りの純粋性が、歪んだ利己心を倒した。本作はそのように捉えることが出来るかもしれません。
さて本作の謎に、肉体として存在したレインは、英利政美が集合的無意識を具現化した存在、つまりレインは英利が作り出したのかという疑問があります。
私はこれはノーだと考えています。
これまでの個人的考察を踏まえると、所詮、英利政美はテクノロジーを万能と勘違いした、ワイヤードという世界の偽神に過ぎません。
つまり英利政美は集合的無意識を集めてレインを作ったのでなく、肉体を持つレインと集合的無意識をリンクさせたと思っていただけなのだと思います。
本作は、本当の神の使いであるレインが、偽神である英利政美を倒すのが大まかなメインプロットなのであり、レインだけは最初から英利政美の影響下になかったのでは? つまり英利政美は大いなる存在によりレインを自分で作ったと勘違いさせられていたのではないか、私はそう考えています。
そうなると英利政美は自分を倒す真の存在を、自ら手助けしていたことになり、それもまた皮肉です。
本作の物語は四方田千砂の自殺から幕を明けます。
これは現実社会で虐げられた存在、弱く純粋な存在の孤独の臨界点、爆発であり、実はこここそが真の大いなるもの、集合的無意識なるものがレインにリンクした瞬間だと私は考えています。
あまりに辛い現実の孤独が臨界点に達した時、本作の物語がスタートしたのです。
その意味で英利政美は、その物語で思考深める為の材料を提供するピエロに過ぎません。
本作は最終的に四方田千砂が願ったワイヤードにより全てが繋がる世界、そして英利政美が目指したデータや情報に一元化されるような、全部が一になるような社会を否定しています。
なぜならそれらの社会は繋がるということではなく、同じになるということであり、本作では真の繋がりについて、自分と違う他者も大いなるものに繋がっていること、それらの価値観を元に他者に対する想像力で思いを馳せるということを、提唱しているように思うのです。
本作は大いなる存在により覚醒した、天使であるレインが、偽の神である英利政美を倒す物語である、私はそのように捉えています。
それをより精神的に言い換えるなら、厳しい孤独な現実の中で、行き場を失った純粋性が、悩み思考し、ある悟りに至る物語である。その様に言えるのではないかと思います。
次の項目では、全てがリセットされた世界でレインはどうなったのかについてを詳しく考えていこうと思います。
レイン再分離説
物語の最終盤、レインが自身の定義の趣旨を「偏在するもの、みつめるもの」と言及します。これは多くの哲学者が定義する神様、もしくは集合的無意識のイメージに近い概念です。
その後レインは「神様になれば楽でいい、誰も嫌いにならない」という旨の発言をするものの、果たして自身の肉体を消し、集合的無意識と完全に同化することがいいのかを考え悩み、身動きが取れなくなります。
私はこの場面こそが、本作における重要なターニングポイントなのではないか、そう考えています。
この場面で、もしレインが本当に神様のような存在になろうと選択した場合、それは英利と同じ道です。
前項でも書きましたが、その場合はあくまで大いなる存在である神の下の部門長に過ぎず、神を目指せば目指すほど、大いなる存在からは隔絶されます。
しかしレインはここで「私はどこにいるの」と自身に問いかけ、悩みます。
ありすの手助けで、肉体や大地の価値観の重要性を認識しているレインには、全てが一になるような普遍的存在になることに対し抵抗感があるわけです。
その後、悩むレインの上空で、雲の中に現れた父(この描写の象徴性は下記で言及します)がレインのクマのフードを取るように促し、レインはフードを脱ぎます。物語が転回し、一つ先へと踏み出す重要なシーンです。
本作のモチーフに「天の岩戸神話」があることは、これまでにも述べてきましたが、ここもそのイメージを投影しています。
天の岩戸神話において天照大御神は、アメノウズメの踊りをきっかけに閉じこもってた岩から出され、光の力を回復します。
本作では、フードを被り内なる思念に閉じこもっていたレインが、父的イメージである存在のパワーにより、フードを脱ぎ、そこから解放されるわけで、ここに神話とのリンクがあります。
それではこのシーンが象徴している事柄について、くわしく見ていきましょう。
父という存在はある種、現代では家父長的なイメージがある為、マイナスに取られることもありますが、そう言う事を抜きに歴史的なイメージを主軸に考えると
父→家族→家や共同体→歴史→地球や大地→神
というように肉体や大地、共同体、神に連なるものの様に、様々な象徴性を含んでいるワードです。
この場面での父、というよりそれ以外のシーンでもレインの父は家族で唯一レインに温かく接している事に着目するなら、大地に連なる優しさやぬくもりの象徴と捉えてもいいかもしれません。
本作の英利の役割は、欺瞞と虚栄心という偽の神でしたから、そこを繋げて考えると、ぬくもりの父性と欺瞞の父性という二つの比較対象という側面もあるように思えます。
さて次にフードについてです。
このシーンにおいて、レインはフードを脱ぐことにより、自身が神的存在になることから下りたのだと私は考えています。
ここまでで述べた様にそもそもレイン自身が、純粋性・幼稚性・空想性の象徴であり、このシーンのクマのフードの他にも部屋には動物のぬいぐるみが沢山あります。
ここで次にフードのクマや着ぐるみについて考えてみます。
クマは様々な国において神の象徴として神話のモチーフになっており、アニミズム的なイメージを帯びています。
そして着ぐるみやフードを被るという事は、一種の空想への逃避。幼稚性・妄想的な思考の象徴でもあります。
まとめると、クマのフードは、このシーンにおいては特に、神的なイメージと空想的なイメージが合わさったものとして表現されていると言えるのではないかと思います。
レインの空想性に関しては純粋性と隣り合わせでもあり、クマのフードに関しては別段否定的なイメージは帯びていないと思うので、いっしょくたにすることは出来ませんが、英利政美の自分が神になるという意志も、ある種の脳内での行き過ぎた空想から出てきたものとも言えます。
その神性や空想性の象徴であるフードをレインが脱ぐということは、神になることから下り、空想的な状態から、肉体的な大地の世界に戻る事を選んだ、そういうことなのではないかと私は思います。
要はレインは現実世界の大地に着地したのです。
さて物語では、レインはこの後、成長し恋人と歩くありすのいる未来へと飛びます。
この場面は、劇中で語られる「記憶とは過去のことじゃなく、現在の事、明日のことも含む」という趣旨の発言を具現化したシーンであるように思います。
ここでいう記憶とは、本作で英利が語る様な、情報として書き換えれるようなコンピュータ―的記録みたいなものとは全く違います。
ここでの記憶は、人類が今まで大地と共に蓄積し、かつ歴史すら超え人類を繋げているような「大いなる深淵の一部」のようなものだと思います。
我々はそれを語る時に集合的無意識という言葉ですましがちですが、本来その深淵は言語化出来るものでもないし、どういう性質かも分かってはいないものです。
しかし大事な事は、レインがそれを恩寵として感じ取り、その思いに呼応するかのように未来ありすとの会合を果たしたということです。
自身が神になることを目指した英利は、それを目指したところで所詮、深淵たる神の下にある部門長に過ぎませんでした。
しかしレインはフードを脱ぎ、神を下りました。
さて一旦ここで、神を下りたことの精神的意義について語る前に、現実世界の肉体を持つレインについて私の考えを書きます。
私は新しくスタートした世界には、しっかり肉体を維持し普通の一学生として生活しているレインがいると考えています。
流れで言うと
① 四方田千砂の自殺により、孤独と哀しみの臨界点が超え、大いなる存在とレインがリンクする
② 孤独と哀しみの中から英利政美が覚醒、ワイヤードとリアルワールドを繋げる
③ レインは様々な事を通じ、悩みながら思考や思索を深め、ありすの力を借り英利政美という偽神を倒す
④ 大いなる存在と大地の恩寵を認識したレインは、世界を元に戻した後、恩寵とは常に繋がっている事を認識し、再び個人としてのレインに戻る
これが本作の大筋の流れではないかと思うのです。
上記に関しては、具体的な根拠があるわけではなく、それぞれ色んな解釈があると思いますが、フードを脱いだことやその他もろもろの事を考慮すると、現実世界の肉体レインと、大いなる存在はここで再分離したと考えるのが妥当のように、私には思えるのです。
考察冒頭で述べたように、私は本作を一つの書物のように捉え、物語の進行そのままの時系列を重視すべきだと考えています。
そう捉えると、レインがサイベリアで、自分に似た存在の噂を知るのは、四方田千砂の自殺の後であり、大いなる存在とリンクした後なので、集合的無意識的な流れと性質で、それらが人々の中に現れたと捉えることも出来ます。
とはいえ本作においては、厳密な事実の特定や断定ははあまり意味をなさず、それよりも制作者が伝えたいのは、それらが表す背後の精神性やメッセージだと思うので、大まかな認識さえあればいいのかなと、私は思います。
さてレインは神になることを下り、そして大いなる存在・記憶の恩寵を理解し、個人に戻りました。
私はこの行為とそれを支える思いこそが、実は神に近づく行為であり、そしてこれこそ本作が示す最重要なメッセージではないか、そう考えています。
自ら神になろうとした英利はむしろ神との隔絶した距離にありましたが、レインは一個人であることを選び、かつ大いなる存在の恩寵に思いを馳せました。
これを自分なりの言葉で要約すると以下の文章になります。
個人は全て、大いなる存在や深淵と繋がっており、そしてそのことに思いを馳せれる想像力さえあれば、それは神と繋がっていることと同義であり、もはや神と同義である
つまり本作は、想像力さえあれば本質的に人間はおしなべて神様である、そう言っているのではと思うのです。
こうやってみるといかに、自身が特権的で選ばれた存在だと認識していた英利が、神から遠ざかっているのか分かります。
全ての他者や存在に思いを馳せる想像力が神の意識ならば、選民意識や優越感などはその真逆にある思想だからです。
前半のオープニングの項目でも述べましたが、歩道橋の上でレインの頭から離れたフードが宙空に浮き停止し、レインはフードをその場に残したまま歩き去るという描写があります。
これは空想性や神になるといった意識の象徴であるフードを脱ぎ、現実世界を歩き始めたことを現わしています。
そして未来ありすとの会合は、レインが、個人に戻る選択をし、かつ大いなる存在の恩寵を理解したからこそ、記憶の繋がりを象徴する一つの奇跡として実現したのではないか、私はそんなことを思います。
大いなる存在に思いを馳せる事。それはそこから生まれた大地、そして大地が紡いできた人間に思いを馳せること。
そして考えは違っても、自分と他者は大いなる存在により繋がっている、それを認識すること。そうすれば人は分断を超え、孤独を癒し、神のぬくもりに辿り着けるのかもしれません。
もしこのメッセージから、日常における大事な生き方を抽出するなら、いくら考えが違くても相手の主張を聞き、相手の考えに思いを馳せ、どこかしら共感し、理解する事が大事で、その延長線上に普遍的で調和的な幸せがある、こういうことかなあとも思います。
その意味で物語冒頭で、四方田千砂が言う「現実世界では繋がれない」という主張は、本作のある種の問いだったのかもしれません。
その答えは、月並みですが想像力があれば、どんな場所にいても人は繋がれる。その様な事だと思います。
ただし本作は重要な精神性は示しつつも、それでなお現実が厳しいというリアルに対する目線も忘れてはいません。それについては次の最終項目で述べます。
本作が示していること
1998年に作られたとは思えない、圧倒的な質量と先見性溢れる数々の示唆、とんでもなく深い洞察を秘めている本作。
スチームパンクを彷彿とさせる舞台背景や不穏な雰囲気も含め、非常に黙示録的であり、エンタメ作品の枠に収まり切らない、啓示的で心の底が震撼するような魅力は唯一無二です。
現代においてはネットワークが世界中を網羅し、ほとんどの人がスマホを持ち、AIが加速度的に進化しています。
それに伴い様々な学者やインフルエンサーが様々な事を語っていますが、私はそのどれもが本作に追いついていないのでは? もしくは本作の持つ神学的・思想的な深掘りが欠けているのでは、そんなことを思います。
2024年の現在においても、本作は時代の数歩先を走っている。私はそう考えています。
既に述べましたが、本作は、守旧派も否定しているけども、行き過ぎた進歩派もまた否定しています。
技術論を中心に自分が神になることを企て、歪んだ男根のような怪物になった英利政美は、技術や情報理論だけを重視し、思想や思考を手放している学者やインフルエンサー、そして何も考えずネットワークを使い続ける私たちの醜悪なカリカチュアのようにも思えます。
本考察における物語のメッセージの解釈は、大いなる存在を感じ、かつ他者に寄り添う想像力を持てば、自分自身が純粋性と繋がった普遍的な存在になり、幸せに辿り着けるというものです。
つまり人間が豊かに感じ、悟ることが出来れば、それぞれが神と同義なのです。
ネットワークやデバイスは確かに重要であり、誰かと繋がる機会を提供してはくれますが、自身や他者の肉体、そしてそれと連動する心と向き合わない限り、孤独は癒されないし、普遍的な幸せには辿り着けない、その様な事を本作は示しているのではないか、私はそう思います。
レインは最後、視聴者に向けて「私はここにいるの、だから一緒にいるんだよ、ずっと」と言いますが、自分自身と向き合い、他者との繋がりを信じることが出来れば、常に普遍的で純粋な恩寵がある。
その様なことを、純粋性の象徴であるレインが、常に一緒にいると言うメッセージで示したのだと思います。
本作は現代社会・ネットワーク社会を生きる指針を示す福音書の様な作品なのです。
しかし一方で重要なのは、本作のラストシーンが、不穏な重低音の中で、依然変わらないネオンをまとうビルと、曇った空が目立つ景色で終わることです。
これは、依然変わらないし、変わる兆しの無い、現実社会の世知辛さ、濁っている精神の掃きだめとしての都会という、厳しいリアルの表現であり、本作の主張を実現し浸透するのが如何に厳しいのかということを、制作者が誠実に表現しているという証左だと思います。
現代においては、個人的に90年代よりは、まだ希望の目が出てきているように思いますが、ネットワークの進化により分断は加速度的に進み、そして自身の思考を放棄しそれをデバイスに任せている人も沢山増えているように見受けられます。
つまり現代は依然、本作の示す暗いネオンの街の雑踏の中にいる、私はそう思います。
私は本作を視聴し、自身とデバイスやネットワークとの距離、そして自身の体と精神とのバランスについて思いを馳せ、また大いなる存在や神について、真剣に問い直しました。
もちろん、神学的なことは軽々に結論なんて出ないし、それ以外の様々な事も、おそらく時と場所、人により結論は適時変わるものだと思います。人間は複雑であり、だからこそ考え続けなければいけないのでしょう。
その意味で人生は、思考的な「serial experiments」=連続する実験であり、常に問い考えていく必要があるものなのかもしれません。
本作は私に魂を揺さぶるような深い感銘と、思考する重要性や新たな視座をいくつも提供してくれました。
そんな素晴らしい本作に感謝し、本考察を終えます。