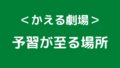悪いことが起きると、連鎖は続く。
気持ちから来るものなのか、それとも私が担う運命なのか、1回何かがあると、その後の行動に全て悪運が付いて回る気がします。
その日は、朝起きた時から、何かもやもやした感じでした。
だがしかし!
「この気持ちを認めてしまったら最後、悪運の連鎖に巻き込まれる!!」
今までの経験から、そう危惧した私は、あたかも素晴らしい朝のような笑顔を作り、トーストを焼き始めました。
しかし、そんな付け焼刃を運命はあざ笑います。
いつもと全く同じ焼き時間にもかかわらず、トーストはものの見事に焦げていたのです。
しかしここで運命に膝を屈するわけにはいきません!
黒いことは見て見ぬふり!
そしてほろ苦い失恋の様なビターさを、夏の花火大会みたいな甘酸っぱいハチミツの味に脳内で無理やり変換し、玄関に向かいます。
しかし再び運命の魔の手が私の肩に手をかけます。
ふとTシャツの肩のところを見ると、目やにが肩にピトッと載っていました。
この時点で怒りの感情がお腹の中で火のようにじわじわ広がりますが、急いで鎮火。
「目やにだってたまには外界に出たい時もあるさ」
と若い旅人を送り出す穏やかな老人の人格を無理やり作り出し、負の運命の泥沼を回避します。
さて、玄関で靴を履いた時。
ゴリッ
何ということでしょう!!
靴の中に小型の石があり、私の足裏にダメージを与えたのです。
・・・・・
発狂しそうになる自分を必死に抑え、石を庭にゆっくり放つ私。
1回深い深呼吸をして、そのまま家を出て歩き出します。
ところが歩き出してすぐに、またしても靴の中に違和感を察知。
「何かチクチクするぞ」
感覚で判断するに、どうやら木のトゲみたいなものが、靴にあり、それが私の靴下を今にも貫通し、刺し傷を与えようとしているらしいのです。
「とにかく一度、靴を脱いでトゲを取らねば」
そう思い、立ち止まると、目の前から近所のおばあさんが犬の散歩をしながら歩いてきます。
靴にかけた手をとっさに戻し、表情筋を無理やり動かし、にこやかに挨拶する私。
おばあさんの返した会釈を見送り、筋肉を弛緩、真顔に戻り今度こそと思い靴に手をかけます。
しかし今度は車が迫ってきているのが目に入りました。
手を戻し、車をやりすごし、今度こそと思った時。
自転車の少年たちの集団が、私の傍をあざあわらうかのように次々と駆け抜けていきます。
・・・・・
私は再び深呼吸して心を落ち着けます。
「もうこうなったら駅まで行って、そこのベンチに座ってゆっくりトゲを取ろう」
適格で冷静な武田信玄の様な判断を下した私は、慎重に歩き出します。
しかし、歩き出して2歩目ぐらいで
グサリ
しっかりとした痛みが足を貫きます。
トゲは靴下防御部隊を撃破し、肉体に刃を打ち込んだのでした。
この段階で、私は空を見上げ
なぜだあああああああ
と叫びました。
完全に負の運命に、意識と感情が負けた瞬間です。
一度崩れてしまうとあとは人間もろいもの。
心身共にズタボロの私は、途中で自転車や車に歩行を何度もさえぎられながらも、ほうぼうの体で何とか駅に辿り着きました。
「何か嫌なことが起きた時は、気持ちやリズムを切り替えることが大事!!」
と言いますが、私は気持ちを上手に切り替えられた試しがありません。
何をしたところで一度は絶望の底に叩きこまれて、そのまどろみの中で、時間がたつと徐々に光が射しこんでくる・・・
といった感じで、結局解決するのは時間のみなのです。
私には切り替えスイッチの様な便利な物は与えられていないのでございます。
そんなこんなで、駅前で無事にトゲを取り、現代社会への恨みを抱えて電車に乗る私。
しかし悲劇はここで終わりではありませんでした。
目的の駅につき、ふと鞄を見ると、大変なことに気付きました。
本を忘れた・・・・
そうなのです、私は外出時に常に読みかけの本を3冊程度持ち歩くのですが、この日は全ての本を家に忘れてきてしまったのです。
そしてスマホを見ると、電車の中でYouTubeを見ていたため、充電の残りがわずか10%でした。
なぜだあああああああああああああ
早くも二回目の、運命に膝を折った瞬間でした。
私は、基本的にぼーっと色々考えるのが好きではありますが、常に読むものや見るものが鞄に控えてないと心がそわそわして、心臓がきりきりしてきてしまうのです。
このままでは、あと10分位でYouTubeは閉ざされ、ただ運が悪い、情けない顔をした男が世の中に放り出されてしまう。
私は、とにかくスマホで本屋を探すことにしました。
「小さくてもいいし、ブックオフでもいいから、とにかく私に本を供給できる場所を指し示したまえ」
しかし、そんな敬虔な祈りも虚しく、その駅にあるのは、学習塾や、焼肉屋ばかり。
「いい加減にしないと、塾の教室で肉を焼かせるぞ、この野郎!!」
と理不尽な怒りのセリフを脳内の生徒たちに叫んでいると、1件だけ検索がヒットしました。
どうやらそこは昔ながらの古書店のようです。
「とりあえずそこで文庫本1冊でもいいから確保しよう」
そんな思いを元に、古書店に向かいます。
早歩きで、駅の裏を10分位行くと、くすんだコンクリートの小屋みたいな建物が見えてきました。
その小屋の正面には
「薬廻堂書店」
という看板がかかっています。
ようやく本屋を見つけた安堵と、急ぐ心を抱えて、店頭に並んでいる古びた専門書には目もくれず店内に入る私。
店内は、横二つの大きい本棚で仕切られており、店内の奥には、ひげを生やした店主らしきおじいさんが座っています。
とにかく安い文庫本を探そうと思い、本棚を見ていくと壁際の奥に黒い暖簾があり、その暖簾に
「特別文庫本コーナー」という紙が貼ってありました。
その暖簾をくぐり、棚を見ると、そこには本はありません。
なんとそこには、きれいに等間隔に並んだ、「生卵」がありました。
私は本を買いに来たのであり、すき焼きの為の買い物に来たわけではありません。
私は、店主に詰め寄ります。
「すいません、卵じゃなくて文庫本が欲しいんですけど」
「ほっほ、若いの。よく見なされ」
そう店主に促され、よく生卵を見てみると、卵を立ててある卵ホルダーに
「純文学」「ラノベ」「漫画」
などの文字がゴシック体で書かれていました。
「お望みのジャンルを割れば、そこから本が出てくるのじゃ」
そうならそうと早く言ってくれれば、厳しい言い方をしなかったのにと、私は引っ越しそばを渡すような愛想笑いを浮かべて会釈し、再度、卵に向き直ります。
そして「純文学」の卵を手に取り、棚の端の方でコンコンと割り、両手できれいにかぱっと殻を開きます。
すると
ボンッ
と小さい爆発音のような音がしました。
それと同時に白い煙に包まれる店内・・・・・
しばらくして視界が晴れてくると、そこには立派な髭を蓄えた紳士が立っていました。
「吾輩は夏目漱石である」
なるほど、それはどこからどう見ても夏目漱石その人でした。
しかし私はがっくりと肩を落とします。
「こういうことではないんだよなあ」
そうなのです、私は作品が読みたいのであり、作者と直接話をしたいわけではないのです。
考えても見て下さい、もしドトールやベローチェで、私と漱石がコーヒーを飲んだとして、一体何の話をすればよいのでしょうか?
仕方がないので、今度は「ラノベ」の卵を割ります。
再び、白い煙に包まれる店内。
すると今度は、ピンクの髪をした、やたら目が大きい少女が
「お兄ちゃん」
と呼びかけてきました。
私は頭を抱えます。
そもそも私にはリアルで妹がいますし、今の私には活字が必要なのであり、萌え的要素をまるで必要としていないのです。
しかも考えて見て下さい。
駅前のロータリーを、私を先頭に、漱石、萌えピンクがドラクエのように歩いている様子を。
そのメンバーでは、何を倒すべきかという議論さえままならないに違いありません。
この時点で半ばあきらめていた私は、やけくそで最後の「漫画」の卵を地面に叩きつけました。
すると今度は白い煙は出てきませんでした。
しかし、かわりに世界が完全に白黒になってしまったのです。
そして店の外に出ようにも、良く分からない白いワクのような、ぶよぶよしたものに阻まれ外へ出れません。
私はまたしても
なぜだああああああああああああ
と叫びました。
私は読む立場を求めたのであり、読まれる立場を望んではいないのです。
これはいくら何でもあんまりな仕打ちです。
私が世界に何かしたのでしょうか?
激情に駆られた私は再度、店主に詰め寄ります。
「白黒の世界を元に戻し、私に文庫本を売りやがれ、この野郎!!」
「ほっほ。若いの。これを見なされ」
すると老人のしわがれた手には小さなサイコロが握られていました。
そのサイコロを渡される私。
私は、サイコロを渡された場合、いかなる場合でも振るようにしているため、苦々しい顔をこれみよがしにしながらもサイコロを振ります。
「5」
5の目が出ました。
「ほっほ。5かね」
そういうと老人は、奥のタンスの上から5番目の棚を開けます。
そしてそこから、A4サイズの紙を出し、裁判で「勝訴」と出すときみたいに、バッと目の前で広げました。
「振出しに戻る」
その文字を見た瞬間、ぐにゃぐにゃと歪む視界。
目の前の漱石が髭を残してドロドロに溶け、萌えピンクに関しては、大きい目だけを床に残して、あとは消えてなくなっています。
そしていきなり
シャアアアアアン
と言う爆音と共に、視界は完全に白い光に包まれます。
そこで私は意識を失いました。
しばらくして目を覚ますと、そこはベッドの上です、見渡すとよく知っている机と本棚があります。
そこは私の部屋でした。
時計を見ると
「7時40分」
今日、私が起きた時刻でした。
とりあえず私はまず顔をしっかり洗い、目やにを取り、トーストを焼き加減を確認しながら焼き、玄関で靴から石とトゲを取り家を出ました。
鞄には外出時に読むようの、夏目漱石の本と、友人から押し付けられたラノベが入っています。
道を歩きながら、唐突に私は理解しました。
「ああ、私は今2回目の人生に入ったんだな」
私があんなにも生きづらく不器用だったのも、私がまだ1回目の人生に留まっていたからに違いありません。
しかし私はサイコロを振り、2回目の人生に入りました。
少なくとも1回目よりは上手く生きれるはずです。
私は皆さんに聞きたいです。
「あなたは何回目の人生を生きてますか?」