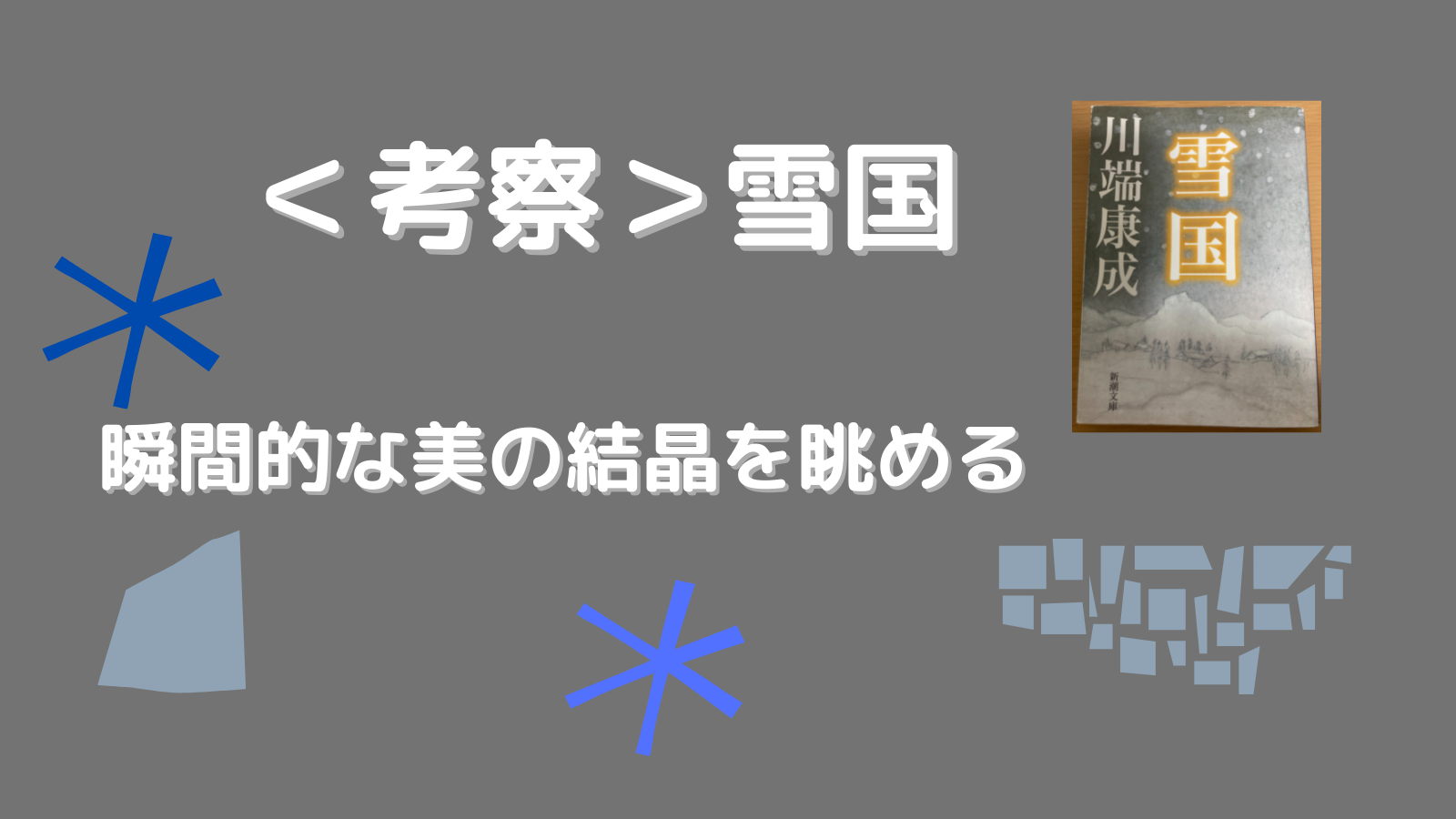「雪国」は川端康成さんの短編小説です。
妻子がありながら無為徒食の生活をしている島村が、ぶらりと立ち寄った雪ぶかい温泉町で出会った駒子との関係を描いていく、近代文学の不朽の名作です。
儚く美しい感覚をそのまま映像にしたような、言葉の流れが心にしみ込むような小説で、読み終わった後も、忘れえぬ印象を残します。
以下、物語の重要部分に触れるので、ネタバレが嫌な人はここまでにしてね
人物たち
まずは主要の人物を通して、物語に迫っていきたいと思います。
島村
この小説の主人公の島村は、退廃的な価値観で生活を送っています。
島村は時々、西洋舞踊に関する紹介や研究を書いたりもしています。
しかし西洋の舞踊を、よく見るわけでもなく、自分の空想で踊る幻影を鑑賞しているだけなのです。
彼自身は物語の中で
「自分の仕事により自分を冷笑することは、甘ったれた楽しみだが、そんなところから、哀れな夢幻の世界が生まれるかもしれない」
とも言っており、生ぬるい喜びの世界に浸っています。
そしてここからがさらに重要で、その退廃的価値観の根本にあるのが、美に対する意識であるということです。
島村は美に対する感覚に非常に鋭敏で、そしてその感覚に素直です。
この小説は、基本的に島村の視点で雪国の景色、人物の描写を眺めることになります。
夕景色と葉子の瞳が、窓に映り重なったときに、妖しく美しい夜光虫と表現したり、蛾の翅と、その向うに連なる国境の山々を対比して、翅の一点の薄緑は反って死のようであったと述懐したりと、このような表現が小説中のありとあらゆるところに出てきます。
美に素直で、それを第一に考えているからこそ、幻想世界で勝手に美を謳歌したり、妻子ある身ながら雪国の温泉宿で、女と会ったりするのです。
彼に道徳がないわけではありませんが、それよりも高い位置に美を置いているので、それが彼の生き方に反映されてるのだと思います。
駒子
そんな彼が温泉宿で、関係を持つのが芸者の駒子です。
駒子の置かれる環境は、毎年変わっていき、毎年転落していきます。
どこかで結婚して、清潔な身にしたいという考えもありながら、島村との、どうすることも出来ない関係をやめることが出来ません。
駒子は、儚いようでありながら、一方で非常にたくましくもあり、座敷を何件もまわって稼いだり、三味線でも力強い演奏を見せます。
師匠が駒子の許婚にしたがっていた、師匠の息子で、幼馴染でもある病の男の療養費を出していた、という健気なエピソードがあると思いきや、島村以外に5年続いている男が他にもいて、断ろうとしながらもずるずるしていたりもします。
その他にも、偶然見かけた島村の車に無鉄砲に飛び乗ったり、色々な顔を小説内で見せます。
活発で清濁併せのんで生きていくタイプに見えながらも、非常に繊細な女として描かれる彼女は、到来した個人主義の時代を、四苦八苦しながらも生きなくてはいけない、戦後の女性の象徴の面もある気がします。
葉子
涼しく刺すような美しさを持つ葉子の特徴は目で、そのすっとした、きらきらした目の美しさが島村を捕えます。
献身的に師匠の息子を看病していますが、師匠が生前、許婚にしたかったのは葉子ではなく、駒子という微妙な状態にあります。
弟を、声をはりあげて見送る健気さ、師匠の息子の死の際に、駒子を迎えに来るときの必死の言葉。
お風呂ではつい歌を歌ってしまう無邪気さなど。
葉子は、無垢や純粋さ、光の性質に包まれている印象を抱かせます。
葉子の無垢さ、純粋さは、戦前の理想の女子の象徴なのかなとも思いました。
徒労という美
この小説のキーワードの一つが徒労です。
島村は何度も小説中で、徒労と美を結び付ける発言をおこなっています。
駒子は感想などを書くわけでもなく、読んだ小説の題や、人物や関係だけを日記につけています。
島村は、それを頭から徒労と叩きつけることにより、彼女の存在を純粋に感じると表現しており、他にも様々な場面で、徒労に対する感覚が語られます。
いうなれば、妻子があるのに、雪国の温泉宿に駒子に会いに来るのも、抒情と徒労の産物です。
島村は、意味のあるものや、便利なもの、建設的なものに美を感じないという傾向があります。
逆に意味のない、自分の利益にはならない、瞬間的で吹けば消えてしまうものに美を感じるのです。
そのあらわれた瞬間を切り取り知覚することが彼の人生の目的なのではと思います。
そして美は消えるから美なのであり、それが継続し、何かの目的性や合理性を持つと、美ではなくなってしまう・・・
そんな感覚が島村に、徒労と美を結びつかせているのではと思います。
手に入らないという美
駒子のセリフで
「なんとなく好きで、そのときは好きだと言わなかった人の方がいつまでもなつかしく、忘れない」
という言葉があります。
自分も小さいころの経験で、両想いだったのにも関わらず、お互い言い出せずに別れた子の思い出は、心の奥のところでとても美しく残っており、駒子の言うこの感覚は非常に共感出来ます。
島村が温泉宿から帰る列車の中で、見た男女が、実は偶然乗り合わせただけの二人だと知って涙が出そうになる場面など、この小説内では、最終的に手に入らず、別れに至る美しさに対する表現が多く描かれます。
そもそも島村たちそのものが、細君がいる男と、年に1回会うだけの芸者の関係です。
つまりこの二人はお互い、完全には手が届かない前提で愛しあっているわけで、そしてこの手が届かないというところも含めて魅力的なのではと思います。
手に入れば、愛はそこで完結してしまいますが、手に入らない場合、自分の脳内で、それを美化し想像を続けます。
さらに年に一回しか会えないとなれば、その限定的な体験は美化されていきます。
この二人の愛は、手に入らないという要素を、想像力の媒介にして成立している面も大きいのではと思います。
死に向かう美
島村は、駒子が転落していく様子、それを自分にはどうにもできない状態なのも含めて、美しいと感じています。
さらに、蛾の翅に死を感じたり、昆虫どもの悶死するさまをつぶさに観察したりと、島村は死に対しても抒情を抱いているように見えるのです。
死んだら肉体が朽ちていって、最後には消えてなくなります。
主人公はこの死というものに対しても、根源的に美を感じているのではと思います。
結局は死に向かいながら、転落しながら生きていくという価値観は、徒労の概念にもつながります。
瞬間的で消えてしまう儚さという美、主人公は死をもそれと結びつけているのでは感じました。
美に対する姿勢
島村の美に対する姿勢は、美の瞬間を捉え、そしてそれに道徳的見地を持ち込まず、想像の余地を残す、というものではないかと思います。
彼は道徳や既成概念に縛られないからこそ、自分が感じる美をそのままに享受しているのです。
恋人が転落していく様をどこか美しいと感じても、理性や意識が働き、普通は自制します。
しかし彼はその感覚をそのまま美として眺めるのです。
駒子がいながらも葉子の美を排除しませんし、葉子の美の中に駒子を映したりもします。
そしてこの美に関して、主人公は徹底してるのが眺めるという態度です。
川端さんの他の作品にも見える傾向として、あげられるのが主人公と女性との距離感です。
女性に美しさを感じ、眺める。
この構図が川端作品の特徴としてあると思います。
そしてこの遠くから美を眺めるということは、自分の想像の余地を残すことになり、自分の中で美がさらに美化されます。
消えゆく瞬間の美を眺めることにより、さらに美化する・・・・・
この小説が提示する美は、そういう美なのかもしれません。
駒子と葉子
最後にこの二人の関係に触れておきます。
葉子の台詞で、駒子に対し「可哀想なんですから良くしてあげてください」という言葉と、「駒ちゃんは憎い」という両方の台詞が出てくるのが非常に印象的です。
人物の項目で、二人を戦後の、現実としての生活の姿と、戦前の理想の体現といいましたが、生活も理想もどちらかだけでは、息が詰まるのも道理で、どちらかだけでは生きていくのは苦しいでしょう。
駒子は葉子の、一途さや、健気さにどこか反発を感じながらも、あこがれも感じています。
また葉子は葉子で、色々な感情がありつつも、駒子の生き方に理解や共感もあるように感じます。
この二つの、憎しみと共感のはざまで、行きつ戻りつしている様子が、戦後日本の退廃と生きづらさをあらわしてるように思えます。
最後のシーンで、二階から落ちた葉子と、落ちた後の様子は、理想をもって一途に生きることがすでに困難になっている現状や、純粋さを保つことを許さない現代という時代を、劇的に表現しているのではと個人的に感じました。
さいごに
この小説は、景色や人の中にある美の映像を、流れる言葉により表現し、そしてそれにより自分の中に「感覚」や「情念」を植え付け、かつ呼び起こしてくれます。
今まで読んだ小説で、そんな風に感じることは中々なく、近代文学の不朽の名作と言われている理由が、読むと体感として実感出来ます。
間違いなく美の陶酔するような一形態がここにはあります。
日本が誇る美の結晶のような作品に感謝して、本考察を終えます。