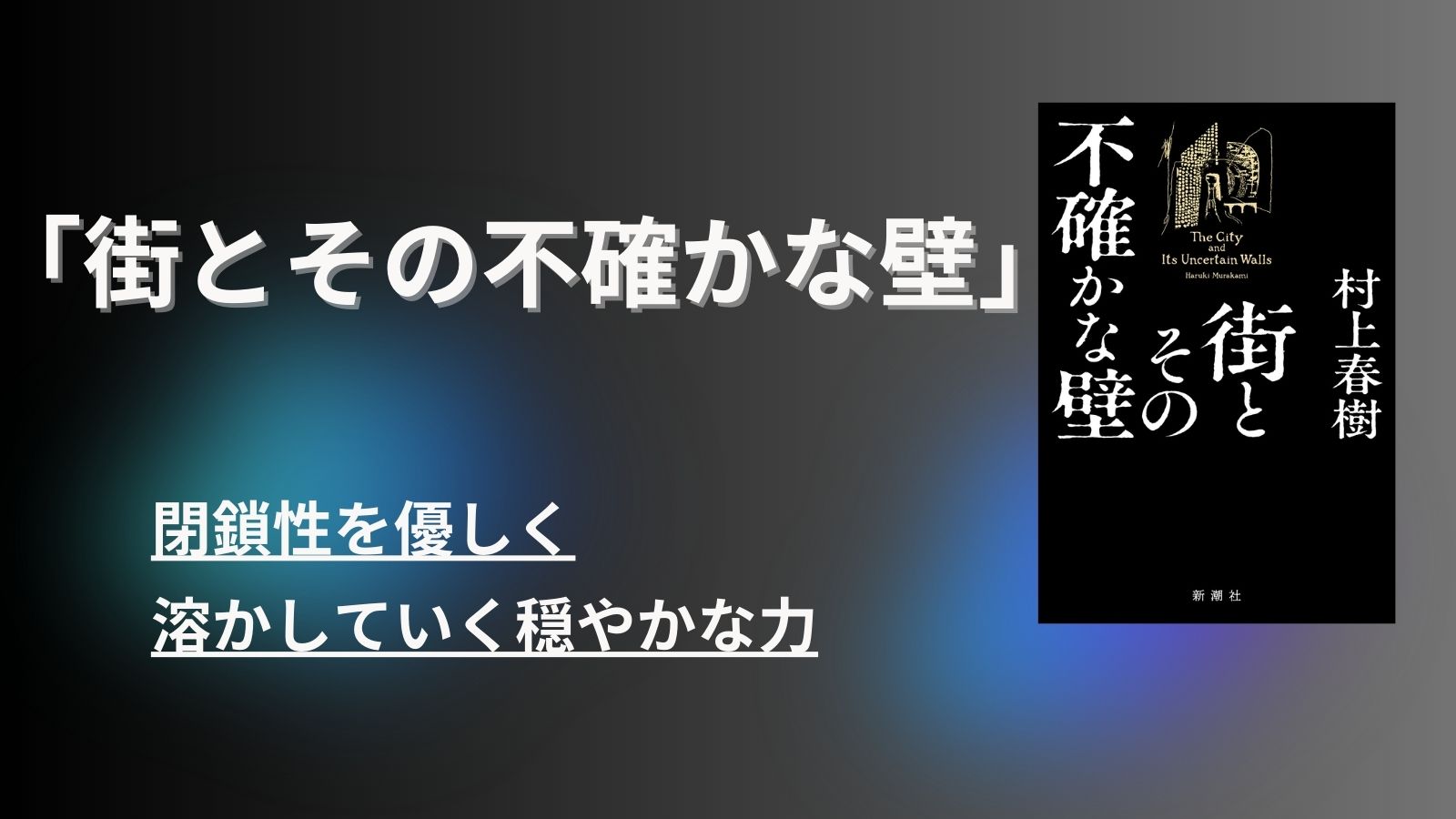「街とその不確かな壁」は村上春樹さんの、15作目の長編小説です。
本作は、かつて村上さんが、文芸誌に掲載した「街と、その不確かな壁」という作品を、大幅に加筆・修正し発表された作品です。
文芸誌に掲載された方の作品を改作したのが「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」という作品で、こちらは単行本にもなっている中期の名作。
しかし文芸誌版の方に納得がいかず、約3年をかけて完成させたのが今作「街とその不確かな壁」です。
ゆえに本作は「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」と、世界観・テーマを共有しています。
しかし、本作は言うなれば、「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」の、もう一つの可能性、さらに言えば、今の日本人が直面している現時代的な問題にとてもコミットした作品となっています。
コロナ過により、我々は何を失い、どういう風にそれを取り戻していくべきなのか、そのようなことも本作の重要なテーマの一つだと思います。
そして本作は、村上春樹さんが描いてきた、純粋な結晶のような宙空からの、ある種の着地地点を示した、そんな作品だとも思うのです。
それでは以下、考察に入ります。ネタバレが嫌な人はここでストップしてね。
なお本作の人物に関しては具体的な名前が分からない人が多く、呼び方も場所や場面により異なるため、主人公は「ぼく」ではなく「主人公」、街のことを話してくれた「きみ」は「少女」と以下では表記し、「イエロー・サブマリンの少年」と「コーヒーショップの彼女」はそのまま表記します。
本作をより楽しむ為の前提
村上さんの作品を読むにあたり、重要なのが集合的無意識という概念で、これは簡単に言うと、「人間の意識の奥には無意識の領域があり、そこでは全ての人間が繋がっている」というものです。
今回の、街に関しては、主人公と少女が<意識で築き上げた>ものですが、そのベース部分は<無意識の領域>で全ての人と繋がっています。
言い換えるなら、誰の心の奥にもある純粋な精神の領域が街であるということです。
ただしこれは緩やかな共有であり、人によってそれは街であったり森であったりホテルだったりするかもしません。
人によって見える景色は違えど、その領域自体は共有している、そんな風に私は捉えています。
本作の作品内において、マジックリアリズムという文学ジャンルの紹介がなされます。
マジックリアリズムとは、「現実と幻想が混ざり合っていて不可分である作風」のことをいいますが、村上作品に関しては、現実と心の中、無意識の領域が重なり、混ざり合っている感覚で読むと、作品に深く入り込めます。
簡単に言えば、頭をやわらかくして、これは何かを象徴しているのかも、と自由に考えて楽しみながら読むといいよ、ということです。
街と壁とは何か
本作における、「街」や「壁」。
これは一体何を表しているのでしょうか。
まず「街」ですが、これは主人公が少女と築き上げた空想上の場所です。
しかし想像した時点で、それは二人の意識の中で形になります。
村上作品は、現実世界と意識世界の輪郭を揺さぶり、その世界を行き来して物語が進むので、意識上にあるものは実際に存在すると考えると、より深く物語に入り込めます。
また本作で描かれる「街」はあくまで、少女ではなく、主人公の視点や意識が作り出した街であるということも重要です。
少女と話して出来上がった街とはいえ、そのディティールは少女の物とは違います。それぞれの意識には違いがあり、それぞれの街があるからです。
一方で「街」は集合的無意識が作った共有スペースでもあるので、少女の街、または他の人の街とも緩やかに繋がってもいるのだと思います。
本作は現代社会で何かに傷つき、また上手く適応出来なかったりするものたち、言わば「失われた人たちの物語」ですが、そういう人々の無意識が作りあげた共有のスペースが「街」であり「壁」なのです。
私のイメージは、共有スペースの基本的な形の上に、各々のアメーバ状の意識がそれぞれ染み出して、個人の街を形成しているという感じです。(あくまで私個人のイメージです)
なので本作の「街」に登場する、少女やイエロー・サブマリンの少年は、基本的には主人公の意識が生み出した存在であり、少女や少年自身にもそれぞれの「街」があり、そこに彼らの意識の中枢や本体はあるのではと考えています。
ただしそれらが完全に無関係ではなく、スペースを共有しているので、主人公の街にいる人物にも、意識の中枢や本体が滲み出し、何かしら影響し合っている、そのような状態だと思うのです。
ここからは街の様子から、主人公の意識が表象しているものを考えてみます。
街には、官舎地区など、階級により住む場所が分けられており、基本的に行き来もありません。
これは現代社会の格差システムを表現しているのではと、私は考えます。
さらに少女が貧しい方の地区にいるのも特徴です。もしかしたら現実世界で主人公は、少女との生活環境の差を無意識に感じていたのかもしれません。
また街は、獣たちなど色々な要素により、循環システムが働き、それ自体で存在し続けられるようになっています。
これは人間の肉体システムを象徴しており、さらに言えば血液の循環など肉体的なことだけではなく、嫌な事を忘れたり、自分の気持ちを整える為の脳内物質を出したり等の、精神を含めた人間システムとリンクしているのだと思います。
また「壁」に関して言えば、「街」が純粋な心の空間だとするならば、そこに入らせない為の心のバリケードだと捉えるのがいいと思います。
本作の中で実は「壁は存在しない」というセリフがありますが、自分を守る為に自分の意識が作り上げているのが壁なわけで、自分の問題がクリア出来れば壁は無くなる、そのことをこのセリフが現わしているのではと思うのです。
常に形を変え、隙間を埋めていくという描写も、自分の意識が心を防衛するために、色んな思想や考え方で盾を作っていくという風に捉えると分かりやすいと思います。
また、街の外へ出る唯一の場所と言われていた「溜まり」とその地下が暗く、そこにいる魚が目を持たないことも印象的です。
これは、自分が作り上げた意識の街を、自らの力で出る為には、自身の暗い無意識と向き合わなければならないという象徴だと思います。(無意識は深く潜っており、それは目で感じるものではない、だから目が無い)
ただ本作は、街から出る方法について、もう一つの可能性について言及しており、それこそが本作のメインテーマでありメッセージなのだと私は思います。
それについては後述の項目で詳しく述べます。
主人公と少女
本作が今までの村上さんの作品と異なるのは、物語の重心です。
主人公と少女の純粋な原初体験ではなく、その後の子易さんやイエロー・サブマリンの少年、コーヒーショップの彼女の方の物語、つまりはその後の物語の方に比重が置かれているように私は感じました。
前半部で、主人公と少女との美しい情景は描写され、それがかけがえのないものであること。そして少女の抱える事情については描かれますが、少女がなぜ消えたのかという事に関しては分かりませんし、本作はそこが重要なのではありません。
少女が語る、家族との関係が上手くいっていないこと、信頼出来るのは祖母だけであること、三十分くらい歩き続けた後、急に泣き続けたりする描写からは、精神に混乱と不安、満たされないものを抱えているのが分かります。
また彼女が語る、「心と身体が離れている」 「いろんなことにたくさん時間がかかる」と言った言葉は、今後出てくる人物の心情やテーマと非常にリンクしているので、非常に重要な存在ではあります。
個人的にまとめるなら、少女の主な役割は「純粋体験」であり、それは重要であるわけですが、本作はそれが失われた後の心の持って行き方に比重が置かれているということです。
その純粋な体験が物語の基盤を作っており、本作はその基盤を踏まえつつ、その後の可能性を優しく指し示すものだと私は考えます。
子易さんと奥さん
主人公が、新しく働くことになる図書館の館長である子易さん。
造り酒屋の息子で、元小説家志望の彼は、フランスのベレー帽・スカート姿という、かなり個性的な見た目ですが、とても穏やかで優しい人物で、本作におけるメンターみたいな役割を担っています。
村上作品においては、過去に巨大な喪失を経験し、現在を死んだように生きる「失われた人」という存在が、長編作品にかなり登場します(海辺のカフカのナカタさんや佐伯さん等)
子易さんも、奥さんや息子の死により喪失や虚無を抱えて生きてきた一人です。
子易さんは元大使館職員の奥さんと二人、幸せに暮らしていたわけですが、ある時奥さんが目を離した時に、自転車に乗った息子が交通事故に合い、亡くなってしまいます。
自分のアレルギーのせいで犬を飼えず自転車に変更になったこと、たまたま食塩を切らしそれに気をとられていたことなど、様々な事柄を結び付け、奥さんは自分を責めます。
そして激しい雨が降ったある日、川から身を投げ、自ら命を絶ってしまうのです。
このことが子易さんのその後の人生を決定付けます。
この奥さんの事件には、震災の象徴が含まれています。子易さんが住んでいるのは福島県であり、そして避けようがない運命は、ある時突然訪れるという村上さんの思う摂理が、ここに込められているように思います。
その意味で、子供の自転車事故もまた理不尽な運命の悪戯です。
子易さんの奥さんの心情については、主人公からみた少女の構図と基本的に同じで、果たしてどういう気持ちを抱えていたのかというのは分かりません。
だからこそ、子易さんも主人公も、喪失に苦しみ、穴が塞がれないまま現在を漂うことになるわけであり、そしてそこの苦しみと救いを描くのが村上さんの作品の特徴です。
その意味で子易さんは、圧倒的な理不尽により家族を奪われた者が、その後どう生き、その心がどうなったかを表現し、未来の可能性を示してくれる存在でもあります。
ここで奥さんが布団に二本のねぎを残した理由についての推察を書いておきます。
ねぎは古名で「ひともじぐさ」とも言われ、枝分かれした状態が人の形に似ているからそう呼ばれていたとのこと。
また神社の役職の一つである「禰宜」の語源は、「ねぐ」であり、その意味は「神の心を和ませてその加護を願う」というものだそうです。
この二点から私は、二本のねぎは、残された子易さんに対する、奥さんなりの感謝や鎮魂の儀式だったのではないかと考えています。
さてそれでは子易さんの話に戻ります。
奥さんが死んだ後、子易さんは虚無を抱え現実を生きましたが、重要なのは主人公が子易さんにあった時は既に死んだ後だったということです。
半地下の薪ストーブの部屋は、主人公の意識と子易さんの意識、または現象界や心霊界、無意識の世界とが溶けあっている霊的な場所であり、そこで子易さんは、主人公に対し数々のアドバイスをしてくれます。
後の項目で詳しく後述しますが、本作は三世代に渡る物語です。
失われたまま生きる主人公と、似た精神を抱えている先輩、つまり主人公から見た上の世代が子易さんです。
子易さんは、主人公の下の世代であるイエロー・サブマリンの少年にも、優しい態度で接しており、本作における子易さんという存在はとても大きいものです。
フランスのベレー帽や、スカートに関しては、色んな解釈が可能だと思いますが、奥さんの気持ちや、女性の気持ちに少しでも近づくための格好と捉えることも出来ます。
結婚前の奥さんはフランスの大使館の勤務だったのかもしれません。そこから連想すると、フランス文学は、女性の内面や性欲、葛藤を描くタイプの小説も多いです。
またスカートを履くことによって、形式的な装いから女性の心に近付こうとしたのかもしれません。
また添田さんが言う、「亡くなってからの方が人間的に生き生きしていた」「それまで内側に大事に隠されていたものが、亡くなられたことによって、外に現れてきた」という表現も本作の重要なポイントです。
肉体という世俗的な器から離れ、純粋な精神存在になることにより、子易さんの魂は活力を取り戻した。そう考えると、死は悪いことばかりでもない気がします。
死んだ子易さんは安らぎの感触を得て、そしてその霊が、主人公にアドバイスを与える。
これこそ先人から脈々と受け継がれてきた人類のサイクルで、その意味で肉体の死は、終わりではないのかもしれません。
子易さんの死後の魂については、後の項目で詳しく書きます。
コーヒーショップの彼女
主人公が図書館の館長として赴任した地で、コーヒーショップを営む三十代の女性。
私は本作において、そして村上さんの作品にとって非常に重要な、着地の象徴としての存在が彼女だと思います。
ニ年前に離婚し、札幌から福島にきて、心機一転、コーヒーショップを始めた彼女。
離婚の理由は他にも事情があるとは思いますが、性行為に対して上手く臨めないことが主な理由だと彼女自身は思っています。
ここにかつて少女が言った「心と身体が離れている」という言葉が重なります。事情は違えど、何かしらの欠損的な感情を抱えている二人は、同じ精神を持った重なりあった象徴でもあるのです。
ただしコーヒーショップの彼女は既に三十代であり色々な経験を重ねています。その分お互いを思いやったり、上手く距離やバランスを取ったりと、精神的に余裕を持った行動を取れるようになっています。
その点は四十五歳を超えた主人公も同じであり、お互いが相手に寄り添い、待つという事が出来るようになっているのです。
主人公はコーヒーショップの彼女に対する気持ちを
「穏当で柔らかな衣に包まれ、それなりの智恵と経験によって抑制されたもの」
「より長い時間性の中で把握されるべきもの」
と表現しています。
また自身が求めている彼女の気持ちに関しては、彼女の全てではなく、心の中の「穏やかなぬくもり」や「心臓の確かな鼓動」だと表現しており、この「穏やか」で「確かな」ものこそが本作において主人公の本体が現実世界へ戻ってくることの手助けをします。
耳のメタファーについては、後の項目で詳しく述べますが、「彼女が耳をさわると痛みが取れる」ということは、感覚を研ぎ澄まし、意識や無意識の世界を感じ取る器官を、現実のぬくもりで癒してくれる存在、そういう意味合いが込められているように思います。
本作の中で、主人公の本体が街から外へ飛び下り、現実に戻る時に重要な心構えについて
「誰かが地面で受け止めてくれることを心の底から信じる事」
と表現されますが、私はこの存在こそがコーヒーの彼女なのだと思います。
そしてそれは受け入れてもらうだけの一方通行なものではなく、コーヒーの彼女を待ち、受け取める存在もまた主人公であり、お互いがお互いと結び付け合っています。
心と体が離れていたり、耳を癒してくれるという共通項はありながらも、少女は過去の純粋体験の象徴であり、コーヒーショップの彼女は、現実に根付いた確かなぬくもりを象徴しており、ここが二人の大きな違いです。
彼女には、現代の女性や人々が抱える苦しみもまた象徴されています。
作中で彼女が着けている下着について「特別に身体を締め付けており、仮説的なものごとから護っている」と表現されます。
私はコロナは、我々のコミュニケーションに大きな深い傷を与えたと思っています。
マスクをし、口元を隠し、かつ人との距離を取る、それ以前から分断が叫ばれて久しかったのに、ここに来て、無意識に人と人との距離が強烈に植え付けられてしまいました。
ウィルス性の病気という事もあり仕方がないですが、その為に過度に衛生面に気を配り、それが強迫概念にまで発展する人も少なくないのではないかと思います。
元々、若い子の中には潔癖的で衛生観念が強い子が多く、コロナの前でも唾液の交換など、性的な行為や肉体関係に抵抗感がある人も多かった印象があります。
おそらくコロナ後に、性行為に対するアレルギー的な感覚を持つ人はかなり増えているのではないか、そんなことを思います。
また、例え衛生面で影響を受けていなくても、人との距離やマスクというのは、心の距離にも決定的に影響すると思います。
コロナ禍に青春時代を送った人は、コミュニケーションの取り方が苦手になることもあると思いますし、それ以外の人々もまた、以前とは違う閉鎖的なコミュニケーションの方向へ無意識のうちに誘導されてしまう気がします。
また「仮説的なものごと」という言葉には、コロナ禍でも色々言われた根拠のないデマや陰謀論など、地に足が付かない不確かな風評というネガティブな意味、さらにそれより大きな意味として、コミュニケーションを含む全ての未来の出来事は、確かなものなど何もなく、仮説的なものである、そのような意味が込められているように思います。
陰謀論は勘弁ですが、コミュニケーションの全てを怖がっていると、未知の出来事や、他者の全てを怖がることになり、かなり狭い世界で生きていくことになってしまいます。
その意味で彼女の下着は、コロナにおける排他性の病をも象徴しているのです。
しかし、本作の希望は、そんな苦しみを抱えた彼女を、穏やかに静かに待つ主人公がおり、そしてその主人公を彼女が救うというところです。
つまり本作は、閉鎖的になっている心を穏やかな想像力により解き放っていく、可能性の物語なのです。
イエロー・サブマリンの少年とその家族
主人公が赴任した図書館で出会う、イエロー・サブマリンのTシャツを着ている少年。
本を猛スピードで脳内に吸収し、かつ生年月日からその人が何曜日に生まれたかを瞬時に計算できる能力は驚異的です。
しかしコミュニケーションが得意ではなく、その能力の特異さもあり、社会に上手く溶け込めません。
この少年も本作において最重要な人物の一人で、様々な象徴を帯びています。
まずその情報吸収力や計算能力は、非常にグーグル的でありかつAI的です。ここにはスマホや検索エンジンが生まれながらにある世代の象徴が込められているのではと思います。
ただし逆説的に言えば、少年の能力はスマホさえあれば現代において必要とされない能力でもあります。
昔であればその驚異的な能力は、神秘的なスピリチュアル的なものとして、価値のあるものとして捉えられていたかもしれません。
しかし科学テクノロジーやGAFA的なものが覇権を握っている現代において、スピリチュアル的なものは軽視されがちな時代になっています。
村上さんが二十代や三十代の頃は丁度、東洋思想やスピリチュアルが注目された時代でした。
その時代はヒッピームーブメントやビートルズ、ウッドストックなどのカウンタ―カルチャーの全盛期でもあり、少年のイエロー・サブマリンのTシャツの柄は、この時代の文化を象徴しています。
後の項目で、本作は三世代に渡る物語だと言うことを書きますが、本作の少年は、現代を生きる若者の象徴であると同時に、作者自身の若者時代の象徴でもあるのだと思います。
少年は現代社会を、とても生きづらいと感じながら、何とかやり過ごしています。それは現代の若者も同じであり、かつ昔の作者の気持ちもそこに乗っているのです。
そんな少年の生きづらさを助長しているのが家族の問題です。
父親は世間体を気にし、兄と弟も基本的に少年に無関心。
母親だけは少年を愛していますが、それは少年の本質部分を認め理解するというものではなく、単純に母親の本能として自分基準の愛を当てはめているだけです。
少年はよく図書館にいる、母猫と子猫たちを眺めていますが、子猫全てを図書館で飼うのが不可能な為、里親の元に子猫たちは連れていかれ、母猫は一人になります。
母猫はしばらくは子猫たちを探すものの、しばらくすると元の生活サイクルに戻る。
ここの猫の描写において私は、本能的な繋がりしかない親子が象徴されていると思いました。
その意味で少年にとって情愛で繋がる家族は存在しないのです。
物語後半で、小屋に木彫りの人形を残して、少年は街へ旅立ちます。
その行為には「自分が木の人形だったとしても家族にとって大して変わらない」という皮肉な思いが込められているのかもしれません。
また視点を少し変えてみると、少年は、自ら地図を書くほどの熱意で、主人公から聞いた「街」を目指すわけですが、主人公が村上さんの体重が一番乗っている存在だと考えると、その主人公が作り出した「街」は、村上さんの文学作品の精神性の象徴として捉えることも出来ます。
そう考えた時に少年は、村上さんの作品を読む若い世代の読者の象徴と捉える事も出来るかもしれません。
古い夢、夢読みとは何か
本作において主人公や少年が街で従事する「夢読み」とは何なのでしょうか。
そもそも夢読みが読む「古い夢」とは一体何なのか。
本書の中で夢は、人の心の残滓や残響と表現されており、卵型の形であることも踏まえて考えると、その人間が生きていた時の、根源的で純粋な思いの結晶が形になったものが、古い夢なのではと私は思います。
「古い」という言葉については、もちろん過去の人間の夢だからというのもありますが、現代を生きていく上で忘れ去られた精神性という意味も込められていると思うのです。
その「古い夢」を読むのが、夢読みの仕事であり、そこには少女との純粋な記憶に捉われている主人公がノスタルジーに浸りたいという後ろ向きな点もあるとは思います。
しかしそこには、過去の人間が残した精神の中にこそ重要な何かがあるという、人文的なメッセージもまた込められているようにも思います。
もう少し広い視点で見るなら、主人公が作った街そのものも、誰かにとっては古い夢の一つかもしれません。
また古い夢にはそれ以外にも象徴しているものがあると私は思います。
それは過去の文豪が残した作品達です。
それこそは作家が魂を削り純粋な思いを伝えようとした結晶たちであり。その意味で古い夢とは、過去の作家たちの作品やその魂が象徴されているとも思うのです。
その意味で言うなら、夢読みという行為は、過去の作家たちの作品を読み、その魂へと近付く行為といえるかもしれません。
少年が夢読みを天職だと言うのも、現実世界の読書の、深いレベルでの延長だとも捉えられます。
ただし、街や夢読みという行為には、「閉鎖性」という特徴も込められています。
目を傷つけなくては夢読みになれないという描写も、現実世界から目をそらしている象徴にも取れますし、街での夢読みは、自分の世界に閉じこもり、純粋な思い出や過去の作家の作品をひたすら読んだりすると言う様な、ある種の閉鎖的・引きこもり的要素も連想されます。
主人公は、その閉鎖性から最終的に抜け出るわけですが、少年は街の中で夢読みを続けます。
現実への着地こそが本作の重要なメッセージですが、一方で村上さん自身は、純粋な思いに浸ること、引きこもることを否定しているわけではありません。
かつて主人公が街で暮したように、今の少年にとって街は必要なのです。つまり人間には純粋に何かをに思いを馳せたり、感じる期間もまた必要であると言っているのです。
主人公は確かに最後、現実へ着地しましたが、それは四十五歳を超えてのことです。
少年は、主人公と夢読みを一緒に行うことにより、共感や想像力など様々なことを学んでいます。
少年は自分で「受け止めてくれる存在が生きている人たちのあいだには一人もいない」と言っていますが、主人公にコーヒーの女性が現れたのも最近の事ですし、少年にもそういう出会いがどこかできっとあると思うのです。
少年自身が<生きている人たちのあいだには>と留保しているところに注目するなら、受け止めてくれる存在が、死者や書物の言葉の中にいる可能性、現れる可能性もあり、そしてそれでも全然良いと思います。
その意味で夢読みとは、ゆっくりと何かを考える時間、過去の作家の魂に触れる時間、一種の逃避の時間等、様々な要素が込められているのだと思います。
本作は、街や夢読みからの開放の話でもありますが、街や夢読みに対する繊細な感性を尊ぶ視線も失っていないのです。
添田さんとは
新しく赴任した図書館で、子易さんとコミュニケ―ションを取りつつ、図書館を実質的に切り盛りしている添田さん。彼女は一体何を象徴しているのでしょうか。
図書館の中心軸でありながら、別の地域の出身で主人公と同じよそ者。
本作は子易さん、主人公、少年の三世代の精神を描いた物語ですが、そのどこにも年代ごとの村上さん自身が乗っかっています。
子易さんはその意味で、今の村上さんの実年齢に一番近く、現実の村上さんを一番象徴している存在ともいえます。
すると子易さんの図書館というのは、村上さんが愛した作家たちの作品群や、自身の過去作の象徴、もっと言えば、読書や本を書くことそのものの象徴ともいえるかもしれません。
その観点から図書館の中心軸である添田さんについて考えた場合、彼女は「文体」の象徴なのかもと私は思うのです。
小説を書く時、自分の思いを表現する時に使うのが「言葉」であり、その言葉を組み合わせて世界観を支えるのが「文体」です。
その意味で、「言葉」という誰にでも分かる材料を使い、自分の心を外へ伝える軸になる「文体」は重要ですが、外へ表現する為のツールであるため、自分の内部からすると、ある意味でよそ者と捉えることも出来ます。
そう思うと本を書いたり等の創作行為自体が、閉鎖性の中から生まれた物を、皆で共有できる言葉により、開放していくという流れの中にあり、本作の物語の流れと共通しているなあと思います。
添田さんの漢字である「添」と「田」。私はその二つの文字から、田んぼを寄り添うように支える水をイメージしました。
田んぼという土地だけでは、お米は育ちません。稲と土の間を流れる水の支えがあってこそ、お米は育つのです。
その意味で、添田さんは、文体であり、水の流れであり、そういうスムーズに支えてくれるものの象徴だと私は思うのです。
三つの世代
本作は、共通の精神性を抱えた三世代の人間を描いた物語です。
世代で言うならば、子易さんが団塊世代、主人公が団塊ジュニアからバブル世代、そして少年はZ世代です。
もちろん社会状況は人間の精神に重大に影響を及ぼしますが、本作の世代とは上記の社会学的区分けとは少し異なり、それよりも実年齢による精神の変化や差の方に重点が置かれている様に思います。
少年のグーグルやAI的な能力など、もちろん時代性の反映もありますが、それよりも思春期、青年期、老年期と言うような大枠での世代の違いに意味があると思うのです。
さらに言うと本作の三世代の人物は、その年齢当時の村上さんの感覚が反映されているように思います。言うなればこの三名それぞれが村上さん自身の分身であるように思うのです。
それと同時にこの三名は、本作品を読む、それぞれの年代の読者の象徴でもあります。
ここに上げた三人は、心のどこかに穴や欠損を抱え何とか生きているわけですが、それは私たちも同じです。
本作は、繊細で優しいからこそ、何かに不安を抱えたり、生きているのが大変な人に対する物語なのです。おそらく村上作品が大好きな人にはそういう人が多いのではないかと思います。
本作で子易さんは、主人公を導き、少年にも優しく接しています。主人公も、少年が四角い部屋に来た時、乱暴な食べ方をする少年を寛容な気持ちで見守ります。
こういう細かい描写にも、上の世代の下の世代への接し方という一つの、寛容さという回答が示されてもいます。
またこれは単純に上の世代が下の世代に与えるというわけでなく、下の世代から教えてもらうことも沢山あるわけです。
子易さんは、自分の図書館を正しく受け入れてくれる素養を持つ主人公がいるから、現実から去ることが出来たし、主人公が街を出ることが出来たのも、少年が夢読みを継ぎ、かつ主人公が街を出るアドバイスをしてくれたからです。
前項の項目で、図書館や夢読みが、過去の文豪作品や村上作品の象徴でもあると書きましたが、これを世代の話に照らし合わせると、読者が作者の気持ちを受け取り、次の世代へ向け、今度は自分が本を書いていく、というような連鎖のようにも捉えられます。
また必ずしも作家である必要もなく、読者が作家の思いを感じ取り、下の世代に思いを伝えていくという連鎖として考えてもいいと思います。
そして作者から読者も一方通行ではなく、読者の感想や反応が作家の人生に大きな影響を及ぼすこともあります。
本作の主人公は最終的に街を出るわけですが、前の世代の子易さんは生きてる間は、ずっとある種の欠損を抱えていました。しかし生きている時に色んな人に優しさを与え、死後の世界では温かい魂の感触を得ることが出来たのです。
少年は街に入り夢読みを続けますが、その中でも成長を続けており、いつか街から出る日がくると私は思っています。
主人公が現実に戻る為に、子易さんと少年が協力し、その少年に街と夢読みという一つの可能性を主人公は提示する。そして子易さんが大事にしている図書館を主人公が継ぐ。
その意味で本作は、繊細で純粋で少し閉鎖的な先輩と後輩たちの、優しい交流の物語なのです。
もう一つ先の思い
本作の設定は「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」と共有しています。
しかし結末や、物語の流れに関していえば、方向性がかなり異なり、本作は失われた人のその後を描く物語で、そこにこそ本作の革新性があります。
それを体現している一人が子易さんです。
子易さんは生前、奥さんと子供の事件のことを忘れられず、欠損を抱えたまま生を終えました。
しかし生が終わった死後に、子易さんは、様々な人物にとって重要な精神を提示してくれます。以下の主人公に対して言った言葉こそ、本作における救いの核心を突いたものです。
「孤独は辛いが、かつて誰かを本気で愛していたという、強い鮮やかな記憶や温かみがあるのとないのとでは、死後の魂のありかたに大きな違いが出てくる」
つまり子易さんは、愛という思いを失わずにいれば、生を終えた後にでも救われる可能性に言及しているわけであり、これこそ失われたまま生きた人生に対する、救いの回答の一つだと思います。
さらに言うなら、この言葉は、「死」という存在を切り離さずに、どこか生の延長線上として捉えてもいます。ここにも一つの救いがあります。
子易さんは、この言葉の前に「遺骨は骨に過ぎず、ひとりぼっちな状態は全く変わっておらず、肉体を失った魂はいつか無に帰す」と言っており、これをそのまま受け取ると非常に虚無的です。
しかし、このセリフの後半部で「無は永遠というような表現を超越したもの」と表現しています。これは独特な表現です。
これは完全に私見ですが、この「無」というのは虚無的で冷たいものではなく、「全てが一」で、「一が全て」でその全てが優しく緩やかに繋がっている、根源的な流れのようなものではないかと思うのです。
現世から消えた後、子易さんの魂は、この緩やかな流れの中に還元されたのではないか、そんなことを思います。
本作において、愛という意識さえあれば救われない魂は存在しないのではないかという可能性を子易さんは穏やかに提示してくれました。
そして主人公とコーヒーショップの彼女との出会いも、本作における穏やかな祝福の要素の一つです。
彼女との時間は「時間にも手出しできない領域」「穏やかなぬくもり」などの言葉で表現されます。
かつての主人公と少女が作り上げた街にも時計の針は無く、時間にも手出しできない一形態ではありますが、コーヒーショップの彼女との時間とは、その意味が決定的に違います。
純粋性ゆえにそこへの固執から時が止まったのと、誰かへの穏やかな愛情ゆえに時間の影響を受けないのとでは、方向性がまるで違うのです。
少女との思い出が、煌めくような胸を突き刺すような思い出だとしたら、コーヒーショップの彼女との時間は、優しく包み込むような穏やかなものです。
「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」や初期の村上作品は、純粋な思いへの憧憬や、虚無に対する重心が強く、それも魅力的でしたが、本作ではそちらよりも穏やかで確かな現存するぬくもりの方に重点を置いているのです。
本作で街から出る時の重要な要素として「誰かが地面で受け止めてくれることを心の底から信じる事」という要素があげられますが、これも本作の最重要メッセージの一つです。
失われたまま年齢を重ね四十五歳を超えた時に、受け止めてくれる存在と出会った主人公。ここにも失われた人生に対する一つの回答があります。
つまり生きていれば、どこかでそういう存在に出会うこともあり、人生とは本当に何が起こるのか予測出来ないという事です。その瞬間にいくら「自分は失われた」と感じていても、未知の人生はこれからも続き、いくらでも状況は変わっていくのです。
本作はその意味で、失われた人々のその後の魂の幸福への道のりを描いたものであり、それは未知である人生そのものに対する祝福でもあります。
少年に関しては、今は「受け止めてくれる人」が居ないわけですが、街の中で共感性を獲得し成長していっていますし、いつか受け止めてくれる存在が現れると私は思っています。
その意味で、喪失と虚無の向こう側にある、可能性と祝福を書いたことに本作の重要な意味があると私は思うのです。
混じりけのない純粋体験の功罪
本作の軸となる「街」、それは主人公と少女の純粋な思い出が作り出した存在です。
本作でその純粋な体験について
「混じりけのない純粋な愛を味わったものは、心の一部が熱く照射され、ある意味焼け切れてしまう」
と表現していますが、この言葉は、純粋でありながら非常に劇的で、ある種、毒にもなるような体験であることが描かれています。
本作では、子易さんの奥さんや子供の事件。
そして過去の作品で言うと「海辺のカフカ」のナカタさんの山での体験、佐伯さんの恋人との思い出なども、混じりけのない純粋体験です。
上記に上げた全ての人が、その体験の強烈さや未練から、その後の人生を喪失感を抱えながら生きていくことになります。
強烈で鮮明なある種の体験や愛は、素晴らしいもののように思えますが、その光が強い分、反動も大きいのも事実です。
さらにいうと村上作品における、強烈な体験を経験している人の特徴としては、自分を取り巻く社会環境や精神のバランスを欠いている人が多いのではと言うのが私の考察です。
家族との関係が上手くいかず歪んでいたり、戦争の様な異常な体験などで、自分の精神が過度な負担を感じていると、感覚の感度が異常に鋭くなってしまうのではと思うのです。
「ねじまき鳥クロニクル」では、戦争中に井戸で見た光により心が焼き切れるエピソードが出てきます。
これは戦争という異常な状況が、精神のバランスを著しく傾かせ、その中でありえないくらい美しい光を自分が強烈に体験してしまった(自分のレンズの解像度が何十倍にも上がっていたのだと思う)ということだと思います。
その意味で強烈で純粋な経験には功罪があり、自分の精神状況に左右される上、その圧倒的な印象が、いい意味でも悪い意味でもその後の人生を左右してしまうものだと思うのです。
本作で、それと対置されるのが、コーヒーショップの彼女の穏やかな愛です。
その意味で本作は、初期村上作品の純粋体験とそれにまつわる憧憬という重心が、温かく穏やかな愛への視点に大きく変わっているのです。
純粋体験の様な強烈な体験と喪失も、その後の人生において癒すことが出来る。
ここに本作の重要なメッセージがあると思います。
本体と影の変更点
本作と「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」において、影という存在の解釈に変化があります。
影は影として描かれていたものが、本作では「本体と影は表裏一体」「時に入れ替わる」「それぞれが大事な分身」などと表現されており、影に対する考え方がかなり柔軟になっています。
これは本作が失われた人のその後の人生や希望を描いていることに大きく関わっています。
本作において厳密に言うと、図書館に赴任したり、コーヒーショップの女性と会ったりしているのは、街から抜け出した影の方ですが、いくら自分自身が「自分は影だ」と認識していたところで、実際に図書館で子易さんと会い心を動かされたり、コーヒーショップの女性に確かなぬくもりを感じている経験は、街という意識の枠に覆われた本体と連動しています。
こうなってくると、もはやどっちが本体なのか分かりません。
つまり本作では、自分の認識や意識、心の動きにより、表と裏は入れ替わり、本体にも影にもなりえるし、そのどちらも重要だと言っているのです。
かつての作品で、本体が純粋な場所に残り、これからの現実をずっと影として生きる失った人を描いていたのと変わり、本作では失われた人も、そのままでいるとは限らず、穏やかなぬくもりを得て復活出来る可能性を示唆しています。
つまり本作の、影と本体の描写は、断絶性・喪失性から大きく一歩を踏み出していると言えるのだと思うのです。
コロナと閉鎖化するコミュニケーション
本作のテーマにおいて大きな位置を占めるのがコミュニケーションの問題です。
それは現代の日本の問題の本質であり、本作のあらゆる場面で日本社会が直面しているコロナ禍の後遺症が象徴として表現されています。
本作の「街」は、欠損を抱えた失われた人の意識や無意識の中の場所であり、前提として閉鎖性を抱えています。
街に関して、本編中で「疫病を防ぐため」とか「終わらない疫病」と直接的にコロナ禍を示唆するような表現もあり、より深いレベルで現代の問題とリンクさせた象徴として、街という概念が組み立てられています。
コーヒーの彼女の項目でも書きましたが、彼女の特別な下着の表現は、コミュニケーションという、未知で予想出来ないものを過度に排除するという病理を象徴しています。
コロナ禍では、病の性質上、衛生観念を社会的に引き上げて対応し、人と物理的に距離を取ることを推奨しました。
ただでさえ若い世代には、綺麗好きで潔癖な子が多いわけで、コーヒーの彼女の様に、性行為に対して上手く臨めない人、心と身体が上手くバランスが取れない人は、今後増えていくのだろうと思います。
本作の母と子猫たちが強制的に切り離されるのも、強制的に距離を取らされ、奪われるコミュニケーションというコロナ禍の問題が象徴されている様にも見えます。
本作の主人公やイエロー・サブマリンの少年、コーヒーの少女など、繊細な感性を持っている人、また厳しい家庭状況に生まれたり、何か辛い事件があった人というのは、自分の中の世界へと閉じこもりがちになったり、過度な他人への警戒感を持っていたりなど、元々コミュニケーションに問題を抱えています。
しかしコロナ禍はその閉鎖性を生物学的なレベルで加速度的に強化してしまったように思うのです。
ゆえにこれからの私たちは、無意識に刻まれた人と人との距離や閉鎖性と戦っていかなくてはいけないわけで、その意味で本作が2023年に出た意味はとても大きいと思います。
主人公はコーヒーの彼女が、受容的になるものを待ちたいと言い、一方でその彼女の力により、主人公の心も動かされ、本体は街から抜け出すことが出来ました。
このお互いの状況や気持ちを尊重し、優しい想像力を媒介したコミュニケーションこそが、閉鎖性を打破する力になる。
そしてその流れの実現は、ゆっくりでよく、あせらなくていい。
本作は上記のメッセージを、穏やかに語り聞かせてくれる、優しい物語なのです。
本作のそんな態度と精神性こそが、コロナで傷を負ったコミュニケーションを復活させる鍵になる、私はそんな風に思います。
耳の使い方、心のあり方
村上作品における「耳」の描写。
デビュー作の「風の歌を聴け」から、既に「聴く」という感受性に対する作者の思いがあり、「羊をめぐる冒険」でも耳が大きい女の子が出てきたり、「海辺のカフカ」でも聴くことの重要さが強調されています。
言うまでもなく耳というのは音を聴く器官です。そして音というのは自然のリズムや動きの現れです。
現代社会は自然にしろ都会にしろ様々な音で溢れていますが、我々は視覚的情報の方に重点を置き、聴覚の方を蔑ろにしています。
そんな目の前に広がる雑多な風景に惑わされずに、じっくりと立ち止まり耳を澄ます事、そこから何かを感じ取る繊細な感性がとても重要であることを村上作品は、一貫して伝えているわけです。
その意味で、本作の街での夢読みもまた、じっくり耳を澄ます行為に非常に近いと言えます。
耳を澄ませば、色々な情報が入ってきます。そして情報が増えることは、考える材料が増えることです。
さらに耳を澄まさないと聴こえない様なささやかな音を聴くことは、優しい感性、弱いものに寄り添う感性を養うことにも繋がります。
言うなれば村上作品の本質は、感覚を優しく研ぎ澄ますことにより、色んな事を考えていく想像力の重要さを伝えることにあると思うのです。
本作でも、あらゆる場面で耳が出てきます。
少年の影である木彫りの人形が、主人公の耳を噛むことにより街への道が開かれるのも、少年が必死で主人公に対しコミュニケーションを取ろうという心情や、街へ行く為の感性の道を意地でも開くという執念が現れています。
家族や周りに信頼出来る人がおらず、そんな時にやっと同じ精神性を持った大人に出会い、少年は必死だったんだと思います。それが「聴いてくれる器官」でもある耳を噛むという行為に現れていると思うのです。
またコーヒーショップの彼女や少女が耳を触り癒してくれるのは、その二人が、感覚を研ぎ澄ます器官である耳に、優しさという癒しを与えてくれるような存在であることを象徴しているように思います。
耳を澄まし聴くという行為は、誰かの愛を感じたり意識したりする感性が無ければ出来ないのです。
村上作品の耳は、「優しさ」「感性」「想像力」など、様々な意味が込められているのだと私は思います。
優しい柔らかな着地
本作は、運命の理不尽や様々な事柄により、心を傷つけられたり、心を失ってしまった人が、どういう風に世の中と向き合っていったらいいのかを、優しく物語として紡ぎあげた、現代を生きる我々にとってプレゼントのような作品です。
「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」が、純粋性の憧憬に重きを置いていたのに対し、本作は読者に対し、優しい穏やかな着地を提示しています。
物語の中での現実へ着地する方法も、本作では明確に他者の力が意識されています。
その方法は「誰かが地面で受け止めてくれることを心の底から信じる事」であり、そのド直球のメッセージは我々の胸を打ちます。
また本作は、村上さんの作品に出てくる、失われた人の人生のその後に光を当てたという意味でも重要な意味があります。
主人公は四十五歳を超えて、コーヒーショップの彼女という自分を受け止めてくれる存在と会いました。
また子易さんに関しては、生の時間軸がたとえ終わっても、死と魂の時間軸・無という未知の可能性において、誰かを本気で愛した経験により救われる可能性を示唆し、死をも包摂した恩寵の可能性を我々に与えてくれます。
つまり本作は例え何があっても、どんなに時間がかかっても、人間が救われる可能性は必ずあるということを示しているのです。
主人公が最後、現実に着地した時、そこが「どこまでも柔らかな暗闇」と表現されるのは、この先何が起こるか誰にも見通せない、人生という暗闇を手探りで進むことを恩寵として捉えているからであり、ここにも優しい肯定の姿勢があります。
コロナ禍で経済的にも苦しく、また人と人との距離は増大し、若者はきっとこれからかなり苦しい時代を生きることになるかもしれません。
しかし、その社会において「どう生きるか」は自分が選べるし、やり方次第でいつでもやり直しはききます。
重要なのは、穏やかに優しく、人の心の動きや音をよく聴き、そしてゆっくりでもいいから歩み寄ることなのです。
本作は、過去に何か大事なものを失い、欠損を抱えた人への希望の書でもあり、また現代に生き、コミュニケーションや色んな事に悩む全ての人に対する恩寵の書だと思うのです。
厳しい時代に、本の持つ可能性と力を、改めて感じさせてくれた本作に感謝して、考察を終えます。
↓「アフターダーク」の考察もしてます。良かったら見てね