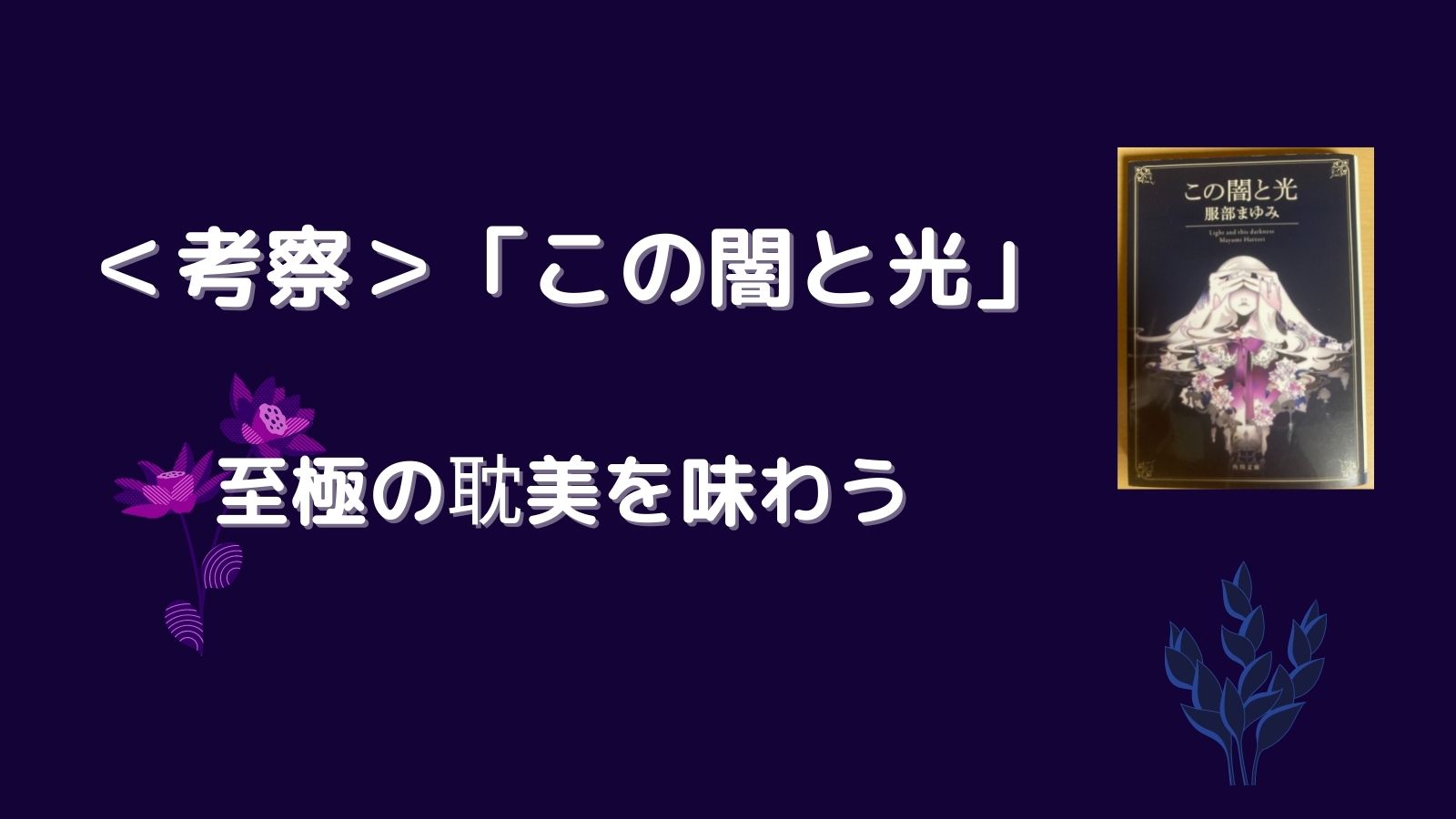「この闇と光」は服部まゆみさんの長編小説です。
森の奥に住んでいる盲目の王女・レイアは、父の愛や奇麗なドレス、物語等、様々な美しいものに囲まれて育ちます。
しかしある時、そんな世界に急展開が巻き起こり、レイアは色々な事実と向き合うことになります。
美に美を塗り重ねたようで、深く内に入り込んでいくような、これぞ耽美というような至極な時間を味わえる本作。
そんな本作を自分なりに考察していきます。
以下、物語の核心に触れることもあるので、ネタバレが嫌な人はここでストップしてください。
美の厳選
ドストエフスキー、夏目漱石・・・・・
目が見えないレイアが、国王から与えられるものは考え抜かれた厳選された作品ばかりです。
そして閉じ込められた屋敷の中の風景や香りなども、レイアの中の知覚を研ぎ澄まさせ、内面に美しい世界を作り上げさせています。
目が見えず、視界は闇の中に包まれており、嗅覚や触覚でしか世界を感じ取ることが出来ない状況に、至高の作品が詰め込まれることで、レイアの想像力は劇的に進化し、普通では到達しえない美の世界を内面に作り上げることに成功しているのです。
のちに屋敷から解放され、大木怜として両親の元に戻り手術で目が見えるようになった時、徐々に現実の醜さに辟易してしまったのも、外にある現実よりも、内面の世界の方が美しい世界を作り上げているからであり、大木怜は美に取りつかれ美に内面を支配された存在に変えられてしまったのだと私は考えました。
男女の差
レイアとして屋敷で過ごしていた主人公ですが、実際は大木怜という男の子でした。
蛇を叩いたら女に変わってしまい、後にまた男に戻り、そして予言者になる人物の「変身物語」という作品が劇中で語られますが、まさにこの体験を大木怜くんはしたことになります。
我々は男女の性別の違いをかなりはっきりとして意識していますが、男も女も同じ人間ですし、もしかしたら境目はそんなに無いのかもしれません。
主人公は、意識において、女性になり、そしてその後男に戻りました。
もしかしたら性別も、自分の意識による部分が大きいのではないか、そうも思います。
また自分は断定的なものよりも、あいまいな感覚の方が、美に近い場所にあるのではと思っているので、この体験がより主人公を、美を志向する存在へと駆り立てているのではと思うのです。
現世への厭世観
大木怜君に戻って、目が見えるようになったものの、目に映るもののほとんどが、彼には醜いものに見えてしまいます。
皮肉な話ですが、彼にとっては目が見えない頃に作り上げていた世界のほうがより美しく華麗だったわけです。
そして怜君ではなく普通の人にとっても現実が想像に叶わないのは当然です。
私はここに作者の現実に対する感覚が滲み出ていると感じます。
世の中にはくだらないものが多く、大木君の本当の父が、画家でありながら売れることや名誉に価値を置いていたり、マスコミは俗な事件ばかりを追い回します。
そしてそういう人たちの顔はどこかしらが歪んでいて、世の中を見回すとそういう人ばかりが目につきます。
そうなってきたときに、自分の中に逃げ込み、自分だけの美を生きるというのは、とても理解出来るし、甘い快楽を漂うような感覚に身をゆだねることが出来ます。
一方で、一生懸命畑を耕している農家のおばあちゃんのしわ等、現実にしか存在しない美もありますし、そちらも尊いと思います。
ただし、この作品は、作者の中にある全霊を込めた美を堪能する作品なので、美というものにのみ主眼を当てた視点からみたら、現世が汚くみえるのは道理であり、「想像美の至極」という脳内美の世界の憧憬こそが、ここでは描かれているのだと感じました。
幼少の歪みが生んだ美
怜を誘拐し、レイアとして育てることにしたのが小説家の原口孝夫、本名は和泉高雄という男です。
なぜ誘拐したのかということは様々な要因がありますが、その一つに幼少時の歪みがあります。
原口の回想から読み解くに、母に愛されたというような感じも受けませんし、家政婦のフネには見えないところでつねったり脅されたりしていました。
そして女性中心の家族の中で、彼は女の子の服を着させられ、そしてそれを母も姉も喜んでいました。
この母や、女性への屈折した感情が、大木怜くんことレイアに向けられています。
自ら声を変え「ダフネ」という意地悪の家政婦と、優しい父の二役を演じ、そしてレイアという女の子として育てる。
ある意味で、自分と同じような存在を作り上げたかったのかもしれません。
そんなレイアに自分が厳選した作品を詰め込んでいくわけですが、レイアが目が見えなかったことにより、想像力の進化、内面世界の拡大が、自分の思っていたよりもすごいレベルで推移してしまったのです。
幼少の歪んだ、屈折した気持ちが、とんでもないレベルの美を内面に抱え、美を志向する存在を生み出したともいえます。
作家と作品
この物語は、主人公の怜が、現在の自分をこのような存在に育てた原口孝夫(本名、和泉高雄)に、大木怜ではなく、和泉怜亜として会いにいき、その会話のシーンで幕を閉じます。
自分は、この原口と怜の関係は、服部さん自身の捉える作家と作品の関係を表しているのではと感じました。
目の見えない、真っ白な状態の存在に、自分が美しいと思うものを詰め込み作品にする。
そして、その作品からも思いもがけないような影響を作者自身が受け取る。
もしかしたら作家と作品との関係も人と人との関係に似ているのかもしれません。
怜に自分の思う美を詰め込んだ原口は最後に、怜と一緒に至高の場所に辿り着いたそんな気がします。
そして作者にとって「この闇と光」という作品も、小説を書くこと自体をモチーフにして、作者と作品の関係性そのものを表現したものなのではないか、そう感じたのでした。
自分が自分自身の歪みも含めて、隠さずに「美」を表現した場合、その作品は自分自身の歪みを携えた存在としてそこに現れます。
そして読者がそれを読むことにより、その作品の美と歪みは作者の手の届かないところまで到達する。
そんなことを思いました。
この作品を読んで思うのは、歪んでいる物ほど美しいと思う心が人間にはあるということです。
バランスを取ることが人生では大事だと思いますが、一方でバランスを欠いた物ほどとても美しくもある。
そんなことをこの作品を読むと感じます。
「美」というものについて、一層深く考えさせれれ、またそれの歪みを味わせてくれる極上の読書体験に感謝して本考察を終えたいと思います。