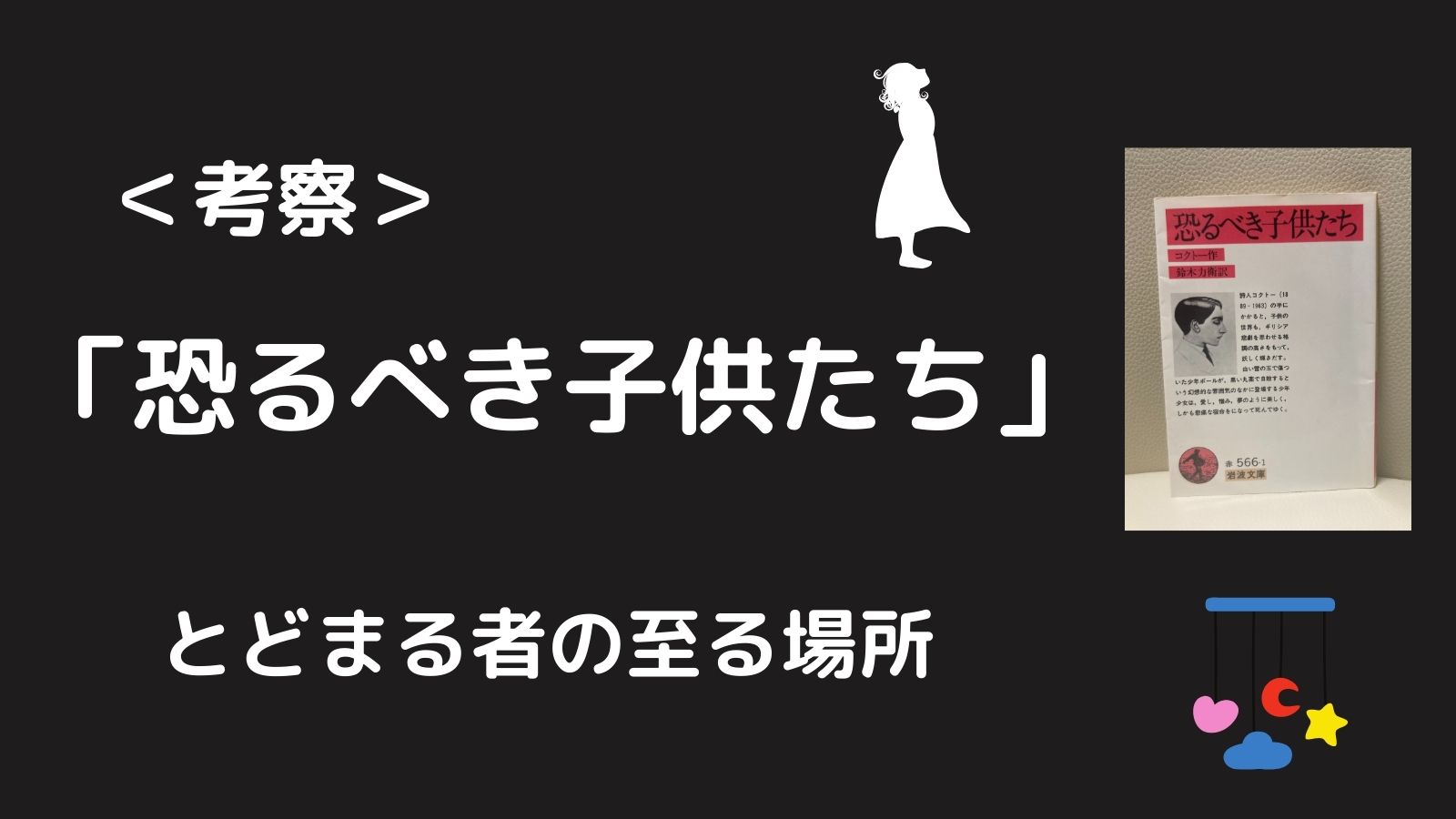「恐るべき子供たち」は、フランスの詩人ジャン・コクトーが書いた中編小説であり、コクトーの小説としての代表作の一つです。
あらすじとしては、モンマルトルの屋敷の部屋で二人だけの世界を築く、エリザベートとポールの姉弟の蠱惑的で幻惑的な生活と、それに魅せられた男女、ジェラールやアガートとの交流を通し、純粋で禍々しい幼少時代に現れる「期間限定の力」を引きずり続けた者の人生を描いた物語です。
遊び、性欲、死、野蛮などの要素を美しい言葉で練り上げた夢想の世界は、想像力の薬と、そして毒を存分にこちらの臓腑にしみ込ませ、しばらく体から黒い力みたいなものが抜けませんでした。
以下、物語の重要部分に触れるので、ネタバレが嫌な人はここまででストップしてください。
夢想世界
「行っちゃった」
モンマルトルの部屋で、エリザベートとポールの姉弟が夢想世界に入ることはこう表現されます。
少しけだるいうんざりした気分から、意識をまどろませ飛ぶ夢の世界。
それは子供だけが把握出来る「世界の混沌をそのままとらえる力」が見せているのではないか、本小説の夢想の描写を読むとそんなことを感じます。
そんな姉弟の遊び方はとても独創的です。
ザリガニを裸のまま胸に抱え、そして寝ている弟の口に突っ込んだり、「盗み」という行為の純粋さの為に、役に立たない物限定という縛りで盗みを働いたりと、彼らは道徳や通念、そして一般的な美という感覚とは違う次元で、人生を泳いでいます。
エリザベートの「美」に対する態度について作中では
「美とは、しかめ面や、鼻ばさみや、ポマードや、ひとりぼっちでいるときにぼろきれで作る滑稽な衣装などにたいする口実に過ぎなかった。」
と表現されますが、夢想世界の剥き出しで遊びや滑稽に満ちた力は、「美」という上品な型に規定されるものではなく、地面に足を付けてしまった大人からは、到底想起出来ないものなんだろうと感じます。
野蛮の持つ力と性欲
この物語は、雪合戦のシーンから幕を開けます。
そして学校の荒くれものであり、力に起因する美しさを持つダルジュロスという少年が、雪の中に石を混ぜた物をポールに投げつけ、大けがをさせることが終盤まで意味を持ちます。
序盤でいきなり意表を突かれるのが、ポールは怪我をさせられたダルジュロスのことを、崇拝しているということです。
事件の顛末を語ろうとした友人のジェラールに
「きみはどうかしてるんだ!」
と声を荒げかばうほど、ポールはダルジュロスに心酔しています。
子供は、大人に比べ知識はないですが、逆に言えば世界のあるがままを見ているとも言えます。
そしてダルジュロスが持つ、あるがままの野蛮さと、それに起因する美が感覚の鋭いポールに強烈な憧れを抱かせたのだと思います。
そしてその憧れの根本は、ダルジュロスを見る「彼自身の精神」なので、劇中でも、「ダルジュロスは宝物のなかの写真と合体し、モデルは不用になった」と表現される様に、ダルジュロスが放校処分になったところで関係はなく、合体して一つになった観念を、自身の憧れの「野蛮という美」の結晶として、精神の神棚に祀り上げ続けることになるわけです。
私が「野蛮という美」に近いものがあると個人的に感じるのが、「性欲」です。
動物の本能としての剥き出しの性欲は、相手を物として扱い服従させる野蛮に連なる側面があることは否定出来ません。
思春期を迎えたポールが後に、ダルジュロスと似た女性のアガートと出会い、彼女に惹かれるわけですが、もしアガートとの恋愛が上手くいった場合、最初は野蛮な魅力からのスタートでも、徐々に彼女の優しさに触れ穏やかな性欲へのソフトランディングも可能だったように思うのです。
実際にはそうはなりませんが、性欲という、野蛮でありながらも生物の循環を体現した力が、禍々しい観念の夢想の世界を断ち切る可能性もあったのだ、そう思います。
死という幻惑の遊興性
実の母親の死を目撃した姉弟。
その「石化した叫び」の様な強烈な印象は、姉弟たちの精神に多大な影響を与えています。
彼女たちは、その死の印象の幻惑性を装飾し、夢想世界での最高の地位を与えることで死を飲み込みました。
しかし、その飲み込んだ死の要素が自身の精神に一つ、新しい部屋を作ったことは紛れもない事実でしょう。
後述するミカエルの死は、これにプラスしてさらなる大きい影響を与えます。
死の感覚を自分に取り入れたことが、終局の場面へと繋がる一つのピースだったことは間違いなさそうです。
富むということ
貧しい孤児である姉弟。
そんな二人に、エリザベートがミカエルと結婚したことで財産が入りますが、実のところ二人には全く関係がありませんでした。
二人は、「財産が無い時代から、常に富んでいた」という表現の通り、夢想から得る富を浴びるように暮らしていた姉弟は、精神における富の体現者ともいえる存在だからです。
しかし現実社会では、形式的には「精神の幸せ」を求めよと言いますが、金銭や形ある物以外の富を強烈な意思で求める人は、変人や異端として排除されます。
精神の富を得る感覚を天才的に持っている二人の姉弟も、この例外ではなく、徐々に現実の形式なものに知らないうちに圧迫されていきます。
本当の突き抜けた精神の富を、現実社会は毒とみなすのではないか、そんなことを感じました。
部屋に入る者たち
ジェラール、アガート、そして看護婦のマリエット。
この人たちは、姉弟の感覚を理解、もしくは憧れを抱き、夢想の部屋に入る能力がある人たちです。
ジェラールは美しい夢想の力を持つポール、後にエリザベートに魅せられ、アガートは最初は洋裁店の友人としてエリザベートに惹かれ、そしてポールに恋をします。
マリエットは老人でありながらも、子供たちの部屋の感覚をあるがまま理解し、解読出来る能力があります。
理屈や道徳とは違う地点にある、姉弟の感覚的なものを理解出来る彼らですが、部屋に入ることは出来ても、その部屋自身を司る精神ではありません、いずれは部屋を出ていき現実に着地することになります。
ただしポールは部屋から出ていく可能性もありました。
それはアガートというダルジュロスの外見に似ている女性の影響ですが、この危険をエリザベートが排除することで、物語は終局へ加速するわけです。
ミカエルの死
エリザベートと婚約したミカエル。
天使の名を冠する如く、財を持ち、美しい見た目を持つ彼は現実の光を象徴するような存在です。
しかし、夢想の部屋の精神は、ミカエルがエリザベートを連れていくことを許しませんでした。
彼は不慮の自動車事故により死亡します。
この事件は、殺人ではなく確かに事故です。
しかしこれは劇中でほのめかさるように、「部屋の精神自体」が彼を殺したのだと私は思います。
何か得体の知れない理屈では処理できない力が、人の命を奪うこともあるのです。
しかし劇中でも表現されるように、この「死」によりミカエルはようやく彼女たちの部屋に、ある種の象徴として入ることが出来ました。
ここからは私の想像ですが、ミカエルという「死んだ天使」は、殺されるだけではなく、「堕天使」として部屋の中に入り死の感覚を撒き散らし、無意識下で姉弟を蝕んでいったのではないでしょうか?
徐々に現実が近付いてくるように、この「天使の死」は、彼女たちが運命から守られる地位を失ったことを象徴している・・・
この後の物語の展開を見て、そんなことを思いました。
失われつつある部屋の力
遊び、野蛮、死、それらの剥き出しの力を夢想に宿し、力を閉じ込められた部屋の力。
それは禍々しくも魅力的で、なおかつ空気よりも軽い浮遊感を持つ子供時代にしか得られない期間限定の力なのではないかと思います。
その能力の才能の大小はあれども、大抵の人が、成長していく過程で、道徳や社会のルールと折り合いをつけ、その能力のことは忘れ去られ、もしくは隠して生きていくことになります。
そしてこの驚異的な姉弟でさえ、現実はドアをノックします。
「夢の世界へ遊ぼうと思っても、自己の中に沈潜してしまい、そこには暗黒と感情の亡霊にしか出会わない・・・」
劇中で示される上記の表現からも、姉弟たちに社会と自己との折り合い、すなわち現実が無意識下に迫ってきていることが分かります。
しかし、それを許さず、認めない行動を強力に推進するのが、エリザベートです。
彼女については後述しますが、彼女のこの精神がラストシーンへ姉弟を導くことになります。
ポール
部屋の力を構成する一人、弟のポール。
夢想の精神の天才的な力を持つ彼ですが、実は意志においては姉より数段劣ります。
少し病状が回復し海岸に向かう汽車の中、もともと無気力になりがちで、弱い性質がある彼に、エリザベートは
「小さな幸福に咽喉を鳴らし、舌なめずりして、それを味わうある種の食いしん坊」
という世間の小市民の幸せの感覚の徴候を見ます。
そしてその生ぬるい感覚をエリザベートは嫌うのです。
エリザベートの峻烈な精神は後述するとして、ここにポールの地面に足の着いた感覚の切れ端を見ることが出来ます。
また、思春期になり、娼婦を求め街に出歩くのも、性欲がなせるわざで、そこには夢想ではなく肉欲という動物としての大地の力が作用してます。
ダルジュロスに対する憧れは、「野蛮という剥き出しの精神」という夢想に繋がる側面もありました。
しかしアガートというダルジュロスに似た女性に会うことで、野蛮から性欲、そして性愛へという感じに一般の幸せへ着地することも彼には出来た可能性もあり、その素養もありました。
しかし最後は、夢想の力と現実の綱引きにおいて彼は負けます。
そしてその綱を強力に引っ張っていたのが姉のエリザベートでした。
エリザベート
「恐るべき子供たち」
その中でもまことに恐ろしく、そして美しい存在。
それがエリザベートだと思います。
野蛮さ、性欲という要素の影響下にあったポールに対し、彼女は純粋に夢想の世界に身を置いていたように私は感じます。
小さな幸せを生ぬるいと感じる彼女の精神の、峻烈さ禍々しさは、とても魅力的です
アガートへの愛を持っていたポールに対し、彼女のミカエルの愛については語られません。
ミカエルを愛してなかったわけではないと思いますが、彼女の精神は「夢想の世界」から全く動かされていなかったのだと思うのです。
期間限定で得られる剥き出しの力に一番こだわり、そしてそこに居続けようとしていたのはエリザベートだと思います。
だからこそ、野蛮や性欲、そしてそこに繋がっていた夢想を、全て断ち切る可能性があるアガートのポールへの愛に対し、最も危険を感じ、それらの成就を壊す行動をしたのはある種当然だったのではないかと思うのです。
そして、その力にこだわり続ける場合、どこかで破綻は訪れ、それを受け入れるか、もしくは違う道を選ばざるを得ない、どこかで彼女は分かっていたのだと思います。
ととまる者の至る場所
野蛮から昇華された憧れの象徴、ダルジュロス。
彼とジェラールとの再会が破局の幕開けです。
幼き日のたわいもない話からダルジュロスが渡した黒い毒薬。
アガートとの恋がエリザベートの陰謀で実らなかったポールは、この毒薬を飲みます。
見方によっては、ねじまがった野蛮への憧れと性欲を昇華出来なかった男が、自分の憧れの野蛮の毒により自死をはかる、そんなシーンにも見えます。
おそらくここでダルジュロスが毒薬を持ってきたことはポールにとって何かの啓示のように思えたのではないでしょうか?
そしてこの「昇華出来なかった憧れが運んだ毒薬」はエリザベートの破滅をも意味しました。
とどまろうとする意思に復讐するように、部屋と現実のねじれが姉弟を押し潰しにきたわけです。
毒に苦しむポールの看病をするアガート、そして二人の会話から露呈するエリザベートの陰謀。
ここにおいてエリザベートは、部屋の力の終わりを決定的に意識します。
例え、ポールが生き残ったとして、もう二度とあの部屋の力は戻らない、そう考えた彼女は部屋の精神を自信で爆発させる道を選ぼうとします。
しかしアガートの「このひとは気違いになる!」という声が、その道を塞ぎます。
「気違い」という安直で陳腐な言葉のレッテルで、終局をくくられることを彼女はよしとせずに、瞬間的に冷静さを取り戻したのではないかと思うのです。
そして緊張の中で彼女がとっさに取った行動は、計算、掛け算、割り算、または建物の番地を思い浮かべ、合計したり、とりとめもないうわごとを言ったり、暗唱をしたりすることでした。
これは部屋の精神に奉仕し続けた彼女が、部屋の精神からとっさに受け取ったプレゼントだったのでしょう、この「無意味で空虚な意味への反逆とも思えるとっさの行動」は彼女に勝利をもたらします。
エリザベートの落ち着き払った様子と、その視線により、ポールは神秘的な好奇心の方へと足を踏み出してしまったのです。
部屋の力に奉仕し続けた、ある種巫女のような彼女の力が、一番近くにいた弟の精神を引っ張り上げた瞬間でした。
そしてここでの夢想での上昇こそが「部屋の力の到達点」だったのでしょう。
弟が頭を垂らしたのを見て、こめかみをピストルで撃ちぬいた彼女は、夢想の最上点で生を終えたことになります。
その意味で彼女は現実に勝った、少なくとも負けはしなかったのだと思います。
夢想という期間限定の禍々しいエネルギーの場所に、あくまでもとどまろうとする場合、現実の世界とは完全にお別れを告げる必要があり、彼女はそれを一番高い位置で実行したのでしょう。
最後に
この物語の密度はすごい。
それでいて、暗い軽さと妖しさが物語を支配していて、最後にはとんでもない地点へと心が運ばれていく・・・・・
何というどんでもない作品でしょうか。
文学作品は毒にも薬にもなるといいますが、こんなにも鮮やかな毒を盛られた場合、もはやそれは極上の薬になるのではとすら思います。
この作品は、過度な想像力の持つ毒のことを描いてあるのと同時に、一方でエリザベートの想像力への奉仕した生き様に対する憧憬や敬意という作者の思いが感じられ、私はそこから芸術や想像力に対する希望をもらいました。
子供の時分から現在に至るまで、変なことを考え、夢見がちに視線を宙にさまよわせがちな私ですが、このままこの思いを抱えて生きていってもいいんじゃなかろうか、そんなことを本書を読み終えて、ぼうっとしている時にふと思ったのです。
この圧倒的で凝縮された読書体験に感謝して、本考察を終えます。