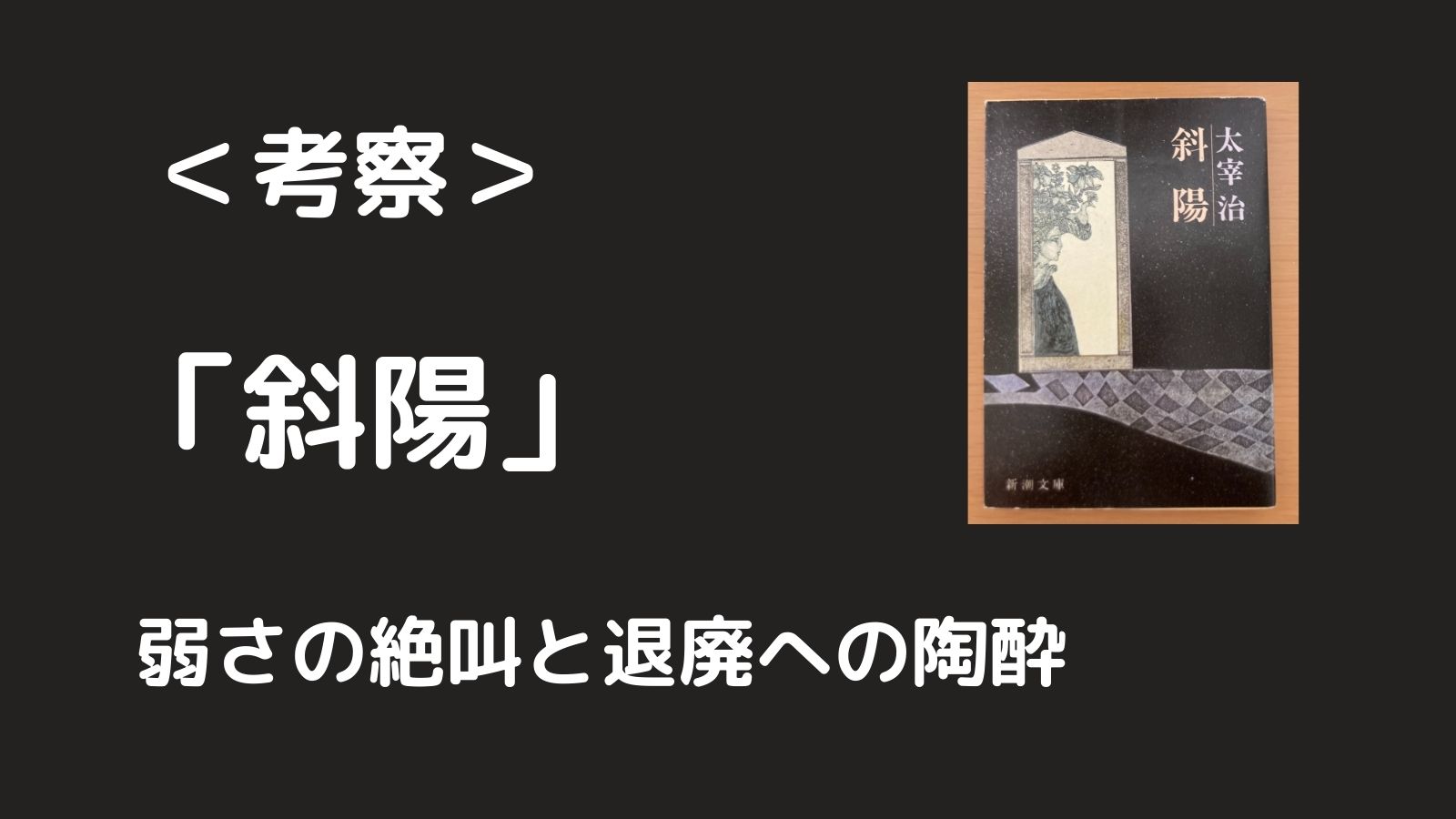「斜陽」は、第二次世界大戦前から戦後にかけて作品を次々に発表した文豪、太宰治さんの代表作です。
没落した貴族の家を舞台に、主に姉のかず子の視点から、無邪気さと高貴さを併せ持つ母、南方の戦線から戻り自堕落な生活を送る弟の直治、芸術や人生に退廃感を抱える小説家・上原、というかず子を含めた4人の人物を描くことにより、戦前・戦後という時代の変化とそこに対応出来る人と出来ない人それそれの悲しみや、生きていくことそれ自体の虚しい無常観等を読者の心に刻み込む傑作です。
そんな本作を自分なりに考察します。
ネタバレが嫌な人はここでストップしてね。
それぞれの人物
まずそれぞれの人物に関してごく簡単に見ていきます。
かず子
この物語の視点となるのが、かず子です。
かず子は一度結婚したものの、家に戻ってきており、弟の師匠的存在である、小説家の上原に恋をします。
物語中盤で上原に当てた3通の文が出てくるのですが、その内容から見ても、生きるたくましさ、そして燃えたぎるような粘り強さを秘めていることを感じさせます。
母と弟の直治が庶民の世に上手く対応出来なかったのに対し、かず子は世間に下りていき生活していく泥臭さみたいなものを持っており、直治とは対照的に描かれます。
母
ゆったりとして高貴な美しい貴族として描かれる、かず子と直治の母。
彼女は、滅びゆく、美しく無邪気なのんびりしたものの象徴として描かれます。
もはや失われた時代の滅びゆく精神の象徴としての母。
この母の振る舞いや、母の病死が、かず子や直治に影響を与えます。
直治
かず子の弟の直治は、南方の戦線に居ましたが無事に戻ってきます。
しかしもともと麻薬の使用癖があり、金遣いも荒い直治。
戻ってきて早々に東京に遊びに行った彼は、東京に行ったきりなかなか戻ってきません。
しかし荒い言葉使いや、すさんだ暮らしは、貴族にも庶民にも自分の居場所はないといった弱さの裏返しであり、最後は、母の死を追うように自分も自殺します。
上原
直治の師匠的な存在として出てくる小説家です。
芸術の仕事をしながらも、芸術に絶望しており、奥さんや子供を放置し遊んでばかりいます。
直治の絶望が自身の階級や存在に根差したものだとすると、上原は、時代の退廃への虚無感、そしてそれとリンクするような物を作るものとしての自分や、物を作ることの絶望の中で生きています。
そして、本作の語り手とも言えるかず子は、この上原と恋に落ち、最終的に子供まで授かります。
蛇とは何か
この小説に繰り返し出てくる蛇の描写。
これは人により捉え方が異なります。
母は夫が死んだときに出てきた死の象徴として捉えており、蛇を恐れています。
トグロを巻いて地面を這いまわる様は貴族の美学からも、とても恐ろしいものとして感じたのだと思います。
一方、かず子は蛇を見ても恐いという感覚はありません。
それどころか、見かけた蛇に美しいとさえ感じます。
蛇とは、地面を這いずる泥臭さからの連想で、まず泥を這うような庶民の暮らしの象徴としての要素があると思います。
さらに、丸い円、繋がっていくもの等の連想から生命力の象徴でもあると感じました。
またこの物語では、かず子が危険な蝮の卵だと思い、普通の蛇の卵を誤って焼いてしまい、後日、現れた蛇が卵の母親ではないかとかず子が思う印象的なシーンがあります。
この母性と執念がねじれたようなシーンを見て思うに、蛇には、粘り強さ、艶っぽさ、執念といった太宰さんが考える女性が抱える情念の象徴としての意味もあるのではと思いました。
上記の物全ての要素や艶っぽい情念に対して縁が薄い無邪気な母と、それを内に抱えるかず子とでは、蛇に対するリアクションが全く違ってくるのは当然で、その対照が物語の奥行を深くしていると個人的に感じました。
退廃を抱える男たち
この小説の男たちは、退廃の中を生きています。
麻薬中毒になりながら、自分には生活する力が欠けていると宙を漂うような生き方をする直治。
上原は小説を書きながらも、芸術に対して光を見ているわけではなく、退廃に浸ることを自ら望んでいる節があります。
生きることに対する切実さに差こそありこそすれ、野望や欲望を持て余し、それでいてプライドもあるため、現実の生活とのバランスを取るのが苦手な、男という存在が、二人に体現されています。
一方、母やかず子の女性陣です。
母は、悲しみに暮れることはあっても、自ら哀しみに浸っていこうという感覚はありません。
無邪気に生きながらも、悲しい時は悲しい気持ちになる、というような感じで、人生の流れを意識的に自分から当てはめようとはしていないように思うのです。
またかず子は、伊豆に来てから農作業をしたり、これからは恋と革命だと決意したり、基本的にこれからも生き抜くことを前提に、思考が組み立てられています。
自分の理性とプライドを保つため、現状をあえて悲観的に捉えて、自分が作った退廃の中で生きることに逃げ込んでいる男性に対し、現実との対峙や、バランス感に優れている女性との対比がここに見受けられます。
母の死への捉え方
男の子にとっての母の死。
これはとても筆舌に尽くし難いものです。
自分を全肯定してくれる存在の死、まさに自分の体のほとんどを持っていかれたの如くに感じ、結果として直治は母を追うように自殺します。
しかし、女の子にとっての母の死は少し意味合いが違います。
悲しみはもちろんありながらも、かず子は戦闘開始だと言います。
これはとても興味深い言葉です。
つまり女の子にとって、母の死は悲しみと同時に自分が母になるきっかけでもあるということだと思います。
生きる意味を自分の理想や環境、感覚や脳内で求める直治に対し。
自らの存在、子という存在を生きる意味に置くかず子。
ここに根本的な生きる強さの差があります。
上原の奥さんに恋をしつつも成就させずに、観念の美を保ったまま死んだ直治。
上原に対しての幻滅よりも、自分自身が一時は感じた恋に身を寄せ、子という存在を成したかず子。
この姉弟の生命の使い方の違いからは、色んな事を考えさせられます。
絶叫
この小説が現代でも若者の共感を呼ぶわけは、直治の最後の手紙にあると思います。
この手紙の内容を一言で言うと、弱さの絶叫です。
どこにも自分が属している気がしない
自分には生きる力が欠けている
どうにかして下品になりたかった
遊んでいても少しも楽しくなかった
人間は皆同じものだと言う哲学に対する憤り(その同じものの社会になじめない自分の悲しみ)
など、ここにある言葉はとてもストレートで切実です。
そして人間はいつの時代も、弱さを抱え、悩みを抱え、孤独を感じながら生きています。
特に青春時代はそれが顕著で、程度はともかくとして一度は自殺が頭をよぎったことがある人の方が多いのではと思います。
だからこそ、この手紙は現代でも多くの人に突き刺さるのです。
太宰さんのすごいところは、若者の普遍的な悩みを捉え、共感を呼び起こし、そして心を揺さぶることが出来ることです。
上記の手紙の内容は、現代でもあてはまることのオンパレードで、それなのにこの小説はあたかも自分だけの心にダイレクトに響いている気がするのです。
ここに太宰さんが若者の心をつかんで離さないパワーがあるのだと思います。
上原の芸術への退廃感や、母という存在への思い、かず子に描かれる女性の強さや可能性、全ての人物に太宰さんが居ると思いますが、一番は、自ら死を選んだ直治に載っているのではないかと個人的に感じました。
自我が自ら作り出す退廃の香ばしさや、誰もが持っている弱さへの共感といった要素に、戦前から戦後への時代の変化の様相を、男女を通して描いたのが「斜陽」という作品だと思います。
この作品が救いになるのか、毒になるのかは読む時期や、自分の状況によると思いますが、ものすごいエネルギーを秘めた傑作であることは間違いないと感じました。