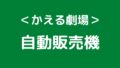「月と六ペンス」はイギリスの小説家、サマセット・モームの長編小説です。
画家のポール・ゴーギャンをモデルにした、ストリックランドという、絵を描くために全てを捧げた男の生涯を、「わたし」が語っていくというスタイルで進む物語で、至高の美に手を伸ばし続けるストリックランドの人生は、読むものの魂を振るわさずにはいられません!
個人的に、自分の人生の生き方の指針となっている大事な作品で、本作から貰ったもので今の人生を生きていると言ってもいいほどに、大事な小説です。
そんな本作を自分なりに考察していきます。
以下、物語のネタバレを含むので、ネタバレが嫌な人はここでストップしてね。
ストリックランド
証券取引所の仲介人として、妻と子供たちと安定した暮らしを送っていたストリックランド。
しかし彼は、ある時絵を描かなくてはならないといい家族を捨てます。
彼はその情熱を、「川に落ちれば、岸に上がるか溺れるかふたつにひとつだ」と表現しており、絵を書くことを宿命として捉えています。
しかし、絵の評価や世間体には一切興味が無いストリックランド。
わたしに「コンテストに出ないのか」と言われた時は
「君はそうだろうな」
となかなか皮肉な返しをしています。
芸術を志す人にも心のどこかで「誰かに認めて欲しい」「良い暮らしをしたい」という欲望が潜んでおり、そしてそれは悪いことばかりではないと思います。
しかしストリックランドには、そういう気持ちが全くありません。
それは彼がとことん、自分の中の光を見ているからです。
それは、とても素晴らしい予期せぬ何かで、朧気に見えているようで、全く掴めそうにもないようなものかもしれません。
しかしそれに辿り着いた時、人々は幸せの恩寵に包まれる。
そのようなものが彼の目指すものだと思います。
世間の評価や、売れる絵をマーケティングして作っていくと、作品は得てして平均的になっていき、そこには媚びる様な陳腐さと安っぽさが並列する魂の抜けた入れ物だけが存在することになります。
しかし、個人が魂を削って本気で手を伸ばし生み出した物は、人間の深い所に届き、他者の心を繋げていく、そんなことを思います。
そしてストリックランドがやっていることもそういうことなのだと思います。
ブランチが彼に惚れたのも、ストリックランドがブランチの本質を見抜き、絵に落とし込む力があったからだと思います。
ストルーヴェ
ありきたりで美しい絵を写実的に作り、「チョコレートの小箱の巨匠」とも言われるストルーヴェ。
優しくて、良い人間でありながら、度を越えたお人よしと滑稽さで馬鹿にされがち。
しかしそんな彼は、本当の美を理解する審美眼の持ち主でもあります。
ストリックランドに自分や自分の絵を見下されながらも、ストリックランドの絵の素晴らしさを手放しで評価する様子は、芸術家としての一つの資質の在り方だと思います。
おそらくこの人格は、両親に全力で愛されて育ったことが影響していると思うのです。
たとえ絵や人格を馬鹿にされたとて、自分という存在は存在してるだけで価値がある。
彼の余裕やお人よしは、そんな心から来ていると思います。
ストリックランドが、自分の中にある美の価値を信じていて絵でそれを表現することに取り憑かれているのに対し、ストルーヴェは究極の話、絵を書いていなくても自分には価値がある、そんな風に思っているのではないかと思うのです。
だからこそ自分の絵とストリックランドの絵を比べ、平気でストリックランドの方に軍配を上げたり出来るのではないでしょうか。
私は余裕のある男こそ人を愛することが出来、女性を幸せに出来る力があると思うのですが、全ての事柄や事象が当てはまるわけではありません。
ストルーヴェとブランチ夫人のパターンも当てはまらない例の一つだと思います。
特に彼が妻のブランチにしたことは、言うなれば優しい凌辱と言えるもので、やってはいけないことでした。
ローマの侯爵家で住み込みの家庭教師をしていたブランチは、そこの息子にたぶらかされ、子供を身ごもった状態で捨てられました。
そんな彼女をストルーヴェは助け、妻にしたわけですが、そこにはやはり罪悪感や弱みに付け込んだという側面が存在します。
ストルーヴェの愛が本物だったことは疑いがありません、しかしブランチの側には愛に加え、罪悪感や弱みもあったのは事実です。
しかしストルーヴェが良い人だったこともあり、そのまま本質からずれた状態で結婚に突入することになってしまいました。
本当は、どちらかに負い目があり、それが後を引き、同じ地平で恋愛感情を持てない場合は、付き合わないか、とても繊細に関係を深めていくことが求められると思うのです。
しかし、ストルーヴェは良い人である一方、鈍感で無神経な人でもありました。(この部分が人に馬鹿にされる一因を担っている)
それは以下のシーンに如実に表れています。
病気のストリックランドを引き取る時にストルーヴェはブランチに対し
「どうしようもなく困っていたときに、手を誰かに差し伸べてもらったことはなかったかい?(本文ではこの後もセリフが続く)」
という絶対に言ってはいけないニュアンスのことを言ったわけです。
この道徳的には正しい言葉は、彼女には過去や同情される自分を思い出させる、最大の屈辱でした。
この言葉が、二人の関係の破局の分水峰だと思いますが、そもそもストルーヴェは過度にブランチを祭り上げ、祭壇の人形にしていた節もあり、本当の彼女を見ていなかったのだと思います。
そこに現れたストリックランドは、彼女の中に眠る屈辱に身もだえする高貴さや、欲望を見抜き、絵にします。
つまり彼女の本質を見てくれた人物だったわけです。
一方でストルーヴェは、ブランチにまとわりつき、そこにはプライドも何もありません。
彼が自分を卑下することは、イコールでストルーヴェが選んだブランチ自身を貶めることでもあるわけで、ブランチが彼の頬を思い切り打ったのも納得出来ます。
ストルーヴェは優しい良い人間ですが、その無神経さがブランチ夫人と境遇にとっては最悪なものだったのです。
要は人間には相性があるということで、他の女性とだったら彼はいい家庭を築けていた可能性が高いように思います。
オランダに帰った彼ですが、おそらくそこでとても幸せな人生を送れているのではないか、そんなことを思います。
ストリックランド夫人、ブランチ、アタ
ストリックランドが関係する三人の女性。
この三人の個性の違いが物語をとても面白くしています。
まずストリックランド夫人ですが、夫を退屈だと思い、芸術に熱中していながらも、彼女の中にあるのは流行と形式だけです。
そして色んな思想に興味は持ちつつも、それを絶対に自分の人生に持ち込みません。
これはよく言えば、社会で生きるバランス感覚が抜群であるとも言えます。
しかしストリックランドの生き方と、最もかけ離れているのが彼女であり、彼女の中では本質なんかよりも、他人からどう見えるか、社会でどの位置にいるかということが大事なのです。
彼女は、退屈だと馬鹿にしていた夫から捨てられるわけですが、これもとても面白いです。
要は退屈だと馬鹿にしてる場合、相手も退屈だと馬鹿にしているわけで、華麗なる因果応報に心がスカッとしました笑
次にブランチです。
ブランチは、ストリックランドの魂の魅力に気付けたという点では、夫人とは立つ位置が違います。
しかし、やはりそこは世間の価値観で、愛や夫婦、同棲という物差しで物事を見ていて、その物差しが図る幸せは、彼女自身の幸せであり、ストリックランドの幸せではありませんでした。
要はブランチは、自然と「利己」の基準で動いていて、「利他」ではなかったということです。
そして最後は、タヒチ出会うアタです。
じっとストリックランドを見つめ好意を持ったアタ。
彼女は島で育ったおおらかさもあり、ストリックランドを自分の幸せの物差しに閉じ込めようとはしません。
自分も伸び伸びと島で生活しつつ、ストリックランド自身のやりたいようにさせる。
それでいてアタ自身が我慢しているわけではない。
ここに利他と利己の共存関係があり、そしてこれこそがストリックランドが最後に素晴らしい絵を書くことが出来た一因となっています。
この三人の女性の個性と象徴する物が、本作の趣きをより深いものにしています。
良心と社会
本作の文明や社会に対する洞察は、鋭くはっとさせるものが沢山あります。
その中でも良心に対しての言及がすごいです。
- 良心とは心の警察で、法を破らせないように自我に送り込んだスパイ
- 世間に受け入れられたいという欲望、世間の批判に対する恐怖から人間はスパイの侵入を許してきた
- 良心は群れから離れたがる人間の欲望を打ち砕き、社会の利益第一に人間を矯正する
- 良心は個を全体に結びつける太い鎖
- 良心は個人は全体に仕えるのだと言い聞かせ奴隷にさせ、社会を王座に座らせる
- だから人間は社会を無視する人間を激しく非難する
以上が大体の要約ですが、とても鋭くて面白い指摘です。
私は芸術や美というのは、人間の底に眠っている、もしくは見たことがないような何かに、個人の研鑽により光を当てる行為で、そしてそれを続けていくことによって人間の魂は上昇していくという風に捉えています。
しかし、世間や社会の常識や目に過度に自分を合わせたら、出来上がるのは窮屈で見たことのある退屈なものしか出てきません。
だからこそ常に常識を疑い、世間に縛られず、自分が本当に必要なものを考え、求め続けていく行為が必要ではないかと思うのです。
自分の中の心を自由に広げ、間違ってもスパイは紛れ込ませたくない、そんなことを思います。
性欲
本作は人間が抱える性欲の問題にもしっかり向き合っています。
- 欲望さえ満たされれば、ほかのことが出来るようになる(ストリックランド)
- 欲望は魂の枷(ストリックランド)
- 芸術とは性衝動のひとつ(わたし)
- ストリックランドが性の開放を嫌うのは、創造的行為で得られる満足に比べると、その行為は卑俗でしょうがないと感じるから(わたし)
以上は、本作の性欲に関する発言をまとめたものです。(カッコ内の人物がその意見や発言をした人)
ストリックランドが欲望を打ち払いたいと思いながら、打ち払えずもがいてるのも面白いですし、「わたし」が芸術を性衝動の一つと捉えているところも面白いです。
自分も性欲と芸術は近いところにあるとは思いますが、一つの物とは思っておらず、芸術はあらゆる自我や意識、自然が生み出す何かだと考えています。
ストリックランドが性欲と芸術を結び付けているかどうかは、劇中では語られませんが、本作は性欲論として読んでもとても面白いと思います。
タヒチと音の無い世界
緑豊かな高い山、神秘的な谷の暗がり・・・
ストリックランドが終の棲家に選ぶタヒチは、自然の理想郷として描かれます。
そして「ストリックランドが住む小屋や住まいには音がなかった」「大気は夜に咲く白い花の香りがする」とも表現されます。
我々が生きる文明社会(とくに日本)では、どこの施設に入っても音楽が流れています。
そして外でも工事の音や電車の音、など人工的な音が常に聴覚を支配します。
時々思うのは、現代の人々は本当の音を聞けなくなっているのではないか?ということです。
大気の中の暗闇や月の感覚、そして耳だけでなく感覚が聞かせる音。
タヒチに流れるものは、太古から流れる、人間が忘れている何かを呼び覚ましてくれるのだと思います。
そして自分の中にある何かに本当に向き合う場合、自然の力や、夜の闇に耳を澄まさないと深い所には行けないのではないか?そんなことを思います。
美と信仰
ストリックランドが最後に書いた奇妙で幻想的な絵。
クトラ医師はそれを「エデンの園」や、「美しく残酷な大自然の賛歌」など、様々な言葉で表現します。
しかしその中でも特に気になるのが
「あの絵がおそろしいのは、自分自身の姿をそこにみてしまうから」
と言う言葉です。
私はこの言葉で、ストリックランドは自分の中に眠る光を求め続けた結果、人類が持つ普遍的な何かに辿り着いたのだと感じました。
そしてこれこそ芸術に携わる人の、真の恩寵ではないかと思うのです。
物語後半に出てくるブリュノ船長が、ストリックランドが取りつかれたのは「美を生み出そうとする情熱」で、永遠の巡礼者だと言います。
私はストリックランドの人生を見た時に、それはまるで修行僧のようであり、彼は美という宗教の敬虔なる信仰者なのだと感じるのです。
信仰もまた、自分を超えた何かを信じ思いを馳せることにより、最後は普遍的な恩寵に至ることを目的としているのだと思うのですが、芸術家の人生もこれにとても似ています。
そしてブリュノ船長が、自分は絵は書かなかったが「美を求めて人生を生きた」と言います。
これは芸術家だけでなく、どんな生き方にも魂の持ちようで「美」に到達できる可能性があるということだと思います。
妥協して世間に合わせてなんとななく生きるのではなく、深い所で物事を考え、感性を磨いていけば、「美」もしくは自分と他人を幸せに出来る何かに辿り着ける。
本作は私にそんなことを教えてくれました。
果実とは
ストリックランドがクトラ医師に渡したマンゴーやバナナ、そして名前の分からない果物を盛り合わせた絵。
それをクトラの妻は、露骨でひわいだから応接室におけないと表現します。
- 暗い青は不透明だがふるえるような光沢は生命の鼓動を思わせる
- 赤紫は腐った生肉のように不気味だが、そのくせ華やかで官能的な情熱を備えている
- 果実の実はクリスマス、子供の歓声、喜びを思わせる一方、ハトの胸の毛のような魅力的な柔らかさを帯びている
- 濃い黄色は異様な官能をたたえるが、いつしか緑へ変わり、春のような香気を放ち、山の清水のように澄み通る
- すべての物が明確な形を持たなかった頃に生まれたかのようなきわめて豊かな果実だ
- この絵が恐ろしいのは「善悪の知恵の木」の果実のように未知の可能性を秘めているからだ
以上がこの果物の絵の本作での表現ですが、上記は一部の抜粋に過ぎず、本文はもっとすごい表現が多いので、是非この場面を読んで欲しいです。
私は、ストリックランドがこの果物の絵で書いたのは、美を生み出そうとする人間が太古の昔から持っている根源の力だと思います。
それは官能的でもあり、理性的でもある、あらゆるものが混ざり、そしてまだ見ぬ何かを大いに含んだものだと思うのです。
ストリックランドが最後に残した小屋の絵は、根源の力を作品として昇華したものだとすれば、この果物の絵は、その根源の力そのものを書いた絵だと思うのです。
「美」と「人間」についてここまで誠実に取り組んだ本作は、本当にすごい作品だと改めて思い知らされます。
月と六ペンス
物語後半で挟まれるエイブラハムとカーマイケルのエピソード。
医者としての将来を期待されながら、休暇で立ち寄ったアレクサンドリアに魅せられ、そこに神のお告げのようなものを聞き、研修医の地位を辞してアレクサンドリアに移住したエイブラハム。
一方で、エイブラハムがいなくなったことで、その地位についたカーマイケル。
カーマイケルは、美しい屋敷に住み、年収は1万ポンドを下らず、ナイトの称号の授与は確実というような、上品で名誉のある暮らしをしています。
一方でエイブラハムはアレクサンドリアでつつましく暮らしています。
その状況をカーマイケルは、「才能の無駄遣い」「人生を棒に振る」と表現します。
私はこのシーンを読んだとき、なんてカーマイケルは哀れな人なんだと同情してしまいました。
彼の幸せは、お金やお屋敷や称号、上品に見える絵といういわゆる形式や物欲に根差したものでしかなく、言うなれば感性が劣化した俗物だからです。
そして彼には想像力も欠けていて、エイブラハムが求めている幸せの種類を考えること、思いつくことすら出来ないわけで、彼の中には他人からすりこまれたテンプレートのような幸せしか存在しないのでしょう。
そして本作の最後のシーンが、ストリックランド夫人のシーンで締めくくられるのも皮肉が効いていて最高です。
夫人はストリックランドの絵を「装飾的」と表現します。
そうなのです夫人は、ストリックランドの絵の本質など一ミリも理解してないのです。
というより彼女は絵を見ているのではなくて、絵を見る自分が好きなだけで、その姿が世間にどう映るかを想像するのが好きなだけなのでしょう。
つまり彼女にとって絵は自分を装飾するものに過ぎず、だからこそ絵の方も彼女には本当の姿を見せないのでしょう。
彼女は絵に馬鹿にされていると言ってもいいかもしれません。
その語も物語では、自分の子供たちが「軍人の妻」であること、「戦功十字勲章」を授与されるかも知れないこと等、次々と世俗の形式の話が続きます。
あげくストリックランドの最後の様子を「わたし」が話した後に、息子が聖書の引用と勘違いして言葉を語る様子の薄っぺらさは、反吐が出るのを通り越して笑えてきます。
聖書の引用と古代ギリシャのことわざを勘違いするというのも、この家族にとっては信仰すらファッションでしかないことを表していて、作者の描き方の巧みさは本当にすごいと思います。
ストリックランドが「誇りと嘲笑をこめて」完成した最後の絵を焼いてしまったのは、カーマイケルやストリックランド夫人が象徴する世間に、絵の価値が伝わらないことを分かっており、そしてそんな人々に残すつもりもなかったのでしょう。
私は月が、芸術や美を生み出そうとする魂や、妖しく光る未知の力を表し、六ペンスが、勲章や形式など即物的で世俗にまみれたものを表していると思います。
そして現代で生きる我々のほとんどは、夫人やカーマイケルのように、人間が作り出した金属を握りしめることだけを考え、夜の月に目を向けることができなくなってるのではないかと思います。
最後に
本作から私がもらったものはとても沢山あり、そして大きいです。
文章を書いていく上で、魂を削り何かを求めていくことを根本に置いていれば、世間の評価や他の色んなものにまどわされなくなります。
そしてもしどこかで野垂れ死んだとしても、精神が高貴であれば、それは恩寵の死になりうる。
これからも人生を通じて、まだ見ぬ何かについて考え作り出していきたい、そんなことを教えてくれた本作に感謝して本考察を終えます。