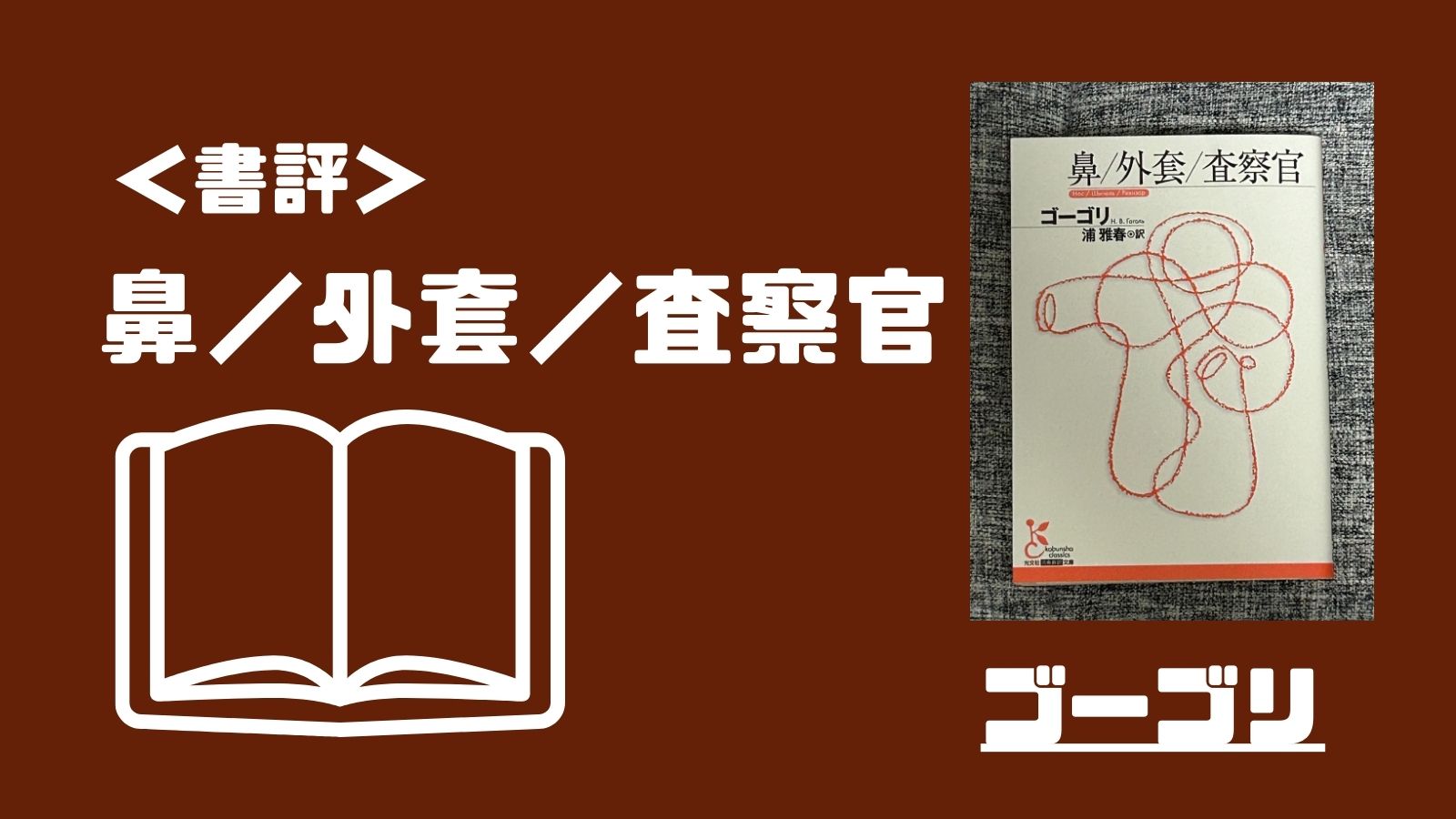「鼻/外套/査察官」は19世紀のロシアの作家、ニコライ・ゴーゴリの短編を収録した作品集です。
ドストエフスキーがゴーゴリの外套を、「我々は皆ゴーゴリの外套から生まれ出でたのだ」と語ったと言われるほどに、近代ロシア文学に影響を与えた、まさに先駆け的作家であり、本作に収録された三作は、まさにそのゴーゴリを代表する作品たちです。
パンの中からなぜか八等官の鼻が出てきて、そのあげく鼻が一人歩きをし始める「鼻」。
ひたすら地味に機械的に仕事をこなす小役人が、心機一転で新調した外套を奪われ、悲劇と妄執が重なり始める「外套」。
ある地方都市に、行政の査察官が来るという噂が広まり、狡猾な市長や、腐敗しきった役人たちがあわてふためく、ドタバタ喜劇の「査察官」。
この上記三作のどれもが、不思議な幻想感やアイロニーが効いていて、今読んでも面白く、特に「査察官」は、非常に古典的で、王道な風刺コメディーなので、スラスラとページが進みます。
また外套にしても査察官にしても、小役人の矮小さ、みみっちさや哀しい空虚さが、リアルに描かれていて、それらの決して理想の人間像とは程遠い、それでも誰もが抱える人間精神にスポットを当てたことが、その後の文学に与えた影響は大きいんだろうなと感じました。
本作の魅力は実は作品だけでなく、翻訳者の浦 雅春さんの解説です。(私が読んだのは光文社古典新訳文庫版)
査察官のような明らかに保守派を刺激する作品を書いたのに、保守派から批判されるとは思いもせずに、大きなショックを受けたり、すぐに嫌なことがあると海外に逃げ出したり、そしてあげく奇妙な宗教心に芽生え、いきなり「農民は聖書以外の本が存在することを知るべきでない」と言って、進歩派からも顰蹙を買ったりと、ゴーゴリの人生は思い込みを狂気で突っ走るジェットコースターのような人生です。
そして最後は、すがった狂信の神父に恐怖をあおられ、何の儀式なのか、断食の為に骨と皮一枚になり、半ダースものヒルが鼻につけられ死に至る。
もう実に凄惨奇天烈! もはやロックンロールまであります笑
浦さんは、ゴーゴリが長い間、ロシアにおいて自然主義やリアリズム文学の祖と言われてきた事に対し反論しており、ゴーゴリ作品の肝は、文脈の整合性の取れないような奇妙奇天烈な出来事、グロテスクさ、哄笑、細部への執拗なこだわりと幻想的ヴィジョンのごったまぜ、と言うような表現をしています。
私は確かにその通りだし、まさにゴーゴリという人間性がそのまま作品に出ているんだなと感じました。
私自身、かなり思い込みが激しく、行動が神経的かつ突飛な人間なので、この解説を読んでゴーゴリの事を、かなり好きになってしまいました←変かしら
「死せる魂」はマストとして、「狂人日記」など他の作品も色々読んでいきたい!
そう思わせてくれるほどの、素敵な読書体験でした。