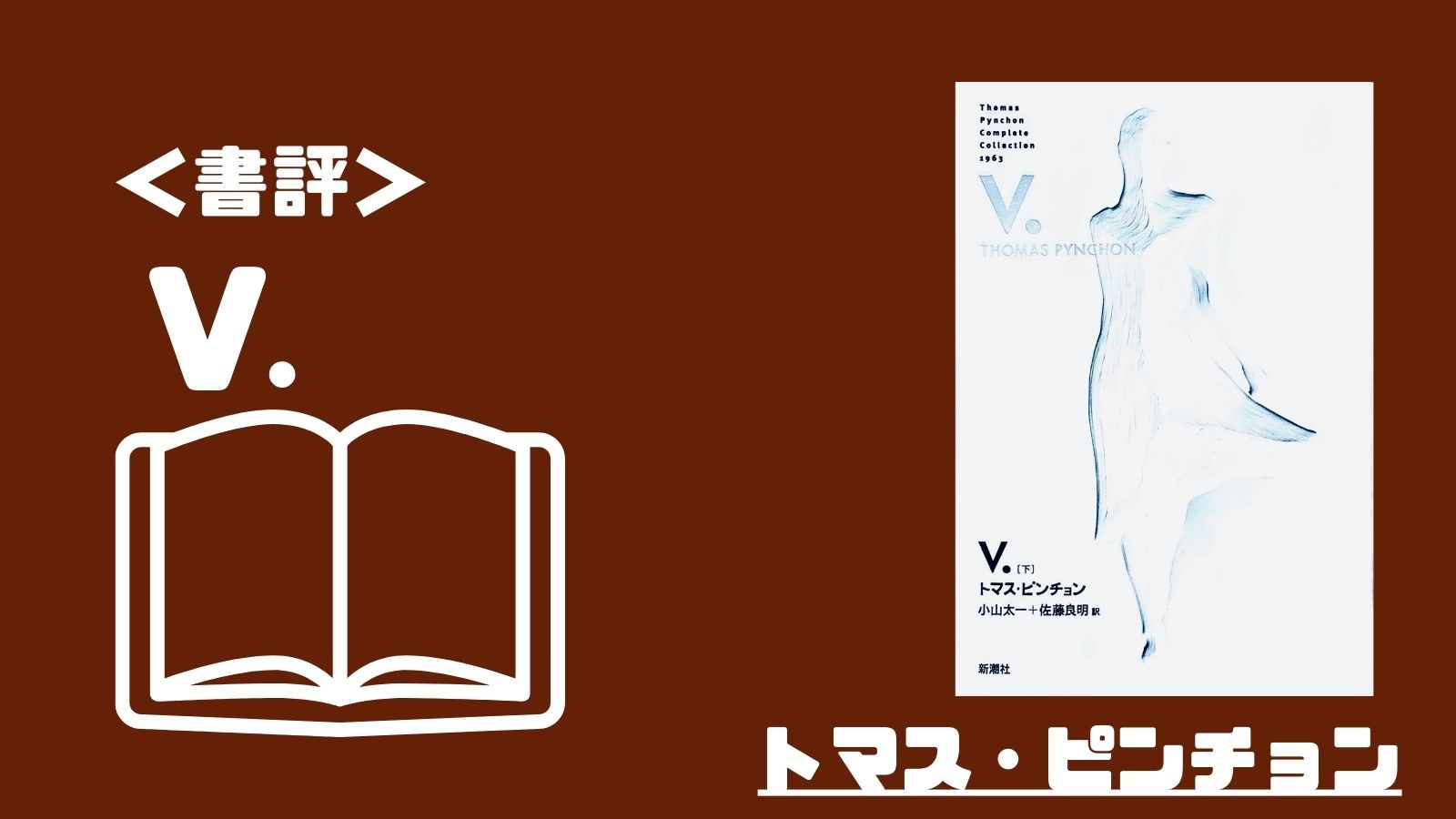「V.」は、現代アメリカ文学を代表し、ポストモダン文学の大家とされるトマス・ピンチョンさんが書いた、最初の長編です。
ピンチョンの小説と言えば難解で、かつめちゃめちゃ長い。そして登場人物も多くて、情報量も天文学的・・・
それが読む前の私が抱えていたイメージで、読んでみると確かにその通りではあるのですが、それ以上に内容がわくわくでぎっしり! 身構えていただけに、その面白さに驚きました。
本作において、文体自体は特段難解ではなく、出来事が分かるように書かれています。そして基本的に全てのベースに情報や思想と共に「物語」があるので、そのエピソード群が楽しめれば、とっかかりに関しては、実は易しいタイプの文学かもしれません。
とはいえ、そんなに人生は上手くいかないもの笑
一つ一つの物語はとっかかりやすくても、それらを繋げる整合性、物語の起承転結のカタルシス、くっきりとしたメッセージ性のようなものを、安易に求めるとしっぺ返しを食らいます。
というより、むしろ本作は、エントロピー増大の法則の文学化という点からか、そういった物を否定するような構成を取っています。その意味で本質が非常に掴みづらい作品である事も事実です。
そんな本作の内部に、自分なりに迫っていきたいと思います。以下、あらすじ以降は、本作の本質的な部分に触れていくので、それが嫌な人はここでストップして下さい。
▼あらすじ
物語は二つのパートを軸に展開する。
一つは1950年代のニューヨークを舞台とした、元水兵のプロフェインのストリートと放浪の物語。
そしてもう一つは、世界に遍在し暗躍する「V.」の女を、探し求めるステンシルが語る、奇妙な挿話群。
マルタ島の都市・ヴァレッタ、英国、エジプトに現れるヴィクトリア、ニューヨーク地下のネズミのヴェロニカ、秘境の地ヴィーシュー・・・
果たしてV.とは一体何なのか、物語は乱打され、解体され、そして加速していく。
本作の軸に置かれている思想。それが「エントロピー増大の法則」です。
これは熱力学の法則で、孤立系において、温度は高温から低温へ移行する。そしてエネルギーは整った状態から無秩序な状態へ散らばっていく・・・というもの。
これを簡単にワタクシなりの解釈で言い換えるなら、物も人もいつかは散らばり無秩序に広がっていく、それは全ての普遍的法則で、宇宙自体も散らばりながら広がり続けているという感じ(違ったらすいません)。
私自身、一時期このエントロピー理論にはまっていまして、散らばっていくエネルギーの中で、生命を個体に、肉体に留めている生物の「維持」の力にこそ、神は宿っているんじゃないかとか、なんとかをお風呂やトイレでぼんやり考えていたのを覚えています。
本作はそのエントロピー思想を、物語に組み込んでおり、ゆえにこそ様々な物語の間に整合性は薄く、ラストにそれが回収され盛り上がっていく、という様なカタルシスはありません。むしろどちらかというと物語自体が解体されていく・ほどけていくような感覚すら抱かせます。
しかしその一つ一つの物語自体が、煌めくパノラマ的、奇想天外で面白く、その乱打と解体の中で神経症的に浮かびあがるような女神を描く、そんなことを本作はやっているわけです。
私自身、エントロピーに対して思いを馳せている人間というのもあるのですが、白状すると実は本作からそこまでエントロピー感を感じませんでした(何だよエントロピー感って)。
というのも私自身は、エントロピーに対し、宇宙や生物が散らばり広がっていくという空間的なイメージに重きを置いているのに対し、本作は放散し、熱が逃げていき、物に、無機質になっていくという性質の方に重きを置き、そこに退廃を重ね合わせているからだと思います。
その意味で私は本作から、どちらかというと量子力学的な情報の転移とか、仏教の輪廻的なものをイメージしました。
言うなれば本作は、エントロピーの爆発感を彷彿とさせるはちゃめちゃさは無く、どこまでも一つ一つは奇妙で不思議な物語であり、それの多発や転移が何かを浮かび上がらせるという感覚。
また本作の特徴の一つなのが、物語全体を覆う虚無感・退廃感です。
私は本作が似てると感じたのは、先週取り上げた村上春樹さんの「風の歌を聴け」と、村上龍さんの「限りなく透明に近いブルー」。
これらが書かれたのは1970年代の後半で、ピンチョンが本作を書いた時期と10年単位でずれてはいますが、60年代のアメリカの夢の終わりの退廃的な雰囲気は共通しています。またデビュー作であり、たまっていた感情や思想、詩的な成分を思い切りぶつけている点もそっくり。(上記の両村上さんの作品もデビュー作です)
その意味で本作が書かれた60年代は、ベトナム戦争の泥沼化やキューバ危機など、様々な変化や衝動が加えられた時代でかつ、アメリカが厳しい現実に直面した時代でした。
本作は60年代の前半に書かれているので、直接上記の事件の影響はないでしょうが、既に変化しつつある夢の終わりの空気・退廃感は本作の軸として、ずしりと沈殿しています。
本作はその退廃感の元で、様々な放散していく物語が描かれていくわけです。
印象深く、かつ哀しいエピソードの数々。
私は都市の地下のワニとネズミの章が特に印象的で、信仰的な描写は元より、少し飛躍するのですが、現代社会において水道から流される生ごみの放出をネズミの広がりに重ね合わせ、人間生活は廃棄物を拡大しているに過ぎない哀しいものという側面を思い知らされた気がしました。
また本作でエントロピーと共に重点的に描かれるのは、サイバネティックスの思想。つまりは無機質化と、人間に対する機械の浸食と同化です。
そのエピソードの軸になるのがマルタ島の話で、第二次大戦の時に包囲され、爆撃され続けた現実の出来事を、孤立系を揺さぶる事象に重ね合わせ、以降は熱を失い、無機質的になり、物と化した人間性に変化してしまった、というような描き方をしています。
また整形医のシェーンメイカーや、整形に熱を上げるエスターの話は、機械化・無機質化していくことへの性的快楽や退廃を描き、また戦争に関しても、作中内の言葉で、兵器という機械と政治という人間性の結託と書いており、人間がエントロピーの放散と共に、退廃し、機械化・無機質化していく様を徹底的に描いています。
そう思うと現代の世界は事実上、スマホに支配されているわけだから、脳まで機械に支配されているとも言え、ピンチョンの懸念はすばり的中しているなあとも思います(もしかしたら私たちの脳細胞もブルーライトと共に放散してるのかも)。
さて、様々な登場人物と物語が交錯したりしなかったりする本作ですが、一応二人の主人公格が登場します。
退廃的なストリート生活を送る木偶の坊のヨーヨー男のプロフェイン。そして様々な手がかりから「V.」を追いかけ探求するステンシル。
プロフェインの方は、アメリカの退廃担当なので筋は分かりやすいのですが、ステンシルの方は、かなりの思い込みと若干の精神の錯乱が錯綜しているので、彼の言っている事、物語が本当なのかも曖昧です。しかしここにもまた作者の重要な意図があります(後述)。
さて、ここからはVについて考えていきます。
ヴィクトリアなど女性の名前、ヴェロニカというネズミ、あるいはヴィーシューという秘境。本作においてVには多くの意味や認識が込め、散りばめられています。
その意味でほぼ確実なのは、Vという存在は女性性だという事です。
女神は英語でヴィーナス、女性器はヴァギナ。考えると人間を生むのは女性であり、始まり・起点には女性がいる。そのような人間の礎・始まりの要素も、Vには込められているかもしれません。
またプロフェインが女性の、家庭へと押し込もうとする、物へと押し込もうとする要素に怯える描写からは、女性=物性=Vという捉え方も出来そうです。
劇中で、役者のメラニーが舞台上で機械に性器を貫かれる描写も、機械化され凌辱されている女神。舞台上の商品やトロフィーとしての物性という、現代社会が未だに抱え続けている問題も包摂している気がします。
そして着目すべきは、やはりマルタ島で、舞台となる都市、ヴァレッタ。これもV。
実はそのマルタ島には、世界最古の巨石神殿があり、そこの眠れる女神像は有名です。ヴィーナスとヴァレッタ、まさにV。
劇中では、第二次大戦でのマルタの爆撃をムッソリーニのオーガズムと表現し、マルタ島自体を岩の子宮と表現している事も興味深いです。
これらの事から、私はVとは、様々な意味や象徴を含む、「女性性」という、人間社会を覆う女神の概念だと思います。
象徴的なのは、劇中における、体に機械や宝石を埋め込まれた神父の服を着た女性が、路上で子供たちにどんどん宝石や体の部位を取られ解体されていく様な描写です。
ここでこれらを踏まえ、本作の物語の本質を自分なりにまとめてみようと思います。
「放散し機械化して退廃化していく、現代では、女神は、信仰は解体され、機械に体を貫かれ、処女を散らされ、路上に、地下に放散されている」
本作はそれを描く物語だったのだと思うのです。神は退廃し、放散し、無機質化する。
本作において主人公が男性二人だったのも、Vという女性性への探求という点からのように思います。そしてプロフェインにもステンシルにも作者の精神は乗っている、男性は常に女神の探究者です。
面白いのは、この二人のV的なものに対するアプローチが全然違う事。
現代アメリカ(50年代)を生きるプロフェインの方は、女性の物性に恐怖を感じ、ストリートに逃げ宙ぶらりんになっています(男性の中には女性への崇拝と共に恐れがある)。
一方で探求者であるステンシルの方は、思い込みや錯乱が激しく、分裂症気味。こっちはどちらかというと2020年代を生きる我々に近いかもしれません笑
さてそんなステンシルが表すことは、この時代(50年代)に女神を追い求める人間なんてのは、分裂症的で思い込みが激しくないと無理であるという、アイロニー的な皮肉。その一方で、思い込みや幻想などの強い力を物語に昇華することこそがVに至る道なのだという、二つの要素がある気がします。
その意味でやはりステンシルの方が、「作家としての」作者に近いかもしれません。(プロフェインは男としてかも)
物語ラストで、ステンシル父は唐突に船ごと、竜巻に巻き込まれて海に沈みますが、ステンシル息子も作者も、Vを追い求め、書く事で、自分が、社会が、世界が沈めた、過去の憧憬や、理想である何かを物語で浮かび上がらせようとしたのかも、そんなことを思いました。
そんなわけで、ここから私は他のピンチョン作品を読んでいくわけですが、聞くところによると、「重力の虹」以降の方が、メッセージ性も開かれているという事らしいので楽しみです。
思えば村上春樹さんも、最初の「風の歌を聴け」では思い切り、自身にたまっていた詩的世界を放出し、ねじまき鳥クロニクルにおいて、読者に対する「光」の物語を与えてくれました。
今後ピンチョンさんの作品のエネルギーや表現がどのように変化していくのかを考えると、とても楽しみです。