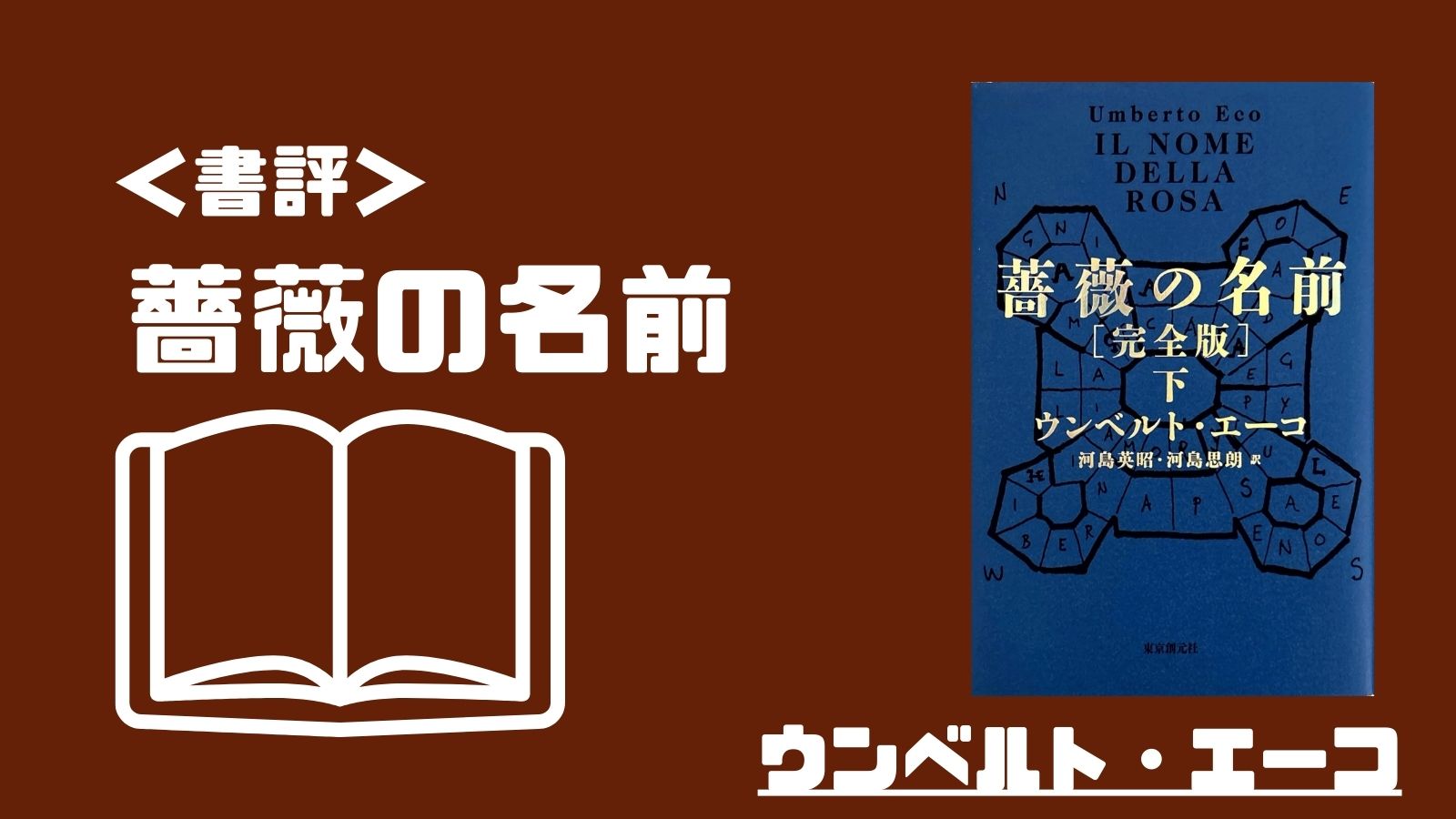「薔薇の名前」は、イタリアの記号学者で小説家のウンベルト・エーコさんが書いた初めての長編小説です。
深淵なテーマ性とエンタメ性が両立している本作は、世界で大ヒットし、現在では海外文学の読むべきスタンダードとして圧倒的な地歩を築いています。
本作は長年、私の中で「読む本リスト」のトップをずっと温めていた一作なのですが笑 昨年の12月、なんと作者の解説やエッセイなどが収録された完全版が発売。
「であるならもう買うしかないやろ!」とクリスマスに購入。分厚い上下巻ながら物語に入り込み、あっという間に読了してしまいました。
さてそんな本作は、作者が記号学者という事もあり、あらゆる構造・場面において「記号」が顔を出し、それが象徴するもの、その中に含むものを洞察する分析的な楽しみがあります。
さらに、それにプラスして王道ミステリーでもあるので、まさにエンタメ性・文学性が両立している、美味しい箇所盛りだくさんの傑作です。
以下のあらすじの後から、その記号の物語に分け入って、書評していきます。
なお、以下の書評では、犯人には触れませんが、物語ラストの描写・本質分部について洞察するので、ネタバレが嫌な人は、あらすじでストップして下さい。
▼あらすじ
ある日、「私」は、中世の老修道士アドソが、見習時代に起きた、七日間の事件を回顧した手記を手に入れる。
そこには、1327年の北イタリアの修道院で起きた連続殺人事件が、聖務日課の時系列により語られていた。
その手記の中で、複雑怪奇な事件に挑むフランシスコ会の修道士、バスカヴィルのウィリアムと若き日のアドソ。
事件は様々な人間の思惑や思想、そして閉鎖的な知の宮殿である文書館の謎を軸に加速していく。
本作の前評判として、面白いけども、序盤に読みづらさがあるという意見をちらほら耳にしていました。
構成として、まず「私」がアドソの手記を見つけた経緯の記述、そして次に年老いたアドソが語る、その当時のキリスト教社会や、師であるウィリアムの人となりを描いた記述と続くので、確かに、そこまで引き込まれる要素はありません
とはいえ、これはゲームで言うチュートリアルパート。
本作は中世のキリスト教社会を描いていて、かつ1300年頃は、ローマでなく、フランスのアヴィニヨンにローマ教皇が移されていたり(アヴィニョン捕囚)、神聖ローマ皇帝の世俗権力と教皇権が対立していたりと、非常に混乱していた時代です。
そのあたりの事情がある程度描かれるので、ここを読んでおけば、本書の出来事の概ねは理解出来るわけで、私はとても親切な構成だなと思いました。
また本作は確かに舞台は、中世社会でキリスト教を中心に描かれる物語であるものの、しっかりした王道ミステリーでもあります。
序盤からウィリアムがホームズで、アドソがワトソンなのが、かなり分かりやすく表現されていますし、他のキャラクターもめちゃくちゃ立っています。(個人的に好きなのは細密画家のアデルモと、厨房係の助手、サルヴァトーレ)
その意味で、手記のパートを越えちゃば、すっと、物語世界に入り込めるようになっていて、他の古典作品よりも全然ハードルは低いなと感じました。(ただし分厚いけども)
先程、手記パートをゲームのチュートリアルと表現しましたが、私が本作を読んでいる時に、ずっと感じていたのは「めちゃくちゃゲーム的だな」という事。
本作は、山頂にある修道院を舞台に展開するクローズド・サークルミステリー的な要素もあるのですが、その修道院が本当にRPGに出てくる街のような感じで、空間的な自由さや広がりがあり、自身がプレイヤーみたいな感覚を想起させるのです。
日本のRPGに、ペルソナというゲームシリーズがあります。そのナンバリングの3以降は、拠点が一つの町で、そこでの行動が冒険に左右するのですが、本作の修道院はまさにその町を移動している感じ。
更にゲーム的なのは、本作の最重要スポットである文書館。これは、まさに妖しく蠱惑的なダンジョンそのものです。
どこかにあるはずの「アフリカの果て」という部屋。また各部屋に施される侵入者を襲う仕掛け、それに加えラスボスとのバトルっぽいのもあるというエンタメっぷり。
多分、エーコさんが記号学者なのもあり、作品の記号的組み立て方がゲームと親和性があって、本作品は、このような雰囲気に仕上がったのだと思いますが、それは確実に本作の魅力を増しています。
少なくとも私が読んできたミステリーで、その舞台がフィールドのように浮かび上がってくる作品は、本作の他に知りません。
その上、「異端」の概念、「清貧論争」など、色々な中世キリスト教の知識にも触れることが出来るので、読んでいて、一石四鳥くらい得るものがある、知的好奇心の充足度がとても高い作品だと、私は感じました。
また本作が、「笑い」の可能性を真摯に描いているのも、魅力の一つです。
笑いは道徳規範の破壊を促す倒錯に過ぎないという意見に対し、想像力の飛躍、新しいものの創出という、ある種そこに神の意志を見るという見方をしている・・・私はそのように本作の「笑い」論を解釈していますが、この価値観は、目からうろこで、とても好きな価値観です。
個人的に、ニーチェが言う、違うものから違うものに飛びうつる飛躍のエネルギーは、もしかしたら「笑い」に通じているのかもとも思いました。
何かから、想像しえない何かを繋げたり、飛び移る。もしそれが「笑い」なら、笑いはとても記号的なのかもと思います。
そして、違う記号と記号を繋げ合わせ、全く違う何か、新しい何かを創出する。新しさを創出するもの=神。
もしかしたら記号こそが神へと至る道のヒント・欠片なのかもしれません。
さてここからは本作を覆う記号について考えていきます。
本作の文書館は、それぞれの部屋にイギリス・フランスのように世界地図の様な感じで名前が割り振られています。これは世界を図書の森に閉じ込める行為であり、世界の記号化でしょう。
そもそもが書物や物語は、文字や文という記号の集合体。そう捉える事も出来ます。そうすると本作の文書館は、記号の壮麗な大宮殿の様な場所に見えてきます。
しかしその宮殿は、特権階級に独占され知識は閉じているわけです。つまりこれは閉じている、世界へ意味を創出出来ない状態の不完全な記号です。
そしてそれがラストでは、美しく徹底的に燃え尽きていく。私はここに不完全な記号が、空気へ外部へ表出する開放・昇華なのではないかと感じました。そしてまたあの多角形の建物が燃える姿にタイトルである薔薇の姿も浮かび上がってくる。
さてそうなると、ここで重要になるのは、タイトルにある薔薇の意味。
これは作者のあとがきの、美しいけど有意義な意味をことごとく失っているという、記号の器という意味ももちろんあると思いますし、アドソが得た女性のぬくもりという、親愛、慈愛から繋がる神への寓意という点ももちろんあると思います。
しかし私は様々な意味が込められる前提の上で、薔薇の本質とは、小説・物語そのものを表しているのでは、と思うのです。
様々な書物が燃え、文書館が薔薇のように燃える。そしてそれらを我々が知りえるのは、アドソが書いた手記、つまり物語のみ。
その意味で、作者は、神が宿るのは記号の集合体である物語の中なのではないか、そう考えて、この小説を書いたのではと思うのです。
つまり本作は、記号の集合体であり、美しく、あらゆる意味や象徴を込める事の出来る物語への、作者のラブレターなのでは、そんな事を私は思いました。
物語=薔薇、その名前は本作の内容や象徴、込められた寓意、そして神。
一方で、本作は書物や知識・好奇心への危険も警鐘しています。
本を読み、物語や知識を取り込む事は体に毒を入れる事でもある、そう警告しているのです。(読書は普遍的な思想を育むだけでなく、歪んだ思想も育む事がある。だからこそ面白いのだと思います。安全で口当たりがいいだけのものは、毒にも薬にもなりません)
そしてそれらの描写もまた、触れたら棘が刺さり血を流す事もある、薔薇の象徴に含まれているのかもしれません。
本作はミステリーやゲーム構造を駆使し、記号と物語・神の可能性を描いた、本を愛する人、必読の書なのだ、そんなことを思うのです。